一方、ヴァタ・ヴァタというバーは若いごろつきがよくたむろしていたので、情報収集に役立った。しかしそこはトラブルや喧嘩も多かったので、私が行こうとすると、道ばたの連中が、今日は不穏な動きがありそうだからやめておけと忠告してくれたり、どうしても行くなら用心棒を連れて行けと言って、ごつい男をつけてくれたりしたものだった。有名なグループの動向は、アリやその他の色々な友達が知らせてくれるので、私は居ながらにして情報を知りうる立場にいたのだが、あの、いなくなったカサイの人たちがやっていた「ムトゥアシ」や、その他の部族ごとの音楽、さらにまだ陽の目を見ない若い無名グループで、アングラに走っている奴等の情報などは、そんなところでないと仕入れようがなかったのである。バーは危険ではあったが、そうした貴重な情報交換の場所だった。そこで得た情報で、私は数々の若いアーティストに出会うことが出来た。
しかし、ズジさんは、そんなところに出入りしはじめた私をはらはらしながら見守っていたようである。「あんまり近づくな、バーならほかにいくらでもある。」確かに町にはもっと気軽に営業している店も多かった。サウンド・システムがないので、ラジオを何台も積んで大音響で鳴らし、小学校の机や椅子のようなものを通りに出して、ズジさんのように自分の家の台所の冷蔵庫でビールを冷やして売っている家が至るところにあった。「音楽が聴けてビールが飲めりゃ、それでいいじゃないか。何を好き好んで、あんな危なっかしいところへ行きたがるんだ?」とズジさんはよく言った。まるで保護者のように振る舞いはじめたズジさんをケムたく思いながらも、私は彼の好意に応えるために、彼の指定する「優良な」バーへ通ったりもした。それはそれで、見るべきものも多かった。そうした小さなバーは、定職の少ないこの街では貴重な収入源だった。そんなところは、たいてい家を守っている家族が経営していたから、ザイール人の生活に直に触れられる良い機会でもあった。
ディアカンダのすぐ北に庭付きの家があって、そこでは庭に置いた藤棚の下でビールを飲ませていたが、暇なときはよくそこへ行っておばちゃんと世間話をしたものである。ザイールのおばちゃんと話をするのは、日本のおばちゃんと話をするのと違って、かなりの体力と気力を要する。そのおばちゃんは、自分でビールを売っておきながら、よく私にビールをおごれと言った。言う通りにすると、ただでさえ快活なのに、より一層快活になって、唾が人の顔に雨のように降るのも構わず、いろんなことをまくしたてる。話の内容は、たいてい女のことだった。「男たるもの、行った先々で女を作らねばならん。」どこからそんな理屈が出てくるのかさっぱりだったが、「とにかくお前がここへ来てもうかなり日が経つというのに、娘と歩いているのを見かけたためしがない、お前はザイール人の女が嫌いなのか。」と泡を吹いてまくしたてた。「そんなわけではない」と言うと、「ならばどうしてザイール娘を口説かん。」と言って大きな体を乗り出してくる。「いや、私は日本に決まった女がいて・・・」と口ごもると、「何を地球の裏側のことをほざいとる。」と言ってまた身を乗り出してくる。そんなことの繰り返しで、とうとう私は座っている椅子から押し出され、自分の飲んだビールのおよそ倍量のビールをそのおばちゃんにおごらされてそこを逃げ出すのだった。
ある日ホテルに帰ると、ズジさん以下従業員がみんなにやにやしながら私を迎えるので、なんだと思って部屋に入ってみたら、なんとそこに全裸の若い娘が横たわっていた。「ズジさんっ」あわてて駆け降りて来た私を見て、みんな笑い転げながら逃げてしまったので、あのおばはんの差し金かと思って行ってみたら、逆に「女に恥をかかせるのは男のすることではない。」と、マジにすごまれてしまった。とにかく部屋に戻って、「これこれこういう訳で、かくかくしかじかで・・・」と何とか彼女をなだめすかしてお引き取り願ったのだが、そのあとが悪かった。そのおばちゃんは声もすごかったが、性格はまさに人間拡声器のようなもので、この噂は瞬く間にキンシャサ中の路地の奥にまで知れ渡り、翌日には「あの日本人は、せっかくのザイール娘をソデにした。あれは役立たずではないか。」などと、あらぬ噂まで立てられる始末だった。
とにかく、規模の違いはあれ、このようにバーにはトラブルが付き物だった。それが夜ともなるとなおさらだった。大きな店では入口に用心棒が頑張っているので、たいていのことは彼等が片づけてくれるのだが、小さな店や、露天営業のところ、さらに流しのミュージシャンが立ち寄るところなどは、喧嘩に明け暮れていたといっても過言ではない。しかしそうした店には、アングラに走ったミュージシャンがゲリラ的にギグをやったりしていたので、それを渡り歩くのもまた楽しみのひとつだった。そうしたギグは、あまり大っぴらには公表されず、広場に貼られた、たった一枚の小さな張り紙か、ヴァタ・ヴァタのようなバーへ行って知るしかなかった。
今ではすっかり有名になった「ウェンゲ・ムジカ」を初めて見たのも、偶然立ち寄ったそんな場末のバーのひとつでだった。当時彼等はキンシャサの若い連中の心をつかみはじめたところだった。その演奏はカサイの人たちの演奏で感じられたような、危ない武骨さに満ちあふれていた。ロコレとコンガを多用していて、非常にパーカッシブな演奏だった。ギターはビバよりもはるかにアグレッシブで、リズム・セクションの堀の深さはヴィクトリアを凌いでいた。歌はソロよりもコーラスに重点が置かれていて、その和音は、明らかにどこかの部族特有のものと察しがついた。彼等は、明らかにビバともヴィクトリアとも違う、新しいスタイルの美学を追い求めていた。それはアレンジの中に如実に現われていた。武骨に聞こえた演奏も、よく聞いてみると、歌を聴かせる部分、リズム・オンリーになって突き落とす部分、それと対照的にメロディアスな分厚い音で盛り上げる部分と、明確に計算されていた。さらにダンスも、「アニマシオン」と呼ばれるかけ声も絶妙にタイミングが計られていたし、ステージングが何よりもショウ・アップされていた。ダンスは、ほかのバンドが軽めのやさしい動きのものに簡略化される流れにあるのに対して、彼等のものは部族的な腰の動きの激しいものだった。どれをとっても、今のザイール音楽の大勢の流れに明らかに反抗していた。ビバやヴィクトリアなどが、いわば親方日の丸式のワンマンバンドなのに対して、彼等は明らかに、好きなもの同志が集まって始めたバンドらしいバンドだった。
私はそれを聞きながらゾクゾクしていた。初めてビバのレコードを聴いたとき以来の、破天荒な感動をそこに感じたからである。それと同時に破天荒なだけではない、音楽に対する慎重で緻密な姿勢をそこに感じたからである。しかしそうした若手バンドにはトラブルも多かった。現にその夜のウェンゲのギグで、私はあわや乱闘に巻き込まれそうになったのである。そのバーは、特にセキュリティのしっかりしているわけではない、中規模のところだった。演奏中に突然騒ぎ声がしたかと思うと、ステージに向かって、何十人もの若者が乱入し、照明が消え、音も消え、あたりが騒然としてしまった。私の耳許で誰かが、「逃げろ、やばいぞ。」とささやいた。彼はそのまま私を無理やり引っ張って場外へ出た。名前も聞かなかったが、彼はそのまま気をつけて帰れとだけ言って、足早に去っていった。客は蜘蛛の子を散らすように逃げ、直後に軍のジープが横付けされた。私はすばやく雑踏の中に身を隠した。次の日にわかったことだが、闖入者はウェンゲの人気をねたむ別のバンドのファンだった。その夜の乱闘で数人の死者が出、店は掠奪され、私の滞在期間中には二度と再開できなかった。しかし、こんなことは日常茶飯事らしい。
例によってズジさんは、あんまり近づくなと言った。「音楽をもっと聴きたいお前の気持ちも分かるが、けがでもしたら何にもならんぞ。第一ここにはろくな消毒薬さえないんだからな。」確かにその通りだった。しかし私はその後もウェンゲを探し求めた。あの音があまりにも鮮烈だったからである。しかし、アリでさえ確たる情報を握ってはいなかった。タクシー・ビスの肉林の隙間から、ウェンゲ・ムジカと大書きしたワーゲンのワゴンを見かけると、車を止めさせてガキを捕まえ、あの車の行き先を知らんかと詰め寄った。ラジオでわずかにウェンゲのギグの情報が流されると、遠いところまで出かけていって、もぬけの殻の会場で地図を地面にたたきつけることもあった。彼等の動向は、いかにヴァタ・ヴァタの連中をもってしても杳として知れなかった。彼等のうちで、ウェンゲを見た者は残らずファンになっていたから、そんな奴等も情報を知りたがっていた。しかし、ついに今回の滞在中、二度とウェンゲを見ることは出来ず、録音したはずのテープも、帰国のどさくさの中で紛失してしまった。彼等に再会したのは二年後のブリュッセルで、その時にはザイールの若手バンドのホープになっていた。しかし、音は既に変質していた。
コンセールの楽しみ
 キンシャサでの楽しみは、なんといっても週末ごとに行なわれる夜徹しのコンセールである。私が最初に見たのは、ヴェヴェ・センテールで行なわれた、「ヴィクトリア・エレイソン」のコンセールだった。その日、アリは夜中に私を迎えに来て、二人でムココでビールを引っかけてからヴェヴェ・センテールへ歩いて行った。彼はローディーというその立場を利用して私をロハで入れてくれた。ヴィクトリアというバンドは、結成当初のビバの歌手の一人だったエメネヤ・ケステールが、首領ウェンバの目を盗んで、主だったミュージシャンを引っこ抜いて作ったグループである。
キンシャサでの楽しみは、なんといっても週末ごとに行なわれる夜徹しのコンセールである。私が最初に見たのは、ヴェヴェ・センテールで行なわれた、「ヴィクトリア・エレイソン」のコンセールだった。その日、アリは夜中に私を迎えに来て、二人でムココでビールを引っかけてからヴェヴェ・センテールへ歩いて行った。彼はローディーというその立場を利用して私をロハで入れてくれた。ヴィクトリアというバンドは、結成当初のビバの歌手の一人だったエメネヤ・ケステールが、首領ウェンバの目を盗んで、主だったミュージシャンを引っこ抜いて作ったグループである。
その音は、当時のビバ・サウンドが度派手でアグレッシブなロック調だったのに対して、エメネヤのウェットな声を存分に効かせた、クールでエレガントなものだった。演奏のテンポも、ビバなど新生のグループのほとんどが、かなりのアップ・テンポだったのに対して、ヴィクトリアのそれはまさに失速寸前の低空飛行といった感じで、腰を直撃するような、のたうつグルーヴ感は何とも黒い独特の心地よさを持っていた。それでいて、おじさんたちがやっているような、あくまでもルンバに徹した職人芸とは違って、ファンク的なアクの強い反骨精神が、歌詞にもアレンジにもにじみでていた。ビバに続いてヴィクトリアのデビュー・アルバムが日本に輸入された頃、それを聞いた我々の間で、ビバ派とヴィクトリア派に分かれてしまったぐらいだった。私はどちらかというとヴィクトリアの方が好きだった。なんといっても渋かったし、ビバが勢い一発のロック色を前面に押し出していたのに対して、ヴィクトリアの音は、限りなくルンバに近いロック的な野太いファンクという、何とも際どいところを行っていたからである。ビバは、破壊力はすさまじいが、一本調子なのでそのうち飽きてしまうのに対して、ヴィクトリアの方はウェットな分、様々なバリエーションが歌の中に込められていて、飽きを感じさせなかった。
実際、ナマで見た彼等の演奏は、より一層エキセントリックだった。ステージにあがったメンバーは、はた目に見てもいやいや演奏していたし、テンポはレコードよりもずっと遅かった。歌手たちのダンスに至っては、まさにスローモーションだった。それでいてしらけた感じなどは微塵もなく、それどころか危うく止まってしまいそうだったが、その重いグルーヴは、一体何がそうさせるのか、聞く者の腰をしっかりとつかんで揺り動かすかのようだった。まだ夜は始まったばかりで、明らかにほんの小手調べという感じの演奏だったが、私は会場に入ったなりその場に凍り付いてしまった。その失速寸前の重いグルーヴの絡み合いに、すでに気もそぞろの状態だった。アリが小突いたので我に返った。客はほぼいっぱいだったが、アリのはからいでVIPしか入れない一角に席を取ることが出来た。我に返って辺りを見回してみて、今度は観客の服装に驚いた。このくそ暑いのに、分厚い皮ジャンや皮パン、スーツにロング・コートまで着込んでいる奴がわんさといたからである。ものすごい光景だった。着ているものが半端じゃない。どれも、度派手にデザインされた、明らかなデザイナーズ・キャラクターものだったからである。そんなブランドもののことを彼等は「グリッフ」と呼び習わしていて、私も日本でそれを聞き知ってはいたが、まさか、こんな泥だらけで砂埃が舞散り、悪臭ただよう通りを、それを着て集まってくるとは思わなかった。しかも、来る奴来る奴がどれもこれも一筋縄では行かない格好をしていて、今までどこに隠れてたんだと思うほど、たくさん集まってくる。生演奏の迫力もさることながら、この物々しい異様な雰囲気はさすがにすごい。
そこで初めて、ヴィクトリアの首領エメネヤ・ケステールその人に直接会った。彼はレコードのジャケットに見られるような、苦虫をかみつぶしたようなこわい顔をして、重みをたたえた物腰で私の握手に応じた。すでに夜半を過ぎていたが、彼はステージに上がろうとはせず、連れてきていた側近と思われる男と二人のアメリカ人の女性を相手に、慣れない英語で話し合っていた。その二人の女性は観光客ではなく、政府関係の何かの仕事でここに滞在しているらしかった。男はエメネヤの知人で、たまたま彼女たちの案内役をその筋から依頼されていたのである。週末の楽しみのために、彼が二人をここに案内してきたのだった。だから彼は終始緊張していた。VIP席にいるとはいえ、コンセールにトラブルは付き物だからである。
ミュージシャンの体が暖まってきたのか、演奏が次第に熱を帯びてきた。私の関心が、女たちを離れてステージに戻っていった。往年のヒット曲が何曲か演奏され、私はそれに合わせて歌詞の一部を口ずさんだりした。徐々に気分が盛り上がってきて、エメネヤがステージに上がって行ったのに合わせて、我々もフロアに降りて行った。スターを迎えて客席は盛り上がった。簡単なスピーチのあと、エメネヤが曲を指示して、実にゆっくりと演奏が始まった。ザイールのルンバの演奏は、たいていゆっくりとした歌から始まる。それまで席に座って酒を飲んでいた客たちは、興がのればアベックでフロアに出てきてチークを踊りはじめる。エメネヤの知り合いの男は髪の黒い方と、私は金髪の方と踊った。イチャーリ先生の特訓の甲斐あって、チークのステップもすでにマスターしていたから、私はうまく彼女をエスコートすることが出来た。エメネヤの甘いヴォイスが、いやがうえにも雰囲気をもり立てる。実にゆったりとした、たゆたうようなリズムの流れに身を任せて、ビールのほのかな酔いと、魅力的な彼女の甘い香りのなかで悦楽の時を過ごした。まるで絹のように細い金髪が私の頬にかかって、頭がくらくらしっぱなしだった。そしてそのあと徐々に演奏が激しくなってゆき、いよいよ本格的なダンス・パートに達すると、アベックは離れて思い思いに踊り出す。彼女は明らかにダンスは苦手のようだったので、ごく簡単なステップを教えた。二、三曲一緒に踊った頃には、彼女も腰の動かしかたが身についてきた。そうして首尾良く何曲か踊ったあと、我々は再び席に戻って飲みなおした。
すると、エメネヤも何故か戻ってきて会話に加わった。そうしてさらに何曲かを、客席でビールを飲みながら楽しんだあと、いい時間になったので二人の女性は、連れの男に導かれて帰っていった。エメネヤは明らかに残念そうに見えた。私も全く同じ気持ちだった。彼女たちは、若くてほっそりしていて、実に魅力的だったからである。ちょうどそのとき、ジョー・ノロが入ってきた。彼は、古くは「アンチ・ショック」の歌手だったが、自分の歌心を最大限に表現するべく、自らのグループ、「ショック・ムジカ」をヨーロッパで結成してしばらく経っていた。紆余曲折あって、今はキンシャサに舞い戻り、ヨーロッパで仕入れてきた服を売りながら食いつないでいた。「どうだ、お前も一着買わないか、これはゴルチェの最新モデルだ。」明らかに日本人の私には派手すぎるデザインだったので、丁重に断わった。彼の素性はともかく、その歌にはやるせない男心を切々と歌い上げる哀愁がこもっていただけに、本業の音楽活動ではなく、服を売り歩かないと生活できない彼の現状に、たまらない寂しさを感じた。エメネヤにも挨拶したあと、服が売れないので彼は肩を落として程なくそこを出て行った。
そのあとエメネヤは再びステージに向かっていったが、明らかに気が抜けていた。私はさらに何曲か聞いたあとそこを出た。これが初めて経験したキンシャサでのコンセールだった。美しい白人女性と、ちょっとだけいい思いもしたし、それにつられて鼻の下をのばしているエメネヤの横顔にもふれた。逆境に苦しむ孤高の歌手の後ろ姿も見た。確かに尻すぼみに私の興味が萎えていったのは否めないが、それでも初めてナマで見たステージは想像以上のものだった。キンシャサでの音楽生活は、こうして静かに始まった。私はその感触で十分に満足し、求めるルンバのニュアンスの、確かな手応えを感じとっていた。しかしヴィクトリアは、その後すぐにカサイ州方面へツアーに出ていってしまい、私の滞在中二度と会うことはなかった。また、魅力的だった二人のアメリカ人女性とも、二度と相まみえることはなかった。
ここでのコンセールは、大体決まったバーで決まったグループが決まった曜日にやることになっている。いずれも夜八時からなどと書いてあるが、そんな時刻に行っても店さえ開いていない。「八時と書いてあれば夜中のことだ」というのがここでの通り相場である。マトンゲ周辺はキンシャサの中でも音楽の盛んなところなので、至る所に大小のライブ・バーがあった。最も有名なのは、ヴィクトワール広場の南東側に面している「ヴィ・ザ・ヴィ」、しかし当時そこは営業していなかった。次に先ほどの「ヴェヴェ・センテール」がある。ここはヴィクトリアのほか、ヴェヴェ・レーベルが推す若手バンドの対決ライブなどが企画されていた。ヴィクトワールをずっと東に行くと、先日アンチ・ショックのレペで私が醜態をさらした「イル・デ・カンボジ」、ここは当時「ストゥニング・マンゲンダ」という、かつて「ストゥカス」というバンドをやっていた連中の残党が本拠地にしていた。ヴィクトワールをずっと西に戻っていくと、広場を過ぎたあたりの北側に「マディゾン・スクウェア」があり、そこでは「ショック・スターズ」がやっていた。さらに西へ行くと、「アンチ・ショック」がコンセールに使っている「キンプァンザ」というバーがあった。書きはじめるときりがないが、重要なものをあげると、「ザイコ・ランガ・ランガ」が分裂して、当時キンシャサを中心に活動していた「ザイコ・ファミリア・ディ」の本拠地「ンゴス・クラブ」、そこから少し離れたところにある、「O.K.ジャズ」の本拠地「フォブール」、さらに「アンピル・バクバ」が本拠地にしていた「ゼニット」など、大体そのぐらいが、マトンゲ周辺での主だったライブ・バーということになる。
そうした大きな店は、昼間は営業していないか、大物のグループのレペ場として場所を提供し、コンセールのない平日の夜などは、ビデオを上映したりレコードをかけたりという、日本でいうところのクラブ営業をしていた。店の造りは、最もゴージャスなのが「ヴェヴェ・センテール」で、建物の一階と二階を吹き抜けのホールに仕立ててあり、二階は回廊のような桟敷になっている。帰国してからも、たまたま二階に桟敷のあるホールへライブをしに行ったりすると、キンシャサ経験者どうしで、「よくここはヴェヴェのようだ」と言ったものである。入口の正面奥にステージがあり、その手前すぐにダンス・フロア、さらに手前が客席、そして入口左手がバー・カウンターになっている。
かつてビバが本拠地にしていた「ヴィ・ザ・ヴィ」をはじめ、その他のたいていの店は敷地全体が高い塀に囲まれていて、その中にバー兼事務所の小屋がひとつと、ステージ兼ミキシング・ブースの屋根付がひとつという程度だった。その高い塀の上には、たいていビール瓶を割ったのを逆さに埋め込んであって、塀を乗り越えてタダ見を決め込む輩を防いでいた。それでもコンセールが始まると、その高い塀にガキがよじ登るので、店の人間が長い柄の着いた箒で威嚇するがよく見られたものである。いかに小さなバーといえども、ステージを持っているところは、その前にダンス・フロアが必ず設けられていた。しかしそれらはたいてい青天井だったので、コンセールの途中でスコールにでも見舞われようものなら、瞬く間にパニックに陥り、客のほとんどが小屋かステージの屋根の下に逃げ込んでコンセールは中止、時には払った入場料を返してくれることもあった。
ヴェヴェ・センテールとは別の意味でゴージャスなのは、当時O.K.ジャズが本拠地にしていた「フォブール」というバーである。そこはマトンゲの街はずれにあった。広い敷地はリゾート地の美しい庭園のようになっていて、南国の浜辺を思わせるような、棕櫚で作られた小さな小屋があちこちにあった。客席はいくつかのブロックに分かれていて、それが段々畑のように扇形に広がり、その間を花で飾られた小径が通っていた。私はその美しい店が大好きだった。O.K.ジャズは、はるか昔、一九五六年に結成された、当時のザイールの最も古いグループのひとつだった。独立当初のアフロ・キューバン大旋風の時代から、歌は世につれてスタイルを変えながら、三〇年近くも連綿と続いてきたビッグ・バンドである。そこの首領は、一九八九年の一〇月に亡くなったフランコという人物である。彼は、名実ともに押しも押されもせぬザイールのトップ・スターだった。日本ではザイールの音楽というと、パパ・ウェンバの名前がまず出てくるが、キンシャサでザイールを代表する音楽はというと、なんといってもフランコであり、O.K.ジャズだったのである。彼はこの時点で既に病魔に冒されており、入退院を繰り返しているという話だった。また、ベルギーのブリュッセルに移住して久しいが、最近戻って来たという噂もあった。
ディアカンダの一階のバーでも、ほぼ人が起きている間中、O.K.ジャズが大音量でかかっていた。もちろん私も日本で何枚かのレコードを持ってはいたが、正直言って古くさい退屈な音楽としか感じられなかった。しかし、キンシャサへ来て、どんなグループよりも広くザイール人に受け容れられているO.K.ジャズを知り、毎日階下から聞こえてくる音に慣れ親しむにつれ、名人芸が生み出すその豊かな音の情感に目覚めていった。しかしキンシャサの若い連中にとっては、その音はまるで時代遅れのマタタビ演歌みたいなものだった。私がついに「O.K.ジャズを聴きに行くぞ」とアリに言ったとき、アリは、「あんな、おっさんが聴くようなもん・・・」と肩をすくめてあきれかえったものである。「わかったよ、じゃあ俺ひとりで行って来る。」というわけで、私はフォブールを捜して、かなり遠い道のりを歩いて行った。
さすがに老舗のコンセールとあって、集まってきた人々はほかのコンセールで見られる人たちとは、ひと味もふた味も違っていた。まず会場の周囲をぐるりと埋め尽くしたピカピカのベンツやBMWが目を引いた。さらに当然のことだが、年齢層は思いっきり高かったし、見事なまでにまるまると太った貫禄たっぷりのおじさんやおばさんばかりだったから、ファッションも上等のリプタや、誂えのフォーマル・スーツで固められていた。なかには、格幅の良いいかにも裕福そうなおじさんと、若くてキュートで釘付けになるほど美しい娘という、明らかに不自然なカップルもあった。どこの世界でも男のやることは同じもんだと思った。
ちなみにO.K.ジャズの正式名称は、「Le Tout Puissant Orchestre Kinois de Jazz」といい、日本語に訳すると、「キンシャサのジャズ界における全能のオーケストラ」ということになる。まさにそれはオーケストラと呼ぶにふさわしいものだった。ドラム、ベースにギターが三人、パーカッションがさらに数人いて、ホーン・セクションも五、六人はいた。歌手に至っては看板スターがざっと五人、バンドの二軍、三軍まで入れると、一体何人いるのかわからないほどの大所帯だった。その分厚いアンサンブルは、ロック的な激しさやエネルギーが昇華されていったあとの、すべてを知り尽くした上でアレンジされた、緻密かつ大胆、スタティックかつダイナミックな、雄大な音の世界だった。ギターの弦の一本一本、ドラムのスティックの先のひとつぶひとつぶのタッチの音が、手に取るようにはっきりと聞こえた。それはまるで鬱蒼としたジャングルの彼方から乾いた風に乗ってやって来た赤土の粒が、ザイールに伝わる呪術の力によって最も厳密な位置に射止められたかのようだった。それなのに全体は大きな流れとなって複雑に絡み合い、あたかも上等の絹の織物にふれるかのような感触があった。しかもそれは朝まで決して乱れることがなく、それでいて完璧なアレンジにありがちな退屈さなど微塵も感じられなかった。それは実に贅沢な時間だった。ナマで聴く彼等の音に、私は文字どおり時を忘れて酔い続けた。バックの演奏もさることながら、おそらく当時のザイールで考えうる、メロウな路線では最も豪華な歌手陣による生演奏を、私はほぼかぶりつきの位置で夜明けまで楽しんだ。 その日はゲストが来ていた。なんと、かつてザイコ・ランガ・ランガで、そのかすれ声による甘いボーカルで全ザイール女性の股間を濡らした歌手、ディンド・ヨーゴである。フランコとディンド・ヨーゴ、この取り合わせは、ファンならば垂れた涎が止まらないほどの大盤振舞だったが、実はフランコが出演したかどうか、今となっては確信が持てない。各資料を調べてみると、この時期フランコはベルギーにいた可能性が高く、私がフランコと思った人物は、実は別人だったのかもしれない。いずれにせよ、その姿を見たのは、ほんの数曲だった。さて、コンセールの楽しみ方は様々である。週末ともなれば、マトンゲに限らず、キンシャサ中の全ての通りで大小さまざまのコンセールやギグが行なわれているといっても過言ではない。それらは夜通しやっているので、はしごしながらキンシャサの夜を満喫するもよし、ウェンゲを探し求めたように追っかけをするのもよし、わけのわからん酔っぱらいのおっちゃんの弾き語りを道ばたで聴くのもよし、過激な民俗音楽のライブを聴きながら聴衆とともに奇声を上げるのも、またよいものである。 その頃には、すでに私の腰振り踊りも、周りの人から一応ダンスに近いと認めてもらえるまでに上達していた。見物人は毎日よく飽きもせずに見物に来ていたが、さすがにその頃には半分に減っていた。いや、半分も残っていたというのが正しいのかも知れない。初めの頃は、何ともいけずな連中だと思ったものだが、私の腰の動きが板についてくるにつれ、ヤジの中に適切なアドバイスが混じるようになってきた。タイミングが違うぞと言って、手をたたいて指示してくれる奴がいたり、わざわざ私の真ん前にやってきて、自分で見事なステップを踏んで見せてくれたりするおやじもいた。ゆったりとしたチーク・ルンバのニュアンスを出そうというときなどは、先生が何度悩ましげに腰をくねらせても、正直言って私には気色悪いだけで、とてもその通りやる気にならないでいた。すると、人垣の中でじっと見ていた若いキュートなおねえちゃんが、業を煮やして私の前に進み出て、いきなり私に抱きつくと、体を密着させたまま腰をくねらせはじめた。「おおうっ、」という歓声が周りで上がり、「どう?、これでもわからないの、それでもあんた男なの?。」その言葉も耳に入らず、私はただただ快感の中で頭がくらくらするばかりだった。やっと離れてくれたときには、涙が出そうになりながら倒れそうになっていたが、それでもどうにかナマのクルーヴを体感できたような気がした。先生は、全くどこまで堅物に出来てやがるんだという顔でこっちを見ていたが、それでも何となくリズムのタメを腰の動きに合わせるという間の取り方を、おぼろげながらつかんだ。ルンバ・ライのレペが始まったのと、いよいよロコレを使っての実践的なレッスンが始まったのは、ほぼ同時だった。課題に使われる曲は、古いものから新しいものに変わってゆき、テンポや情感に応じてどうたたき分けていったらよいかなど、現場に即した様々なバリエーションの実に細かな指導になっていった。いつしか私は先生のことを「シショー」と呼ぶようになり、先生はそれに答えて、「オゥ、イタミ」と返してくれるようになった。 さて、その頃私はマトンゲ周辺から、師匠のいるゾーン・デ・キンシャサ、それにグラン・マルシェから都心方面ならば、一人でさっさと出かけることが出来るようになっていたが、マテテなどの周辺部は、ズジさんの家に行ったことがあるぐらいで、まだ不案内だった。そんなある日、都心のブティック街で、キンシャサのすべての通りを記入した実に詳細な地図帳を手に入れた。おかげで私は、ところ番地ひとつでザイール人も驚くほど的確に目的地へ着けるようになった。レペの初日はフィストンが迎えに来てくれたが、その地図帳を見て、彼も「もう案内はいらないな」と言ったほどである。主だった場所のすべてをマッピングして赤いマークをつけていたからである。これから行く場所も、タクシー・ビスの中で通りの名前と番地からおよその察しをつけていた。ただ、「この地図帳を持ち歩くのはやめた方がいい」と、乗客の一人から忠告された。何故かというと、ザイールは軍政で、その地図には軍事施設は載っていなかったものの、謎の空白域は見る人が見ればそれとわかるからである。とにかく、いちゃもんをつけられていらぬ面倒に巻き込まれないためにも、それはあまり見せびらかさない方がいいとその人に言われ、親身な忠告に感謝して車を降りた。似たようなことはほかにもあった。ものの本によると、キンシャサは世界で最も写真の撮りにくいところのひとつだそうだが、市内の至る所に軍事施設が散らばっていて、空港は勿論のこと、それらはすべて撮影厳禁だった。はっきりと標識が出ていればわかるが、行き届いていないところも多いので、街頭でカメラを持ち出すのは慎重を期する必要がある。このことも、タクシー・ビスにカメラをぶら下げて乗るという、今から考えると全く恐ろしいことをやったときに、親切な乗客にやんわりと諭されたのである。 ともかくマテテに着いて、かつて訪れたサロン・ルンバ・ライを通り過ぎ、その斜向かいにある、とある小さなバーに入って行った。そこが今日からのルンバ・ライのレペ場である。まだ昼過ぎなので、当然営業していなかったが、何人かのミュージシャン相手に食事が出されていた。そのときそこにいたのは、マライの渡欧中ルンバ・ライを守ってきた歌手のグロリアと、ミシャ、ファーレー、デスカ、バテクルという面々だった。いくつかの有名どころのグループを見てきた私の目には、彼等の第一印象は、正直言ってまるで子供だった。年齢的にはそうでもないはずなのだが、ミュージシャンが持つ特有のふてぶてしさに欠けていた。ストレートではあったが、どこか青臭かったのである。彼等はめいめい曲を持ってきていた。そしてレペは、その曲をひとつずつ歌うことから始まった。まずはグロリアの曲からだった。ここらにはコピー機など普及していなかったので、彼は歌詞を伝えるのに紙とペンでもって手書きしていた。さらに、他人のことは言えないが、驚いたことに彼等は楽譜の読み書きが出来なかった。しかしこれには親しみがわいた。曲を伝えるのに、彼等は全くの絶対音感をもって、ハーモニーを互いに思い浮かべながら、口移しでやっていたのである。ここまでは、わが「カーリー・ショッケール」の練習と大して変わらなかった。 彼等の曲は、歌パートだけで優に一〇分に達することが多く、その中にいくつものソロ・パートやサビが含まれているので、ひとつの曲の歌い込みが完成するまでには、相当な時間がかかる。今日のところはグロリアの曲の歌パートの全貌を一通りさらってみるところまで来て休憩に入った。そのあと、今度は遅れてやって来たディッキー・レ・ロワの曲にとりかかった。これも大体同じようなやり方で、暗くなりかけた頃には大まかにわかってきた。その頃にはミュージシャンも集まってきていたから、楽器の置いてある方でセッションが始まっていた。彼等は明らかに久しぶりに音を出す喜びと、新規に加入したメンバーとのコミュニケーションなどによる、わくわくした緊張感が見られた。そっちのほうが賑やかになってきたので、私は歌手たちの集まっているところから、ミュージシャンのいるところへと移った。 彼等の演奏は、ウォーミング・アップとはいえ、ダイナミクスが素晴らしく大きかった。走らせるところは、エンジン全開で突っ走るようだったし、押さえにかかるところはドラムでさえ撫でるようなタッチで音を抑制した。順繰りに各楽器がソロをとるお遊びも取り入れられていて、盛り上がりのあまり、離れたところで歌の打ち合わせをしていた歌手たちが、集まってきて即興で歌いはじめたほどだった。ここでまた驚かされたことに、何の打ち合わせもない即興演奏のはずなのに、歌手たちは、ある部分ではテーマとおぼしきコーラスをとり、ある部分では歌手が順繰りにソロをとっていく。演奏が即興ならば、歌詞の内容も即興である。誰かの悪口を歌ってみんなで大笑いすることもあった。その進め方には、何か一定のルールやマナーが、あたりまえのものとしてあるのではないかと思わせるほどだった。それに、おそらく我々一般的な日本人とは比べものにならないほど、彼等の頭には歌詞が詰まっているのだろう。泉のようにわき出る歌詞とギター・フレーズ、そしてソロをとりながら次の歌手に大きな身ぶりでタッチしたり、本来フィストンがリード・ギターで、ワジェリがアコンパニュマンと決められているはずなのに、お互いの立場を目で合図しあいながら取っ替え引っ替えしていく演奏の駆け引きを見ていると、今更のように音楽に参加する歓びを実感した。 そうした、タイトルのない即興演奏が一時間も続いた頃、リーダーであるマライがジョジョを連れて、自分で指定した時刻に大幅に遅れてやって来た。演奏が打ち切られ、全員が彼に握手し、飲み物が振る舞われ、新規のギタリストのジョジョが紹介された。もうすっかり暗くなっていたので、その日はマライの新曲の披露はなく、マライの古い曲の練習をすることになった。ビバですっかりお馴染みの曲や、ルンバ・ライ名義になってからシングル盤として発表された往年の名曲のかずかずを練習した。私も大喜びでロコレをたたいた。自分の演奏に確たる自信はなかったが、彼等は十分だと言った。その時は、まだ誰とも初対面同然だったので、それは日本人に気を遣ってお世辞で言ってくれているものとばかり思っていたが、後にエドゥシャやシモロと仲良くなるにつれ、それは本当のところだとわかって、自分の演奏に自信を持つようになった。
彼等二人はそれでも私に対して厳しい注文を付けた。ドラムは、演奏の中では骨格のようなものである。コンガの皮の音はそれに潤いを与え、ロコレの木の音は、時にはスピード感を、また時には堅すぎず柔らかすぎない深みをリズムに与えなくてはならない。特にコンガとロコレは、基本的に相反するリズム・パターンに従うべきで、それらは互いに隙間を補完しながら大きなリズムを作る。また、コンガが「ため気味」に演奏するのに対して、ロコレは「つっこみ気味」でたたくことが多かった。全体としてはテンポの緩い演奏でも、ロコレはその倍のリズムで刻むことが多い。しかし、逆にアップ・テンポの一六ビートのニュアンスによる演奏であっても、歌がその半分のニュアンスでゆったりと歌っている場合は、ロコレだけは決してつっこんではいけない・・・等々。そのような、微に入り細に入った指摘は、私にとっては本当にありがたいものだった。それを忠実に受け容れることによって、我々三人の友情は深まっていった。ギタリストからも細かい注文が出た。聞かせどころのフレーズの上に、私のロコレのパッサージュが被さってしまうことがあったからである。歌や演奏のメロディが四小節ずつの区切りの前に食い込む形で始まることの多いアフリカの音楽では、区切りのために四小節目の最後にパッサージュを入れる際には細心の注意を要する。そんなことに気がついたのは、このときからのことだった。スリットを境にした、たった二音だけの単純な楽器だが、それだけに音を出すタイミングとタッチの調整は、実に千差万別で難しいものだった。 とにかくそうして一日目のレペが終わり、私も彼等と一緒に、振る舞われた食事をほおばった。とても腹が減っていたので、「お前はやせているのによく食うなあ」と彼等に笑われたほどである。マライはその場で、「何とか二ヶ月後ぐらいにアルバムを発表したい」と言った。それでツアーをやってバンドを立て直そうという考えだった。そして私に向かって、「お前はいつまで滞在するんだ」と訊いた。私はビザの有効期限を伝えると、「それはちょっと足りないな」と言った。「わかった。俺が何とかするから、お前はレコーディングに参加しろ、みんなそれでいいか?。」こうして全会一致で私はルンバ・ライの正式にメンバーに迎えられることになった。この時ほど今回の滞在で嬉しかったことはない。 こうして、正式なルンバ・ライのメンバーとしてレコーディングに参加するという、明確な滞在目的が出来た私は、その後の一切の生活をこの目的のために絞り込んでいった。師匠の特訓や、古い時代のルンバ・ザイロワーズの名曲をラジオから録音することも欠かさず続けた。もちろん週末にはコンセールにも行ったが、翌日の特訓に備えて、明け方まで遊ぶようなことはしなかった。なんと言っても、音楽は聴くよりやる方が面白いに決まっているからである。師匠は、私がルンバ・ライの正式メンバーになったことを聞いて、今度はわがごとのように喜んだ。そして今までのように、週明けに寝不足の目で訪れることがなくなったのを見て、本気でいろんな表現方法の伝授にとりかかってくれた。テープが足りなかったので、私の持っているテープを渡し、師匠は知り合いからレコードを借りまくって教材を作った。そして様々なグループの様々な演奏を二人で聴いては、それにロコレを入れる場合、師匠ならこうする私はこうするという、実質的なディスカッションにかなりの時間を割いていった。しかし、完成された作品に、あとからどうロコレを入れるかと考えるのには限界があった。さらに古い曲になると、お互いの年齢の差から解釈に食い違いが生じることもたびたびだった。師匠は、「音楽はそうやって進化していくもんだ。」と言って、解釈の違いについては私の意見を尊重してくれたが、マナーを逸脱したリズム・アレンジについては鋭い指摘が飛んだ。そのうち、そうしたやり方がひととおり終わると、今度は、アレンジの途中にあるルンバ・ライの新曲に、私がどうロコレを入れていくかという実際的な指導をすべく、師匠は足繁くルンバ・ライのレペに顔を出すようになった。師匠はマライやムコカとはビバ時代からの旧知の仲だったので、彼等は喜んで師匠を受け容れた。そして彼は年長者の立場から、リズム・セクションのアレンジに意見を述べ、私に対してはその上に立ったフレージングや、リズムの変わり目を導くキメの作り方を指導し、エドゥシャやシモロに対しては、さらに突っ込んだ意見をするようになった。 毎朝決まった時刻に起き出して師匠のところへ出かけて行き、昼過ぎには必ず帰ってきて古いルンバのラジオ番組を愛聴し、またすぐにレペに出かける私を見て、ホテルの従業員や、周りの人々は何とも不思議な日本人だと思ったに違いない。明らかに周りの人の見る目が変わってきたのもその頃からだった。それまでは、私は表に出ると、通りのガキどもから「シノワ、シノワ」と声をかけられたものだった。それはつまり彼等には中国人と日本人の区別がつかないので、普段目にすることの多い中国人と思って、とりあえずそう声をかけるのである。中国人とはもちろん華僑のことだが、彼等はキンシャサにも確固とした社会を築いていて、都心から下町に至るまで、実に広い地下のネット・ワークを持っている。しかし、彼等は現地のザイール人たちと溶けあうことはなく、ザイール人たちにとっては、彼等は自分たちだけの社会に閉じこもる不可解な人種だと映っていたのである。だから、華僑の人たちに「シノワ」と声をかけても、たいてい無視されるのがわかっているから、特に子供たちは、なんの危険もない無邪気な遊びとして、そんなことをやるのだ。 シノワに次いで多いのが韓国、朝鮮の人たちである。ある日、ヴィクトワール広場を歩いていたら、ブティック街の入口で、銀色のBMWを洗っている、明らかに私と顔の種類のよく似た人に出会った。向こうも私に気がついて微笑みかけてきたのだが、お互い相手をどこの国の人と判断してよいのかわからなかったので、なかなか第一声を切り出せずにいた。私が英語で話しかけたのだがすぐに行き詰まり、向こうがフランス語でやり直したのに私が座礁してしまった。しかし、とりあえず私が日本人で、相手が韓国人だということだけはわかった。しかし、相手に日本語の通じるはずもなく、私はハングル語を知らなかったので、仕方なく私はリンガラ語で切り出してみた。すると通じたので、一台の高級車を間に挟んで遠い地球の裏側を故郷とする隣国の男どうしが、よりによってリンガラ語で盛り上がりはじめたのである。一部始終を見ていた周りのザイール人たちが呆気にとられたのも無理はない。どう見ても同じ顔をしているとしか思えない二人が、車を挟んで何か別の言葉でやり合うのならともかく、よりによってぎこちないリンガラ語で世間話を始めたからである。たちまちのうちに人垣が出来てしまった。 ちょうどその頃を境にして、マトンゲで私に「シノワ」と声をかける者はなくなった。しかし閉口したのは、今度は「ピリピリ」と声をかける奴等が激増したことである。その頃にはすでに私はピリピリの忠告のほとんどすべてが的外れだったことを思い知らされていたから、私ははっきり言って「ピリピリ」と呼ばれることが不愉快だった。ある日、アリに「ザイール人たちがピリピリと言うときに連想するイメージはどんなものなのか。」と訊いてみた。彼は、ほかのザイール人たちとは違って、我々と同じようにピリピリのことを彼の本名で呼んでいたのだが、彼は私の素朴な質問を聞くと、腹を抱えて笑い出した。 それは、ある事件に由来している。キンシャサに音楽を聴きに来た珍しい日本人ということで、彼はビバと一緒にテレビ出演したらしい。時はまさにビバの黄金時代、ルシアナ、ファタキ、リジョ、ファファという豪華な歌手陣に恵まれ、「クァッサ・クァッサ」というダンスが一世を風靡していた頃である。プロモーションでテレビ出演したビバの演奏に合わせて、なんとピリピリがステージで「クァッサ・クァッサ」を踊った。しかし悲しいことに、彼は一番盛り上がるジャンプの部分で、よりによってウェンバの前で派手に転倒したのである。助け起こしたウェンバに、「ピリピリ・ナ・クァッサ」と言われて、惚けたように笑ったその顔が、大写しになってザイール全土に放映され、翌日にはピリピリという日本人の名を知らないザイール人はどこを探してもいなくなってしまった。 それで日本人と見ると、何もわからずに彼等は「ピリピリ」と声をかけるのである。私は怒った。「冗談じゃない、そんなアホと一緒にせんといてくれ。」以来私は、「ピリピリ」と声をかけられると、「俺の名前はイタミだ、よく覚えておけ。」と大声でやり返すようにした。しかし、それを見てガキどもやおばはんは笑い転げ、おっさん連中は「やれやれまたか」といった顔をした。どれが功を奏したのかはわからないが、とにかく帰国する頃にはマトンゲを歩いていて「ピリピリ」と呼ばれることも、トラブルに巻き込まれることもなくなった。街を警備している兵士にいちゃもんをつけられるようなことがあっても、どこからともなく体の大きな若者がやって来て、「こいつは俺の連れだ、何か文句あんのか。」と彼らを追い散らしてくれたほどである。 これはアリも認めていたことだが、私は実に微妙なバランスのなかで身を守られていた。つまり私は、物見遊山に来たツーリストではなく、この国の音楽を本気で身につけようとしている。彼等と同じ言葉を話し、彼等と同じ飯を食い、今ではルンバ・ライの正式なメンバーだ。それをみんなが知っているのである。そういうことが、彼等のプライドに微妙に訴えかけている。事実、ザイール河を下って来たというバック・パッカーたちが、身ぐるみはがされているのを街で何度も見かけたが、彼等は一様に自分たちの冒険のためにここを訪れていて、キンシャサをあくまでも物資の補給基地としてしか見ていなかった。だから決してリンガラ語を覚えようとはせず、ザイールの食事を口にせずパンだけで暮らしてきた。ものを買うときも値切り方を知らず、しきたりを覚えず、第一いでたちが汚い。この汚い格好というものを、ザイール人たちは最も嫌う。これはしばらくここで生活してみてしみじみとわかったことだが、彼等は実にプライドが高く、実にきれい好きなのである。確かに服は粗末で、水道の水にはわずかに色が付いているから、白いものも純白ではない。しかし、汚れたものは決して着ていない。シャワーも実にまめに浴びるし、ひげやつめや髪の毛の手入れなどにも気を遣い、多くのバック・パッカーたちのように無精ひげを伸ばし、手ぬぐいをぶら下げ、なりふり構わぬようないでたちでは絶対に街を歩かない。 「それなのにあの汚いバック・パッカーたちは、このくらい汚くてもお前らには適当だとでも言わんばかりに、当然のような顔をして我々に話しかけてくる。」と、彼等は怒る。都心の表通りならいざ知らず、マトンゲの裏通りをそんな格好で闊歩しようものなら、全くのいいカモである。ここらにいる連中は、そんな旅行者が死ぬほど嫌いなのだ。「そんなもん、いてもたらええんや。」今から考えると実にひやひやものだが、私は毎日のようにそんな街をうろつき、道ばたの兄ちゃんとビールを飲み、葉っぱの売人と世間話をし、界隈を仕切っている親分のところで闇両替をしていたのである。冷静に考えてみると、確かに危ない橋を渡っていたことになる。というのは、いかに分け隔てなく人と付き合うようにしていたとはいっても、おのずから限界があったし、私に取り入ろうとしてうまく行かなかった者のなかには、逆恨みをする者が出てきても不思議ではなかったからである。そこまで思い至って、やっと私は自分の振舞いに注意を払うようになった。 ある日のことである。朝早くからズジさんがやかましくドアをたたくので、何事かと思って出てみると、「今日は絶対に外出してはならん。」と言う。「どうしたのか。」と訊くと、「今日はサッカーの試合があるからだ。」と言う。ますますわからなくなって怪訝な顔をしていると、ズジさんはいつになくいらいらして、「とにかく出るな。サッカーの日はな、暴徒と化した群衆がここらを荒し回るから、今ホテルも戸締まりをしとるところだ。」と言う。ホテルの窓からは、ヴィクトワール通り越しにスタジアムが見えていた。そこが会場なのである。そこは、かつてモハメド・アリとジョージ・フォアマンが、世界ヘビー級タイトルマッチを競った際に、それを記念して一大ブラック・ミュージック・フェスティバルが開かれたところである。その時キンシャサを訪れたファニア・オール・スターズの歌手が、熱狂する聴衆に向かって、「ケ、ビバ・ラ・ムジーカ」と叫んだことが、若きウェンバにバンド名を決心させるきっかけを作ったという逸話がある。後に日本でも発売されたその時のファニア・オール・スターズのライブ・ビデオには、このスタジアムの準備風景などが写っていて、キンシャサの雰囲気がよく現われていたものだった。「それならば一度行ってみたい。」と私は言ったが、ズジさんは真顔で、「お前はキンシャサを知らんのだ。このホテルから日本人の死者を出すわけにはいかん。出るなと言ったら出るな。」と言って、すたすたと行ってしまった。「何を大げさな」と思ったが、忙しく戸締まりに精を出すホテルの従業員と、「行くのならば俺の屍を越えて行け。」とでも言わんばかりのズジさんの後ろ姿を見て、「わかったよ、今日は一日ラジオでも聴いて過ごすことにしますですよ。」と独り言を言って引き下がった。 その日もレペがあったので、朝早くからフィストンが曲の打ち合わせにやって来た。玄関に堅く鍵がしまっているので、彼は、いつもやるように道路から口笛で私に合図した。ズジさんの気を悪くしてもまずいので、下に降りて格子越しに「かくかくしかじかで」と、ことの次第を説明した。そこへズジさんも出てきて、フィストンと少し問答になったが、「とにかくレペには行けないから、みんなによろしく伝えてくれ。」と頼むと彼はぶらぶらと去っていった。程なくして、いつもの時間に来ない私を心配して、イチャーリ先生が遣いをよこしてきた。私はその子供に小遣いを渡し、「かくかくしかじかでここから出してもらえないのだ」一時間ほどしてその子がまた戻ってきて言うには、師匠は「それならば今日の何時何分に始まる何々というFM番組を必ず聴いて、そこで取り上げられる新曲のパーカッション・アレンジを明日までに考えてくるように」と伝えてきた。なんと、宿題が出たのである。とにかくそういうわけで、その日はバーからビールを取り寄せて、一日中ラジオを聴くことにした。ホテルに缶詰にされたのは、むろん私だけではなかった。従業員以下、すべての宿泊客が、その日は何もできずに暇を持て余した。 ホテル・ディアカンダは客筋のよいホテルだった。泊まっていたのは、たいてい商用でキンシャサを訪れていた、ザイールの地方都市や近隣の国々のビジネス・マンだった。最上階には、なんとホテル暮らしをしている金持ちの小説家までが住んでいた。私はかねてから一度その人と話してみたいものだ思っていたのだが、従業員たちは彼を不可思議だと言うばかりで、評判は今一つだった。今日は千載一遇のチャンスである。しかし生憎その日は彼は不在だった。仕方なく部屋に戻って、ラジオを聴きはじめると、することのない宿泊客やホテルの従業員たちが、珍しい日本人と話してみようとして、暇つぶしに私の部屋にやってきた。部屋にやってきた人たちは多彩だった。カサイ州からダイヤモンドの原石を売り込みに来た商人、その南のシャバ州から金を売りに来た商人、何の商売かはついに明かさなかったが、何かの用事で来ていたナイジェリア人、さらにビンザというキンシャサの高級住宅街に実家のある金持ちのぼんぼん、そしてズジさんと、ホテル専属のコック、それに少し遅れてホテルのオーナーが顔を出した。 このひとときは楽しかった。全員に通じる言葉がなかったからである。カサイの人はチルバ語とフランス語しかわからなかったし、シャバの人はテテラ語とズールー語とフランス語、ナイジェリア人はヨルバ語と英語、などという具合だった。リンガラ語はザイールの共通語じゃなかったのか、という素朴な疑問がわいたが、彼等の話によると、リンガラ語がまともに通じるのは、キンシャサと、それより西のバ・ザイール州、東のバンドゥンドゥ州、ザイール河中流のエクァテール州ぐらいまでだということだった。今あげた地域は、古くから通商のためにリンガラ語が普及した大きな河の流域なので、そこの住民もリンガラ語に古くから親しんでいるが、ほかの地域では、それに代わる別の言葉があり、自分たちの部族語やその部族を支配したもっと大きな部族の言葉、さらに国の公用語としてのフランス語などもあるので、特にリンガラ語が必要なわけではないということだった。例えばズジさんはキンシャサ育ちだが、彼でさえ、リンガラ語とフランス語、そして故郷バ・ザイールのコンゴ語や、国境をはさんですぐ南側のアンゴラで使われているポルトガル語は話せるが、カサイ州のチルバ語はさっぱり、という具合だった。大体キンシャサそのものが、部族の分布としてはコンゴ語の地域だった。さらに地方へ行けば行くほど部族の結束も強いから、小さな部族語も残っていて、そこらの人はたいてい五つは異なる言葉を喋れるらしい。びっくりした。日本語にかたことの英語と、聞きかじりのリンガラ語ぐらいでは話にならない。それを聞いていたナイジェリア人もすごかった。彼はラゴスのかなり北のある部族の出身なのだが、その部族語と、そこを支配したさらに大きな部族の言葉と、ナイジェリアの国語であるヨルバ語と英語、さらにカメルーンに商売に行くことが多いのでそこの言葉と、かたことのフランス語が出来た。大変なもんだった。それだけの学識豊かな人々をもってしても、全員が理解しうるひとつの言語がなかった。いや失礼、正確にいえば、私がフランス語を解さなかっただけのことなのだが。 こうして私の部屋に数え切れない言語が乱れ飛び、この日は言葉遊びの平和なゲームで盛り上がることになる。その間、ラジオはつけっぱなしだったので、時々かかる曲やミュージシャンの話題にもなった。集まっている人がみんな年配の人であるせいか、話題に上るのは、往年のスターたちのことや、古いいくつかのグループの離合集散にまつわるエピソードだった。キンシャサでは、ザイールの放送のほか隣国コンゴの放送も聴くことが出来たので、コンゴの音楽シーンのことや、アフリカのほかの国々のことにまで話題は広がっていった。中でもセネガルとナイジェリアの話題が多く、ラジオでも結構かかっていた。おそらくアフリカ全土でいえることだと思うのだが、彼等は今も古い部族社会のシステムをそのまま捨てずに守って生きているから、音楽の世界でもあるグループのトップに位置する人が、そのグループの興行収入を独占し、それに飽きたらない下っ端のミュージシャンがクーデターを起こして仲間を引き抜いて別のグループを作る。しかし、そこでもクーデターを起こした本人が、同じように利益を独占するものだから、またクーデターに見舞われる。健康なのか不健康なのか、芸術的価値から言ってどちらが正しいのか細かいことはわからないが、とにかくそうして新陳代謝が起こって、シーンはよくも悪くも活性化していく、というのが現実のようである。そうした現実について何も知らない私に、彼等はそれぞれの言葉でかんで含めるように教え諭してくれた。 さて、ラジオは私がいつも愛聴ている「タンゴ・ヤ・カラ」という番組になった。そのテーマ・ソングがかかったとき、「これが好きやねん。」と声を大にして言った私に、そこにいたおじさん連中は、「そうか、これが好きか。」と、全員身を乗り出してきた。アフロ・キューバンの大旋風が吹き荒れた時代の音楽を中心に紹介するその番組の内容には、カサイもシャバもナイジェリアもなかったからである。おそらく独立の歓びにわき返ったアフリカのほとんどの国々でその手の音楽は大流行したので、どこの国の人にとっても、その手の音楽は一種のナツメロみたいなもんだったのであろう。スペイン語で歌われることの多かったそんな曲でさえ、彼等はその歌の内容をよく知っていて、そんな古いものが好きだと言った私にわかりやすく説明してくれた。続いて師匠が指定した宿題の番組となった。私が宿題を課せられていると言うと、「おおそうかそうか」とまたおじさん連中は身を乗り出してきて、「ここはな、こういうリズムで演奏されとってな、それには実はこういう意味があって・・・」、「いやいや、ここはチルバで歌われているんだから本来使うべき楽器は・・・」、などと部屋の中で侃々諤々の論争になってしまい、結局私は何をどうすればいいのやらさっぱりわからないほどに混乱してしまった。 そのうち、スタジアムでサッカーの試合が始まったということなので、彼等はテレビのある最上階のオーナーの部屋へ中継を見るために移ることになった。「お前も来るか。」と誘われたが、何だかひさびさにのんびりしたい気分だったので、丁重に断わって一人残ることにした。結局その日は、心配された暴動も掠奪もなく平穏無事に一日が過ぎていった。しかし、スタジアムから響きわたる歓声がホテルの部屋にまで届き、試合終了と同時にそのどよめきはただならぬものとなったあと、程なくしてホテルの前の通りを全力で駆け抜ける大勢の血気盛んな若者や、その群衆の中を速度も落とさずに疾走する車などで、一時あたりは騒然となった。表通りからも鋭い笛の音や叫び声が聞こえ、ホテルにも緊張が走った。窓から一部始終を見ていた私に、通りにいた中年の男が、危ないから顔を出すなと身ぶりで教えてくれたほどである。後にも先にも、キンシャサでこういう緊張に直面したことはこれっきりだった。ここは、普段はとっても平和な町で、観光ガイドなどに書かれているように、世界で一番危険な都市のひとつなどというのはとんでもない話だった。 さて、次の日私は宿題が出来ていなかったので、重い足取りで師匠の家に向かった。「どうだ、考えてきたか。」とカセットを用意しながら機嫌良く訊いた師匠に、「いやあ、あの、その、実はかくかくしかじかで、カサイの人やナイジェリア人たちが、自分の国のリズムはああだこうだとまくしたてるので・・・」、と言い訳じみたことをぼそぼそと言いはじめた私を、師匠は烈火のごとく怒鳴りつけた。「そんなことは訊いとらん、お前がどうアレンジしたいのかと訊いとるんだ、お前はミュージシャンなんだぞ、そんなもんひとつ考えつかんでどうするんだ、このばかたれが。」平謝りに謝るしかなかった。「罰として今日の昼飯は抜きだ、お前はわしが食っているのを、横でじっと見ておるがよい。」「そんなあ・・・。」結局その日の昼飯は、私が師匠の分をおごって、私は何も頼まずに、じっと師匠が食事を終えるのを傍で見ている羽目になった。メシ屋のおばちゃんはずっと怪訝な顔をしていたが、私は腹の調子が悪いんだと言ってその場を濁した。 三月も半ば近くになると、ルンバ・ライのレペでは録音する新曲が出揃ってきた。リーダーであるマライは、「ミランダ」と「ザコ・マトゥバンガ」という二曲、グロリアは「オークノム・ネ・ボー」、ディッキー・レ・ロワは「カランダ」(これはレコーディングの際「ジャキド」と改題された)、バテクルは「べべ・カムンドゥングレ」、更にコンセールのイントロなどで使われるダンス・パフォーマンス用の曲「ンガフーラ」の、以上六曲である。三月の初めにレペが開始された当初は、曲自体がラフな状態だったので、歌手だけが集まって歌を練る時間が多かった。しかし、三月も半ばを過ぎる頃になると、歌の構成やアレンジが固まってきたので、それにつれて歌パートの演奏のアレンジも決まりはじめ、ミュージシャンが揃い次第バンド入りで新曲を練習する機会が多くなった。更に、ダンス・パート(セベン)の展開が決まりはじめ、新しいダンス「ンドゥェケレ」のかけ声(アニマシオン)の付け方が決まり、ようやく全体が曲らしい体裁を整えるようになってきた。 初めの頃のレペでは、私はアカペラで歌われる肉声の絡み合いのなかに強烈なリズムを見いだしていたのだが、それに慣れるにつれて、歌そのものが要求してくるリズムを感じとれるようになった。その頃は、昼間のレペの前半の時間は新曲の練り上げにあてられていたので、彼等の歌をじっと聴き、歌の中でどういうパーカッションを入れるのかをずっと考えていた。そんな毎日は、今回の滞在の中でもっとも創造的な時間だった。それに対して後半は、来たるべきコンセールに備えた旧曲の練習だったので、私にとっては、配られたテープを聴き、前任者がどういう演奏をしていたのか、またそれは何故なのかと、ドラムやコンガとのコンビネーションを考えながらロコレをたたくという鍛錬の時間だった。 エドゥシャやシモロと非常に仲良くなったのはこの頃のことである。そして、その後新曲も徐々にバンド入りで練習されはじめるようになると、彼等もドラムやコンガで実際に歌の中に入ってきたので、今まで頭の中だけで暖めてきたことを、実地に演奏するようになった。もちろん解釈の食い違いからリズムがぶつかり合ってしまうこともあったが、彼等はすぐさまその食い違いを指摘してくれた。さらに、地面をのたうつようなベースや、細かいアフター・ビートで腰を突き上げてくるようなリズム・ギター(アコンパ)も、実際に合わせてみるまでは、どういう風に演奏してくるのかわからなかったので、初めのうちは、なかなか演奏全体がしっくりしなかった。 もちろんそれはひとり私だけが原因なのではなく、彼等といえども、めいめいがめいめいの解釈でプレイしているから、ギタリスト同士でぶつかったり、ベースとドラムがカー・チェイスを繰り広げることもしばしばだった。そんなときには演奏がよく止まって言い合いになった。そのたびに彼等は、ギターやベースを首からぶら下げたまま、大きな身ぶり手振りで、口でメロディやリズムを口ずさみながらああ弾けこう弾けと互いに要求し合ったものである。我の強いミュージシャンと調和を大切にする人との間で微妙な駆け引きが始まり、たいていは声の大きな方が勝利を収めて、その場のアレンジが決められていった。しかし、争いはアレンジに関する議論ばかりとは限らなかった。いかにザイール人といえども、リズム感の悪い奴や、音感の悪い奴がいるのである。どこにでもよくある簡単なパッサージュなのに、どうしても弾けない奴がいたり、ここ一番決めなければならないコーラスを、何度やってもはずしてしまう奴がいた。むろんそんなときにはたちどころに演奏が止まり、いつ果てるともない言い争いになるのだが、「俺のリズムが乱れるのは、ドラムのフレーズがあそこで必ず乱れるからだ。」とか、「コーラスが狂うのはギターのチューニングがなってないからだ。」とか、そんな子供みたいな責任の擦り合いに何十分も時間を割いてしまうのである。 エドゥシャやシモロは、たいていそんな争いをじっと冷ややかな目で見ていたが、彼等はメンバーの中では年少者だったので、たいてい引き下がる分際だった。しかし彼等も黙って引き下がっていたわけではない。一応言われたとおりのフレーズを弾きつつも、そのなかに自分の考えていたニュアンスを残し、日に日にその色合いを強めていったからである。彼等はよく目で合図をしながら、二人で、時によっては私を含めた三人で取り決めたアレンジをゲリラ的に実践した。しかし、それらは巧みにオブラートにくるまれていたので、文句を付けた声の大きな人に気づかれることはなく、むしろかえって彼の方が我々のリズム・アレンジにつられて演奏のフレーズを変えてきたほどだった。そんなときには、よく三人にしかわからない符丁で、互いにガッツ・ポーズを交わしたりしたものである。しかし時によっては、争いが大喧嘩に発展してしまうこともあった。そんなときはたいてい作曲者が中に割って入るのだが、どうしても収拾がつかずに、全員がかんかんに怒って帰ってしまうこともあった。全く、そんなところは、本当に日本のがきんちょのロック・バンドとなんら変わるところがなかった。やれやれ一体どうなることやら・・・。 それでも、なるようになるものだ。三月も末になると、まるで波に乗るサーファーのように、私はロコレをたたくのが楽になった。全体の演奏がこなれてきて、何と言うわけではないが、音楽の全体が、私にこうたたけと指示でもしているかのように、また、その指示を自分の手が、まるで分かり切ったことででもあるかのように、自然に求められるフレーズをたたき出せるようになったのである。私はただそこにいて、ロコレの前に立ちさえすればよかった。あとはオートマチックに、音楽が全てを決めたのである。この感覚は、今でも忘れられない。  私はコンセールを見に行くのも大変好きだったが、そんな店に、客のまばらな平日の夕方、ぶらっとビールを飲みに行くのがまた好きだった。お気に入りの店は、ショック・スターズが本拠地にしていたマディゾンで、そのだだっ広い青天井の下で割れかけたスピーカーから流される往年のルンバを聞きながら、暮れなずむ夕陽の向こうに列をなして飛んでいく渡り鳥を眺めて飲むビールはまた格別だった。しかし何より贅沢なのは、わざわざ出かけて行かずして、ディアカンダのベランダに椅子を持ち出してふんぞり返ってビールを飲みながら、風に乗ってやって来るコンセールの音を聞くことである。風向きによって、ヴェヴェのヴィクトリアの重いグルーヴや、キンプァンザのアンチ・ショックのボジの甲高い声や、すぐ近くのマディゾンでやっているショック・スターズの甘いラブソングを、居ながらにして聞くことができるからである。この楽しみ方を私は結構気に入っていた。しかし、下の道を歩く顔見知りからは、「どうした、今日はコンセールには行かんのか。」と冷やかされ、そのたびに、「オレは日本人だからわざわざ出かけて行ったりはせんのだ。ここにいればちゃんと奴等の方から音を運んできてくれる。」と答えてやった。するとたいていの人は肩をすくめて、「結構なご身分だな」というようなことを言って、夜の商売に戻って行ったが、実際これは結構なご身分だった。こうしているとズジさんも安心らしくて、頼みもしないのにビールを何本も持ってきて、仕事を放ったらかしてともに飲んだりした。
私はコンセールを見に行くのも大変好きだったが、そんな店に、客のまばらな平日の夕方、ぶらっとビールを飲みに行くのがまた好きだった。お気に入りの店は、ショック・スターズが本拠地にしていたマディゾンで、そのだだっ広い青天井の下で割れかけたスピーカーから流される往年のルンバを聞きながら、暮れなずむ夕陽の向こうに列をなして飛んでいく渡り鳥を眺めて飲むビールはまた格別だった。しかし何より贅沢なのは、わざわざ出かけて行かずして、ディアカンダのベランダに椅子を持ち出してふんぞり返ってビールを飲みながら、風に乗ってやって来るコンセールの音を聞くことである。風向きによって、ヴェヴェのヴィクトリアの重いグルーヴや、キンプァンザのアンチ・ショックのボジの甲高い声や、すぐ近くのマディゾンでやっているショック・スターズの甘いラブソングを、居ながらにして聞くことができるからである。この楽しみ方を私は結構気に入っていた。しかし、下の道を歩く顔見知りからは、「どうした、今日はコンセールには行かんのか。」と冷やかされ、そのたびに、「オレは日本人だからわざわざ出かけて行ったりはせんのだ。ここにいればちゃんと奴等の方から音を運んできてくれる。」と答えてやった。するとたいていの人は肩をすくめて、「結構なご身分だな」というようなことを言って、夜の商売に戻って行ったが、実際これは結構なご身分だった。こうしているとズジさんも安心らしくて、頼みもしないのにビールを何本も持ってきて、仕事を放ったらかしてともに飲んだりした。 さて、カサイの人がいなくなった頃、フィストンがルンバ・ライのレペの場所と時間を伝えてきた。いよいよ本格的に始まるらしい。レペは、なんと毎日午後一時からやるとのことだったので、私はその日のイチャーリ先生のレッスンの際に、いきさつを伝えて時間を繰り上げてもらうことにした。「毎日やるだと、あいつらにそんな根性があるもんか。」先生は私の喜びとは裏腹に懐疑的だった。とにかく、次の日から、朝起きたらまずイチャーリ先生のレッスン、帰って昼を食ってラジオを聴いてからマテテ地区にあるルンバ・ライのレペ場へ行き、そこで暗くなるまで練習したあと、ミュージシャンたちに賄いで出される飯を食い、なんとトランスポールまで貰って帰ってくるというのが日課になった。平日ならば、それからアリなどと飲み歩くこともあり、週末や日曜日には夜徹しのコンセールに行った。そのため、寝ぼけ眼で受ける月曜日のレッスンで、先生に大目玉を喰らうのが習わしとなってしまった。
さて、カサイの人がいなくなった頃、フィストンがルンバ・ライのレペの場所と時間を伝えてきた。いよいよ本格的に始まるらしい。レペは、なんと毎日午後一時からやるとのことだったので、私はその日のイチャーリ先生のレッスンの際に、いきさつを伝えて時間を繰り上げてもらうことにした。「毎日やるだと、あいつらにそんな根性があるもんか。」先生は私の喜びとは裏腹に懐疑的だった。とにかく、次の日から、朝起きたらまずイチャーリ先生のレッスン、帰って昼を食ってラジオを聴いてからマテテ地区にあるルンバ・ライのレペ場へ行き、そこで暗くなるまで練習したあと、ミュージシャンたちに賄いで出される飯を食い、なんとトランスポールまで貰って帰ってくるというのが日課になった。平日ならば、それからアリなどと飲み歩くこともあり、週末や日曜日には夜徹しのコンセールに行った。そのため、寝ぼけ眼で受ける月曜日のレッスンで、先生に大目玉を喰らうのが習わしとなってしまった。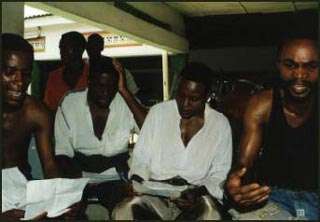 こうしていくつもの黒い頭を付き合わせて、しゃがみ込んだ状態で最も単純な作業からレペが始まった。一時間もすると、グロリアの持ってきた曲の主要な部分の歌い込みが板に付いてきた。ここで驚かされたのは、彼等の歌うセンスだった。特に役割分担を決めたわけでもないのに、めいめいが自分の得意とする音域で、思い思いにその場でメロディを作っていった。もちろん主旋律はあるのだが、それに対してどうハモるかということまでは一切決められていなかった。それらは、歌手自身の歌唱力と好みにまかされていたのである。そしてラフな状態のまま歌い込みが進み、作曲者であるグロリアによるいくつかの手直しのあと、部分ごとに歌い回しが決められていった。さらに驚かされたのは、彼等は伴奏もなく肉声で歌っているだけなのに、その微妙なハーモニーが、強烈なリズムのうねりをつむぎ出していたのである。歌を聴いているだけで、それがどんなリズムを要求しているのか、手に取るようにわかるほどだった。メロディ、ハーモニー、リズムなどという、三つの要素をよく考えて音楽にとりかかるという教育を受けた私には、これは大きな発見だった。
こうしていくつもの黒い頭を付き合わせて、しゃがみ込んだ状態で最も単純な作業からレペが始まった。一時間もすると、グロリアの持ってきた曲の主要な部分の歌い込みが板に付いてきた。ここで驚かされたのは、彼等の歌うセンスだった。特に役割分担を決めたわけでもないのに、めいめいが自分の得意とする音域で、思い思いにその場でメロディを作っていった。もちろん主旋律はあるのだが、それに対してどうハモるかということまでは一切決められていなかった。それらは、歌手自身の歌唱力と好みにまかされていたのである。そしてラフな状態のまま歌い込みが進み、作曲者であるグロリアによるいくつかの手直しのあと、部分ごとに歌い回しが決められていった。さらに驚かされたのは、彼等は伴奏もなく肉声で歌っているだけなのに、その微妙なハーモニーが、強烈なリズムのうねりをつむぎ出していたのである。歌を聴いているだけで、それがどんなリズムを要求しているのか、手に取るようにわかるほどだった。メロディ、ハーモニー、リズムなどという、三つの要素をよく考えて音楽にとりかかるという教育を受けた私には、これは大きな発見だった。 そこには、かつてビバの第一回来日で日本で会ったゴーチェ・ムコカがいた。その後長いつきあいとなるドラムのエドゥシャやコンガのシモロがいた。いつもひょうきんなギターのワジェリもいた。彼等は適当にコードを決めて即興演奏でウォーミング・アップをしていた。傍らにロコレが置いてあったので、すぐさま私も演奏に加わった。ルンバ・ライのロコレの奏者としては、かつてイェンゴという人がいたのだが、色々あって彼はもう来なくなっていた。しかし、その後彼に会う機会があり、何度か彼の家を訪れたこともある。
そこには、かつてビバの第一回来日で日本で会ったゴーチェ・ムコカがいた。その後長いつきあいとなるドラムのエドゥシャやコンガのシモロがいた。いつもひょうきんなギターのワジェリもいた。彼等は適当にコードを決めて即興演奏でウォーミング・アップをしていた。傍らにロコレが置いてあったので、すぐさま私も演奏に加わった。ルンバ・ライのロコレの奏者としては、かつてイェンゴという人がいたのだが、色々あって彼はもう来なくなっていた。しかし、その後彼に会う機会があり、何度か彼の家を訪れたこともある。