私が二度目の旅行から帰国してからの三年ほどは、おそらくカーリー・ショッケールの絶頂期だったといってよい。かつてのクラブ・ダイナマイトのプロデューサーをはじめ、多くの業界関係者とコネが出来たのもこの頃だった。われわれは精力的にライブ活動をした。おかげで沢山のバンドやミュージシャンと友達になり、自主的なイベントを数多く打ったりもした。またこの頃は、まだバブルの名残が色濃く残っていて、いわゆるエスニックな音楽のムーブメントに注目する業界関係者も多かったし、企業が文化活動の名目で、そうした方面に金を使うことも多かった。パパ・ウェンバのインターナショナル・バンドが二度目の来日を果たし、ヴィクトリア・エレイソンが初来日したのもこの頃である。われわれはそれらにも出演した。そうして演奏は目に見えて上達していった。しかしそれは、あくまで以前と比べればの話で、プロ並みの腕前に上達したということではない。われわれはそれを痛いほど自覚していた。しかし露出効果が高まるにつれ、その自覚とは裏腹に、様々な人脈からプロ・デビューの誘いやレコーディングの話が舞い込んだ。
私はマネージャーとしての立場から、そうしたチャンスはすべてものにするべきだと考えていた。少々歌や演奏にまずいところがあっても、一般の人はそこまで聴いていない。要は、こんなことをやっている奴等がいるということを示すのは無駄なことではなかろうし、プロ意識を持つということも、レコーディングという作業をするということも、自分たちの音に、もっと立ち向かういいチャンスだと考えていたのである。しかし、メンバーの意見は、話があるたびに何度も対立した。私はメンバーを代表して、せっかく話を持ってきてくれた相手との折衝に気を遣っていたが、図らずも結論をずるずると先送りすることになり、彼等に対して不義理を重ねたあげく、結局どのチャンスもものにすることが出来なかった。われわれは結成した頃にはまりこんだ泥沼からはどうにか這い出ることが出来たが、そよ風の吹く見晴らしのよい晴れた野原にはまだほど遠く、依然として太陽の光のあまり届かない鬱蒼とした熱帯雨林のジャングルの湿地を、ありのようにうごめいていた。
そんなある日、いつまでたってもうだつの上がらないバンドの現状に嫌気がさして、ギターの大西先生がバンドを辞めると言いだした。彼が辞めるということは、黄金時代のビバからボンゴ・ウェンデが抜けるのと同じくらいの痛手だった。大西先生は、ギターを持てばフレーズが泉のように湧き出る天才的ギタリストである。その才能と技術は、ボンゴ・ウェンデを驚愕させたばかりか、ザイールきっての指の魔術師、あのペペ・マヌワクをして、「こいつのギターには心がある。」と言わしめたほどである。彼の音は、全くわれわれの音楽的特性の要だったと言っても過言ではない。それまでの我々の演奏は、彼のギター・フレーズやアレンジに依存しすぎている面があった。彼が辞めたことによって、われわれはアレンジというものについて真剣に考えざるを得なくなった。
いままでの音は、いわゆるギター・バンドののりで、バックの演奏はギター・フレーズを中心に構築されていたから、フレーズが変われば演奏も変わってしまうという性質を持っていた。あながちそれが欠点だとはいえないが、少なくともわれわれが、ギターのキャラクターにおんぶに抱っこの状態だったことは否めない。彼が辞めたために、われわれは寄り掛かる柱をなくし、仕方なく自分たちで立つ練習をしなければならなくなった。クマちゃんがキーボードでリードのメロディを弾き、アニキがギターでリズムを支えた。時にはその役割を入れ換えてみたり、ドラムやベースというリズム・セクションの絡み具合も作りなおさなければならなくなった。そればかりではなく、かつてはギターの音色にかき消されて聞こえなかったボーカルの歌い回しの細かい処理のずさんさなどが明るみに出た。それらを手直ししようとすると、歌い方全体を変えざるを得なくなり、果ては曲の構成そのものを見直さざるを得なくなった。
われわれは、骨組みのやり換えにまで及ぶこの大改造のため、一年近くライブ活動を中止した。そして再び客の前に立てるようになった頃には、とっくに日本の景気は冷え切っていて、いくらDMを打っても、もはやわれわれを見に来る業界関係者などひとりもいなくなっていた。こうしてわれわれが得たものは、アレンジと構成によって曲を聴かせるやり方を覚えたことである。しかし同時にわれわれが失なったのは、偶発的な即興演奏によってしか得られない、あの怒涛のような音の奔流だった。大西先生が辞めたのと相前後して、歌手の何人かもやめていった。われわれの音は、必然的にこじんまりとまとまらざるを得なくなってしまった。
「ヌーベル・ジェネラシォン」
 大西先生が辞める直前、パリで「ヌーベル・ジェネラシォン」というグループが結成された。これはかつての第二期ビバ・ラ・ムジカの歌手だったリジョ・クウェンパ、ファファ・デ・モロカイ、ルシアナ、ファタキを中心に、ギターのボンゴ・ウェンデ、ドラムのアウィロ・ロンゴンバなどが、ウェンバに反旗を翻す形でビバを脱退して結成されたものである。パパ・ウェンバはかつて七〇年代後半には確かに若者の代弁者であったし、若い音楽の改革の闘士であったことは事実である。それを彼は自らの甲高い声とロック魂で実現してきた。しかしそれから十五年が過ぎ、彼の威光も自分で築き上げた古くさい権威主義の煤けた霞の中で、その輝きを鈍らせつつあった。それに反発する者が出てくるのは当然である。彼等にとってウェンバは、もはや自分たちの音楽の代弁者ではなく、単なる気むずかしい親分だった。しかも怒らせるとただでは済まない厄介な独裁者だった。彼等は長い間親分の顔色をうかがいながら歌い、演奏することを余儀なくされてきた。第二期ビバの結成からほぼ一〇年目にして、彼等の忍耐は限界に来てしまったのである。
大西先生が辞める直前、パリで「ヌーベル・ジェネラシォン」というグループが結成された。これはかつての第二期ビバ・ラ・ムジカの歌手だったリジョ・クウェンパ、ファファ・デ・モロカイ、ルシアナ、ファタキを中心に、ギターのボンゴ・ウェンデ、ドラムのアウィロ・ロンゴンバなどが、ウェンバに反旗を翻す形でビバを脱退して結成されたものである。パパ・ウェンバはかつて七〇年代後半には確かに若者の代弁者であったし、若い音楽の改革の闘士であったことは事実である。それを彼は自らの甲高い声とロック魂で実現してきた。しかしそれから十五年が過ぎ、彼の威光も自分で築き上げた古くさい権威主義の煤けた霞の中で、その輝きを鈍らせつつあった。それに反発する者が出てくるのは当然である。彼等にとってウェンバは、もはや自分たちの音楽の代弁者ではなく、単なる気むずかしい親分だった。しかも怒らせるとただでは済まない厄介な独裁者だった。彼等は長い間親分の顔色をうかがいながら歌い、演奏することを余儀なくされてきた。第二期ビバの結成からほぼ一〇年目にして、彼等の忍耐は限界に来てしまったのである。
彼等は水面下でクーデターの準備をした。密かにパトロンを捜し集め、賛同者を募っていった。そして九二年のある日、ウェンバに対する忠誠の誓いを踏みにじって彼等は離反した。ウェンバは彼等に対してはっきりと破門状を突きつけ、彼等は喜んでそれにサインして去った。程なく彼等のファースト・アルバムがリリースされ、われわれはそれを聴いて、そこに再びあのゾクゾクするような怒涛のルンバの奔流をみた。翌年、私とトミヨリ氏と大西先生は、三人でその「ヌーベル」を観るためにパリへ行った。
われわれはロワッシーからRERで市内に出ると、メトロを乗り継いであの懐かしい煤けたクリシー広場へ出た。そのまま荷物を引きずって、まるでわが町のようにホテル・サボイまで行き着くと、自分の家に帰るかのようにそこへ入って行った。受付のアラブ人の兄ちゃんはわれわれをよく覚えていて、私には例の屋根裏部屋の鍵を、ふたりには通りに面した最も広い部屋の鍵をニタニタ笑いながら渡した。今回はみんな仕事を休んで来ているので、わずか一週間足らずの滞在だった。
われわれは即行動を開始した。ここへ来る前に、リジョと手紙のやりとりをしていて、ヌーベルのコンセールを今回の滞在の最終日になるように、日程を設定していた。それまでの間に、彼等のレペを出来る限り多く観ておきたかったのである。私はリジョに電話を入れ、翌日から始まるレペの場所と時間を訊いた。その後三人でパリの裏町を散策した。行くところはクリシーからモンマルトルへ、そしてその下に広がるアラブ人街だった。パリの中でも、この周辺は実に面白い。モンマルトルの澄んだ空気を満喫したあとで、徐々に坂を東へ下りて行くと、やがて生活の臭いが立ちこめ、アラブ人街に近づくとその臭いはどぎついものになる。バルベスから脇道にそれてアフリカ人の多く住みついているあたりまで来ると、明らかな黒い肌の臭いがし、空気も目に見えてよどんでくる。それは懐かしいザイールの香りだった。アフリカの原色に満ちた布を売る店や、店頭で串焼き肉カムンデレを焼いている店などがあり、車も入って来ない路地で黒いガキどもがサッカーに興じているのを見ると、ここがパリであることを忘れた。かつてはフランス人が通っていたであろうカフェも、いまではアフリカン・レストランになって、コーヒーなどよりも主にビールと肉料理を安い値段で出す店になっていた。のみならずあたりは、けたたましいリンガラ・ポップスが鳴り響いていた。この空気に触れるだけでもパリに来た甲斐がある。
翌日、ヌーベルのレペのためにメニル・モンタンへ行った。古いアパルトマンを改造したスタジオは、入るなり大麻の煙のウッと来る、すさんだ空気に満ちていた。低いベースの音が鳴り響いていた。それはあちこちの部屋から混ざりあって地を這うように思われた。受付で部屋を訊いて奥に進んだ。階段によりかかって白目をむいたラスタ・ヘアの黒人、低い声に似合わない激しい身ぶりで顔をくっつきあわせるように議論している若者、窓辺でいちゃついているカップル、そんなのを横目に見ながらわれわれは示されたドアを押して中に入った。例によって中はすし詰めに近かった。狭い部屋の壁際を埋め尽くしたとりまき連中の真ん中にメンバーたちはいた。リジョがわれわれに気づいて手を挙げた。いくつもの黒い顔の中の白い目がギョロッと一斉にこちらを振り向き、われわれを上から下までなめるように睨み付けた。私は演奏の止まるのを待って人垣を越えてメンバーに近寄り、ひとりひとりに握手した。メンバーは全員知った仲だったが、彼等と笑いながら二言三言話し合っているときに、「イタミ」と声をかけてきた者があった。
 それはシモロだった。彼は、キンシャサでカルチェ・ラタンをやりながら、国立パーカッション楽団のメンバーも務めていたが、そのヨーロッパ・ツアー中にそこを抜け出してパリに落ち着いたのである。私は思いがけない友人との再会を喜んだ。そのうち再びレペが始められた。それはわれわれが感じたとおりのエキサイティングな内容だった。
それはシモロだった。彼は、キンシャサでカルチェ・ラタンをやりながら、国立パーカッション楽団のメンバーも務めていたが、そのヨーロッパ・ツアー中にそこを抜け出してパリに落ち着いたのである。私は思いがけない友人との再会を喜んだ。そのうち再びレペが始められた。それはわれわれが感じたとおりのエキサイティングな内容だった。
ヌーベルはリジョのリーダー・グループということが出来る。彼は、ビバ時代から摩訶不思議な曲を作る人として際立っていたが、その深遠さと複雑さと過激さが、取るべき形を求めてさまよっていた。ビバ時代の彼の作品は、そうした混沌とした部分と、緻密にアレンジされたダンス・パフォーマンスやアニマシォンの激しさという、ミス・マッチが大きな魅力だった。棒のように背の高いトミヨリ氏は、やはり棒のように微動だにせずにベースを弾きまくるボスという若者に釘付けになって、棒のように立ち尽くしていた。大西先生はまるで彼をそっくりそのままザイール人に仕立てたようなボンゴ・ウェンデとの再会を喜ぶあまり、お互いに全く言葉も通じないのに、にこやかに見つめあっては頷いていた。私は私で、見ようによってはトッポ・ジージョによく似ているドラマーのアウィロ・ロンゴンバの見事なスティックさばきを、ハイハットの真横に座って凝視していた。レペが終わると、夕暮れのパリをメンバーとともにシャトー・ルージュまで戻り、彼等のファンの集まる「メー・ジェー」というバーへ行き、そこで何本ものビールと、ザイール料理をたらふく食った。
大西先生とボンゴ・ウェンデは、もうひとりのギタリストのコレジャンという男のギターを取り上げて、ふたりでセッションを始め、大いに盛り上がった。トミヨリ氏はボスと話していたようだ。私は初めシモロと話していたのだが、彼は郊外に住んでいるからと言って程なく帰って行ったあと、アウィロやリジョと、ヌーベルの結成にまつわる話などを聞いた。店内はすっかりコーン紙のへたったスピーカーでヌーベルのアルバムをかけていて、その音のつぶれ具合がまさにキンシャサの夜を彷彿とさせた。さんざん飲み食いして騒いだのだが、われわれはミュージシャンの端くれだからという、システム・ザイロワの慣習の適用を受けて、ロハということになった。それから三日間はそんな日々が続いた。
そのレペの見学でわれわれの得たものは多い。私はアウィロから、スネアをハイ・ピッチでチューニングして、きわどいリム・ショットで音色を作り出す方法や、日本の常識では考えられないことだが、打面ヘッド裏側の中央部に小さく切ったティッシュ・ペーパーを微妙に張り付けて倍音をコントロールする方法などを伝授された。トミヨリ氏は、既にオロミデのマナーのベース奏法をマスターしていたが、さらにボスのつむぎ出す音のセンスを体で覚えたようだった。大西先生はボンゴ・ウェンデのギターを見ながら、いままでの自分の奏法が正しかったことを確認していたが、アコンパのコレジャンのギターを見て、そこにリズム・ギターの本質を見たと言っていた。彼はコレジャンからアコンパにおけるアンプのチューニングの仕方と、微妙なピックのタッチの加減を学びとった。
こうしてわれわれは短い間に多くの音楽的な収穫を得たのだが、そのおかげで滞在期間の半分以上が、あっと言う間に過ぎてしまった。最後のレペが終わって、コンセールまでの二日間は休養ということになったので、われわれはその時間を観光に費やした。凱旋門へ行き、グラン・アルシュへ行き、シャンゼリゼを歩き、ポンピドー・センターへ行った。セーヌの風に触れ、カルチェ・ラタンを散策し、ソルボンヌの近所の安メシ屋で食事をしたり、みやげ物を買ったりした。パリらしい楽しいひとときだった。
 そうしてコンセールの日がやってきた。会場は、サン・ドニ郊外にあるLSCという公会堂のようなところだった。われわれは夕方からリハーサルに付き合った。スタッフ面をして楽器類のセッティングを手伝い、音響のバランスを整えるのは楽しいものだった。リラックスして体をほぐしているメンバーとともに、様々な曲のおさらいをした。アウィロがトイレでキメている間に順番が来たので、私がドラムを叩いたりした。それはそれで楽しいものだったが、われわれにはひとつの心配があった。先日のレペが終わって打ち上げをやっていた時に、みんなで酔っぱらったあげく、リジョが自分の名曲「セシ・セラ」をわれわれを交えて演奏したいと言いだしたからである。
そうしてコンセールの日がやってきた。会場は、サン・ドニ郊外にあるLSCという公会堂のようなところだった。われわれは夕方からリハーサルに付き合った。スタッフ面をして楽器類のセッティングを手伝い、音響のバランスを整えるのは楽しいものだった。リラックスして体をほぐしているメンバーとともに、様々な曲のおさらいをした。アウィロがトイレでキメている間に順番が来たので、私がドラムを叩いたりした。それはそれで楽しいものだったが、われわれにはひとつの心配があった。先日のレペが終わって打ち上げをやっていた時に、みんなで酔っぱらったあげく、リジョが自分の名曲「セシ・セラ」をわれわれを交えて演奏したいと言いだしたからである。
初めは、どうせ酒の席でのことだったから、みんな忘れているに違いないと思っていた。その後二日間その話は出なかったので、われわれはその確信を強めていた。トミヨリ氏は心配そうに、「まさかあれをやるとは言わんやろな。」と私に何度も訊いたものである。ところがその心配が現実のものになった。サウンド・チェックの最中に、大西先生がボンゴ・ウェンデに、どっちがどっちのパートを弾くのか、と真顔で訊かれてびっくりしたというのである。全く練習していなかった。コード展開など覚えていよう筈がない。ましてや、ただでさえややこしいリジョの曲だった。しかもザイールを代表する名曲中の名曲である。われわれは焦った。とにかく構成を思い出そうとして、三人でうずくまって歌を思い出しながら打ち合わせをした。それを見ていたルシアナがにこやかにやって来て、歌をつけながらキメ場所を指示してくれた。われわれの不安をよそに、ルシアナはOKだと言って行ってしまった。何がOKなもんか。
われわれはリハーサルの途中でそこを抜け出し、メトロに乗ってホテルに一旦引き上げた。そして大西先生が、たしかその曲のテープを持って来ているはずだと言うので、彼の部屋で復習することにした。われわれはそれを何度も聞き直し練習して、回数をメモった紙を持ち、夜中に再び会場に戻った。コンセールは始まっていなかったが、会場は既に満杯だった。客の感じは、ビバなどに比べておとなしい印象を持った。コンセールはスモークが焚かれ爆竹が打ちならされる派手なものだった。しかし、システムが悪いのか会場の音響特性が悪いのか、音はモコモコだった。演奏は申し分なかった。やはり親分肌の人間がにらみを利かしているバンドの音楽とは全く違う、いきいきとしたもので楽しめた。しかし、われわれの心配は消えなかった。やるのかやらんのか、今もって疑わしかったからである。
二時間ほど経ってコンセールが中盤を迎えた頃、ヌーベルのローディーをやっている男がわれわれの前に来て、スタンバッてくれと言った。われわれは仕方なく心臓が口から飛び出そうになるのを抑えながらステージ・サイドに向かった。アウィロがドラムを叩きながら、私に大きな身ぶりで笑いかけた。私は目を伏せてしまった。前半最後の曲が終わり、リジョが、「ここでゲストを紹介します」というようなことを言った。われわれはステージに上げられ、まばらな拍手をもらった。日本から三人の友人が来ている、彼等はわれわれの音楽を演奏できる、ここでためしに俺の昔の曲「セシ・セラ」を彼等を交えてやってみようと思う、とリジョが紹介した。どよめきが拍手に変わり、意を決したように大西先生がイントロを弾きだした。もうやるしかない。
この曲はイントロにリジョの短いせりふが入る。例のキクウィットで私が耳にした「マクゥア・ンドゥング」という、あれで始まるのである。その後にリジョが、「アア?」と言うのに合わせて、ベースとドラムが入らなければならない。その瞬間をトミヨリ氏は次のように述懐している。「あの瞬間、会場を埋め尽くした真っ黒な人たちが一斉に『ああ?』と言ってぽっかり口を開けたんだ。それを思い出すとおかしくてベースが弾けなかったよ。」曲は流れはじめた。モニターの調子が悪くて互いの音が全く聞こえなかったが、われわれはとにかく演奏した。リジョの長い歌のパートが終わり、大西のフレーズに導かれて、曲はゆっくりとセベンに流れ込んでいった。いにしえのダンス「ルンバロック・フレンチェン」がアニメイトされ、曲は本格的に加速していった。ここまで来ればもうお手の物だった。トミヨリ氏の棒のような体が揺れているのが見える。私も楽しみはじめた。でも大西先生は堅くなっていた。とにかくその緊張の時間は成功裏に終わり、われわれは満場の拍手をもらった。こうして、ヌーベル・ジェネラシォンを見る旅は終わる。
「カーリー・ショッケール」の衰退
ヨーロッパにおけるザイール音楽の流れは、本国におけるそれと同じように、年を追うにつれて衰退していった。若手のウェンゲ・ムジカも、デビュー当時の大成功とその後の分裂のあと、本家というべき「BCBG」も数枚のアルバムを発表した頃には、持って行き場のないマンネリズムに陥っていた。来日公演のあと紆余曲折を経て、どうにかロンドンに活動の本拠を構えることに成功したヴィクトリア・エレイソンも、既に首領エメネヤが親分風を嵐のように吹かせまくって、音に生気がなくなった。尤もこれには、一九八九年に発表された革新的なファンク・アルバム「モコサ」以後、その実質的なコンポーザーであり、有能なギタリストであり、アレンジャーであり、エンターテイナーであったサフロ・マンザンギの脱退が大きく影響している。ヌーベルも三枚目以降のアルバムは、どれも同じ様な出来具合で新しさを打ち出すことが出来なかった。ウェンバもインターナショナル・バンドでの活動の情報は伝わって来ず、わずかにビバ名義のアルバムがリリースされはしたが、どれも聴く気にもならない駄作だった。
唯一新しい動きのあったことといえば、コフィ・オロミデがキンシャサからカルチェ・ラタンをパリに呼び寄せ、華やかな女性ダンサーと若手コーラス陣によるスペクタクル・ショウ形式でステージとアルバム制作の両方に取り組んだことである。そのコーラス陣の中には、ウェンゲと同世代の、SUZUKI 4X4というやんちゃ坊主がいて、徐々に頭角を現わしていた。その天性と思われる歌唱力と、若い世代の持つ独特のアグレッシブさが次の流れを引き出すかも知れないと思わせた。こうして一九九四年頃には、既に聴くべき新譜はなくなり、われわれの多くはCDで次々と復刻される、往年の名曲や幻の名盤を聴きあさることになる。私がザイールから帰って以来、OKジャズの魅力にとりつかれ、その絹の織物のように緻密に繊細に織りあげられた音の襞の美しさに虜になって、手に入れうる限りのアルバムを買いあさっていたのもこの頃である。
一方、カーリー・ショッケールは、われわれがヌーベルを見にパリへ行ったあと、トミヨリ氏と私によるリズム・セクションは、渡航の成果があって音的に成熟し安定していった。メロディ楽器では、アニキがリード・ギターを担当し、くまちゃんがキーボードでそれをサポートすることになったが、なにぶん職人気質の強いアニキのギターの音色は、派手できらびやかだった大西先生のそれとは大きく違っていて、その持ち味をわれわれがサポートできるようになるまでにずいぶんと時間がかかった。さらに改革は進んだ。高い声の出る大室を歌手としてコーラスの要に置き、中域での声量を持たせるためにカズはボイス・トレーニングに励んだ。アントワーヌそっくりの独特のキャラクターの歌手タコは、あえてその低い濁声を強調した。こうしてフロント陣にも徐々に声のメリハリがつくようになり、大西先生が抜けた後のカーリーの音造りは完成に近づいていった。
しかしこの頃から、カーリーの進むべき方向性をめぐって、内部で意見の対立が深まっていった。その対立とは、要するにオリジナル曲を作って日本語で歌うわれわれの演奏スタイルの根幹をめぐるものだった。つまりこういうことである。われわれは、ガキどもが集まってロック・バンドを始めるのと同じようにしてバンドを始めた。下手でもなんでも、自分たちの歌いたいことを歌いたいように歌うことを目指して、誰の指図を受けずにやってきた。つまりそれはロックだった。ザイールのリンガラ・ポップスに感じたものも、それがルンバの形式を踏んでいようがいまいが、われわれにとってはロックだったのである。形式とは無関係なところにある、いわば音楽の魂の部分にこそ、われわれは感動してバンドを始めたのであった。しかし、音楽というものは、のめり込めばのめり込むほどに、細かい違いがだんだん重要なことのように思われてくるものである。それは、遠くから見れば折り重なっているかのように見える山並みも、近くまで行けば何キロも離れているのと同じ事である。どんなにアフリカをイメージして演奏しても、出来そこないの十六ビートのロックにしか聞こえなかったものが、数々の経験を経てルンバのゆったりとしたニュアンスを出せるようになってみると、そのニュアンスの中の微妙なセンスの違いにこだわりを持つようになってしまったのである。どんなものにでも違いがわかるようになると、どんどんその違いの面白さの中にはまりこんでいくのは仕方のないことなのだが、それが度を超すと、一般の人には全く見分けのつかない細かい違いをめぐって、侃々諤々の論争になってしまうものである。われわれもまさにその罠に落ちてしまった。
ある者は、さらにそのニュアンスの違いを突き詰めて探求を先鋭化させようとした。しかし別の者は、そこに入り込むことを避け、もっと広く演奏表現の幅を広げるために、様々な実験をやろうとした。そこに大きな考え方の違いが発生したのである。私は後者の立場だった。自分たちが求めていたのはなんだったのか、確かにザイールのある種類の音楽に魅力を感じて始めたのは事実だったのだが、それはあくまで音楽として人が聴くに堪えるものでなければならないはずだった。多くの人にとって、また古くからのカーリーのファンにとっても、異常なまでに細かいニュアンスの違いなど、どうでもよいはずである。また、われわれはザイール人と同じ事を同じようにやる気はさらさらなく、また出来るはずもなかった。また、ザイール人ならおそらくそんなニュアンスの細かい違いなどをめぐって、こんな議論に発展したりするはずはないと思われた。なぜならそれは彼等の音楽だからである。つまりこんなことで対立すること自体が、その音楽を産み出した者でない者がその音楽を模倣しようとするから起こるのであって、その姿勢は既にこの音楽の精神に反する。それは余りにも不毛なことのように思われた。
しかし、メンバーの大半はそうは思わなかった。フロント陣を中心に、さらに凝り固まる傾向は加速して行き、それは歌い回しだけにとどまらず、バックの演奏にまで様々な要求が突きつけられるまでになった。歌詞そのものをリンガラ語にするところまでは行かなかったが、アニマシオンはリンガラ語に置き換えられ、さらにウェンゲやカルチェ・ラタン、ビッグ・スターズなどというバンドの流行りのものがコピーされるようになった。唱えられるアニマシオンの順番が厳密に決められ、それに従ってバックの演奏フレーズまでが細かく決められていった。どのギター・フレーズが何回なったら、私が何小節のフィルを入れるという具合だった。たまに興が乗って、私が思わずドラムをぶったたいてしまうと、それを合図と勘違いしたフロントが、とんちんかんなところで歌いはじめるということが起ったりした。確かにステージングにおけるメリハリは際立っていったが、あまりにも手順が細かく取り決められたので、これでは楽譜に書かれたものを演奏しているのと大した違いがなくなった。演奏の完成度は増したが、勢いがなくなってしまった。それはとりもなおさず、われわれが音楽をやる動機に対する裏切りだった。その頃から、私はバンド活動への情熱を、徐々に失なっていった。
ダンス・ユニット「OKガールズ」
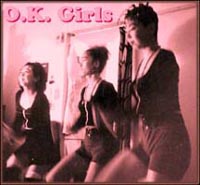 そんな一九九四年の春のことだった。私の住んでいた古くさいアパートに、実にコケティッシュでお茶目な女の子が引っ越してきた。彼女は大阪にある音楽とダンスと舞台芸術を教える専門学校に通う学生だった。私とは十四も歳が離れている。彼女は学校でダンスを専攻していて、夜な夜な廊下でステップの練習をしているのが見られたものだった。さらに服装がレゲエやラップのスタイルだったので、私はバンドにダンサーとして入ってみないかと誘ってみた。当時、パリから輸入されたばかりのオロミデ率いるカルチェ・ラタンのビデオを見せ、だいたいこんな感じのことをやりたいんだけど持ちかけてみると、彼女は非常に面白がり、その次の練習の日に友達をふたり連れてやって来た。
そんな一九九四年の春のことだった。私の住んでいた古くさいアパートに、実にコケティッシュでお茶目な女の子が引っ越してきた。彼女は大阪にある音楽とダンスと舞台芸術を教える専門学校に通う学生だった。私とは十四も歳が離れている。彼女は学校でダンスを専攻していて、夜な夜な廊下でステップの練習をしているのが見られたものだった。さらに服装がレゲエやラップのスタイルだったので、私はバンドにダンサーとして入ってみないかと誘ってみた。当時、パリから輸入されたばかりのオロミデ率いるカルチェ・ラタンのビデオを見せ、だいたいこんな感じのことをやりたいんだけど持ちかけてみると、彼女は非常に面白がり、その次の練習の日に友達をふたり連れてやって来た。
こうして、平均年齢が三〇歳を裕に超える気むずかしいバンドに、三人のピチピチギャルが加入することになった。メンバーの女たちが戦々恐々となったのは言うまでもない。しかしそれは要らぬ心配だった。彼女たちはそんな子たちではなかったからである。また、われわれは全員スケベなことにかけては海千山千だったが、曲がったことの嫌いな気のいいおじさんたちだったからである。さて、私は初め彼女らにコーラスとダンスを担当してもらおうと考えていたが、歌に女はいらんという意見に押されて、その考えは排除された。じゃあ、というんで、とりあえずセベンの部分からでもダンスを入れていってもらいましょうか、ということになった。こうして彼女らは、見たことも聴いたこともない遠いアフリカの音楽をやっている、この胡散臭いおっさん連中を大変面白がって、毎回練習に来るようになった。三人は、揃ってダンスのクラスにいたのだが、当然のことながらアフリカのものは習っていなかったので、われわれは腰使いから教えなければならなくなった。そのため、なるべくわかりやすいダンスから始めようということになって、ビデオで見られるアニマシオンやダンスを大室とその彼女が中心になって、彼女らにレッスンしはじめた。
当初、われわれは三人は長続きしないだろうと思っていた。何しろ流行らないジャンルの音楽だったし、メンバーとの年齢に違いがありすぎて、気を遣うのではないかと思ったからである。しかし彼女らはハマってきた。どう感じているのかは知る由もなかったが、彼女らなりにこの音楽に魅了されているようだった。その頃からバンドの練習はフロントとバックに別れて行なわれるようになり、セベンはダンサーのレッスンの内容に従って構成がまとめられるようになった。それにつれてフロントのバックへの注文もさらに細かくなっていった。半年ほどで、彼女らはステージに立てるまでに上達した。しかし、その間に三人のうち一人が辞めたので、大室の彼女が交替で参加することになった。三人は「OKガールズ」と名乗った。もちろんこれはOKジャズを意識してのことである。
こうして新しいカーリーの珍道中が始まった。私はマネージャーとして、ショウ・アップされたステージを売り物にライブの仕事をたくさん取ってきた。大西先生脱退による一年近いブランクの後、そしてOKガールズのステージングのための半年の空白の後、その都度変貌していくわれわれのステージを、昔からのファンは評価してくれた。ショウ・アップされたステージは新しいファンを増やし、初めて見た人たちからも高い評価を受けた。演奏や歌も、もはや初期の頃の独りよがりなものではなくなり、内部には依然異論があったものの、おおむね聴くにたえるものが出来るようになっていた。その頃ならプロ・デビューの話や、レコーディングの話があれば、即座に受け容れることが出来ただろう。しかし、残念ながらもはや世の中は、われわれのようなバンドにお呼びがかかるほど呑気なご時世ではなくなっていた。一時決裂しかかっていたバンド内の意見も、とりあえず現状を維持しながらやっていくこと、つまりOKガールズのダンスを交えたステージングを継続するということで、どうにか収拾の方向に向かった。誰もその点を突き詰めて問いただそうとはしなかった。しかし、意見の合うメンバー同士ではときどき愚痴がこぼれた。われわれはやりたいことをやりたいようにやるバンドから、バンド活動を維持するためのバンドになってしまった。わかりやすくてきらびやかなステージを演出する、ちょっと変わったアフリカのダンス音楽をやるバンドという、一定の評価を得た代わりに、演奏の独創性と自由を失なった。
私は、良くも悪しくもここから出発するしかないと考えた。われわれは才能豊かな集団でもなければ、スター性のある中心人物がいるわけでもない。始めた頃から理想は高かったのだが、多くを一度に望んでも仕方がないものと自分に言い聞かせた。 われわれに与えられたこの評価と内部の現実が、われわれの偽らざる姿だった。これは謙虚に受けとめる以外に仕方がない。そして私は、単独ライブの実現を目指して大きなライブ・ハウスやホールへの働きかけを強めてゆき、演奏曲のバリエーションを増やすために、ダンス・パフォーマンスだけの民俗音楽色の強い曲を提案した。そうして紆余曲折の末、それまでまともなライブをやらせてもらえなかった神戸で、ある老舗のライブ・ハウスでの出演交渉がまとまり、翌一九九五年の春以降に、持ち込み企画で継続的な出演が出来そうな見通しが立った。
その矢先のことである。年が明けてすぐに兵庫県南部を強烈な地震が襲った。ほとんどのメンバーが家を失ない、神戸にあったその老舗のライブ・ハウスも瓦礫の山になってしまった。
地震の後遺症からグループの解散へ
この地震で失なわれたものをあげつらっていけばきりがない。私の場合、助かったのは自分の命ばかりだった。その後、人命の救出活動のかたわら、土砂木屑の山と化した自分の部屋を、つるはしやスコップでもって掘り返しはじめたのだが、なんとかあきらめのつくまでにひと月近くかかった。慣れ親しんだ家具調度はいうに及ばず、長い間かかって買い集めた書籍やレコード、同じものがこの世にふたつとないザイール現地録音のテープやフィルム、写真などの大部分が失なわれた。三百枚はあったザイールのドーナッツ盤は、今ではそのほとんどが甲子園浜の埋め立て地で眠っていることだろう。パチョ・スターやジュジュ・シェをはじめ、リシャ・シャ、アウィロなど、著名なザイール人ドラマーのフレーズのニュアンスを、細かく分析して打ち込んだシーケンスのデータも、二度にわたるザイール旅行について、人が読めるようにまとめ終えようとしていた、二十万字を超える原稿を打ち込んだデータも、マッキントッシュの本体とバック・アップのフロッピーとともに土に還って行った。
しかし、いくらかの重要なレコードやテープ、フィルムと楽器が残った。何かを思い悩んでいる時間など、当時の私には残されていなかった。私は持てる限りのものを持ち、運びうる限りのものを安全な場所に運んで事態が好転するのを待った。避難所を出るのに二週間、物置に住むこと三カ月、恐怖とすなぼこりの中で迎えた三五回目の誕生日に、尼崎市内の線路沿いにちっぽけな部屋を借りることが出来た。しかしこれでも早い方だった。
仕事を失なってしまった私は、暇に飽かせて阪神間の街の移り行きを写真に撮り続け、そこに生活する沢山の知り合いのことを書きはじめた。書き進むにつれ、それはただならぬ量にふくれあがって行き、一定の形式を帯びはじめ、ひとつの物語らしき形を得た。それが一段落すると、今度は失なわれた記憶の中に散在する、ザイール旅行のエピソードの断片を拾い集めて、カップ・ヌードルに熱湯をかけるようにそれをふやかしはじめた。そして出て来たものを自動記述のように右から左へと言葉にし、事実関係を再構成することによって、瓦礫の中に喪失してしまった旅行記の復元を図ろうとした。
梅の便りも桜の開花も知らず、梅雨も猛暑も気にならなかった。列車の騒音や振動に悩まされながら、方丈の庵にひきこもってひたすら文章を書き続けた。仕事もせず、新聞もテレビもなかったので、世の中の大きな出来事のほとんどを知らずに何日も過ごすことがよくあった。それは、自分自身の心のわだかまりや、やり場のない怒りに踏ん切りをつけるための自己完結的な行動だった。また毎晩のように襲いかかる、形のない恐怖と終わりのない悪夢から逃れるための、ほんの気慰みでもあった。精神状態の激変は、当然音楽の趣味嗜好にも反映していった。自宅に逃げ込んだとき、初めて聴こうとしたのは、バッハのチェロ・ソナタである。もはやリンガラ・ポップスの明るい楽天的な華やかな音は、当時の私の精神状態からすれば、やかましい以外の何物でもなくなっていた。ひたすらに静けさと心の安らぎがほしかったからである。その傾向はそれ以後変わることなく、趣味嗜好はクラシックの室内楽をはじめ、静かなジャズ・ピアノ、モータウン系のソウル、そして黒人のラップへとつながっていくことになる。
カーリーの活動は、交通網が整備されはじめた春まで中止を余儀なくされた。その後、徐々にライブ活動を復活させてゆき、音の感覚を取り戻していった。私は半ば義務感から、以前のように営業活動を再開した。そして夏には、大阪と神戸の大きなホールで行なわれる、翌年の冬から春にかけての日替わりイベントへの出演契約をとりつけた。地震で一旦くじかれたカーリーの活動も、OKガールズを交えた華やかなステージングをひっさげて、ようやく陽の目が見られるかのようにみえた。
しかしその矢先、今度はアニキの実父が倒れ、そのためにメンバーの根幹をなす福丸兄弟とクマちゃんが大阪を離れなければならなくなった。さらに大室の東京への転勤が決まり、タコが徳島の実家を継ぐことになった。OKガールズの卒業や就職も重なり、十一人を数えたカーリー・ショッケールは、瞬時にして私とトミヨリ氏と大西先生の三人だけになってしまった。もとの黙阿弥である。八年間も変わることなく活動を続けてきたわれわれだったが、この完膚なきまでの状況の急変には成すすべがなかった。われわれはいつのまにか、家庭の事情が原因でバンドを解散させなくてはならない年齢を迎えていたのである。もう、ロックだ魂だなどとほざいている場合ではないのかも知れない。
年末から春にかけての一連のワンマンライブの皮切りにと、十三のファンダンゴでブッキングしたライブがラスト・コンサートになってしまった。一九九五年九月三〇日のことである。こうしてカーリーの音楽活動は、あっけなく終わった。私は解散の記念に、とりあえず現状のわれわれの音をきちんと残しておきたいと考え、レコーディングをしようとメンバーに持ちかけた。例によって反対意見も多かったが、それまでのカーリーの営業利益に幾らかの金を出し合えば、簡単にできることがわかったので、それは実現した。レコーディングの全ての段取りを終え、ミックス・ダウンにこぎつけたのは、クリスマス寒波の頃だった。その冷たい空気と冬の淡い太陽の光は、いやがうえにも一年足らず前にわれわれの人生を変えた災害のことを思い出させずには置かなかった。一時持ち直していた私の精神状態も、冬の訪れとともに不安定になり、悪夢にうなされる不安な夜が毎晩のように続くようになった。
トゥンバ・マシキニの謎
さて、私は地震の前に三度目のザイール旅行を計画していた。しかし、地震にともなう精神状態の急変のために、ザイール音楽一般に対してかつてのような情熱的な興味を失なってしまったため、その計画や目的について書くことは無駄だと思われる。地震さえなければ、瓦礫の中をさまよっていた頃には、とっくにザイールの奥地で天国か地獄を見ているはずだった。しかしそのために用意していた金も時間も資料も気分も、一瞬にして吹っ飛んでしまった。カーリーが解散した後、私は音楽活動をやめた。おかげで、やっと重い荷を降ろして身軽になり、残された三人で気ままにやりたい音を捜そうということになった。もう大編成のバンドはやらない。われわれ三人は歌が歌えないので、ライブもやらない。コンピューターとディスク・レコーダーの力を借りて、プログラムと多重録音を中心にした音楽を創ることに重点を置く。気心の合った者だけで、誰に聴かせるでもない、自分たちの満足のためにのみ演奏する。バンドがあって自分たちがあるのではなく、一人一人が思い思いの曲を作って、それを具体化するためのバンドを目指す。などということを話し合った。とにかく、しばらくは音楽のことを忘れて休養することにした。私は救い出して手許に残されたレコードやテープを片っ端から聴きはじめた。それらをほぼ年代順に、そして傾向によって分類し、古いものから順に聴いていった。
私のコレクションは、イギリスの七〇年代プログレッシブ・ロックのひとつの流れであった「カンタベリー・ファミリー」から始まっている。そしてヨーロッパのプログレに移り、現代音楽、小編成のクラシックへ、それと並行してパンク・ロックからオルタナティブへと広がった。そしてある時期を境にしてジャズへの傾倒が始まり、黒人の音やラテンなどを求めていくようになった。その若き日々の関心の移り行きを追体験することによって、私が音楽の中に求め続けてきた、口では言い表わし得ないある無限なるもののおぼろげな姿を見ようとした。それは演奏された瞬間に消え去ってしまう、宿命的な音の性質の不思議さと、深い井戸を覗き込んだときに、吸い込まれそうな闇の中に感じる、暗い空間の広がりに対する畏れのようなものだった。レゲエ、スカ、サルサ、コンパ、マンボ、タンゴ、サンバ、ボサノバ、ジュジュ、マコッサ、リンガラ。こうしたラテン系の音は、音楽のコアともいえるそれら一種暗い魂に関わる部分を、巧みにくるんで明るさに溶け込ませたようなところがある。かなりの数が失なわれたとはいえ、すべてを聴き尽くすのに一年以上を要した。そして、私が身を入れて聴いて来なかったもの、すなわちアメリカン・ブラック・ミュージックの王道の中に、徐々にではあるが、確かな感覚、すなわちある種のスピリチュアルなものを感じはじめていた。そのため、もう一度人生をやり直すような気持ちで、そうしたメジャーなシーンをていねいに聴きなおしていった。
ザイールへの第三の旅、もしそれが実現できるのであれば、それはリンガラ・ポップスでもルンバでもない、もっと大きな人間の黒さを捜しに行く旅となるはずである。私が音楽に感じた黒さを身に浴びに行く旅である。それはロックだともいえるし、ソウルだともいえるし、ブルースだともいえるだろう。それこそジャズだと言う人もあるかも知れない。音楽の無限なるもの、私にはそれが黒さだと感じているだけで、何なのか正体は分からない。しかし、それはどうやらザイール中部の、エクアテールからバンドゥンドゥのあたり、「マイ・ンドンベ(黒い水)」という地域を中心に広がる、ザイールの最も深い熱帯雨林の中にあるような気がする。そこから出た人の創る音楽が、やはり世界で一番黒いように思われるからである。そこへ行けば、何者にも毒されていない、純粋な黒い音楽の伝統が、まだ壊されずに残っているのではないか。そして、黒人特有の、あの低くて深くて豊かな歌声の中に潜む、強烈なリズムの骨格、すなわち世界中のすべての黒人音楽の暗さと深みと力強さの源泉が残っているのではないかと思えるのである。
ザイール人は、よく歌の中で「トゥンバ・マシキニ」という言葉を使う。いろいろなミュージシャンに訊いても、その意味が判然としないのだが、それは音楽を、特に打楽器やリズムを司る精霊、あるいは原理とでもいうような意味を表わしている。彼等はこの言葉を使うとき、なにか切なさにも似た、遠い眼差しのなかで使っているように感じられる。その切なさは、われわれがザイールのルンバをやりたいと志したときに駆り立てられた独特の感情、つまり完全に手に入れることなど出来るはずがないとわかっていながら、それでもやらずにはいられない衝動であるような気がする。それは、世界中の混血音楽に共通する、特殊な感情の屈折に通じるものがある。好きで好きでたまらないのに、決してそれ自身にはなり得ない、しかしそれでも好きだからやってしまう、どうしようもない「性」。彼等ザイール人も、同じ切なさに駆り立てられて音楽の虜になっているのだとすれば、彼等が神と崇め、原理と考えるものを極めることこそ、最も核心を突く方法ではないか。彼等が最も濃いと思う地域に出向き、その音楽を身に浴びて、自分の感覚の中にいくらかでも取り入れることこそ、この謎に少しでも近づける方法なのではないか、と私は思うのである。そして願わくば、そんな音楽の中にまみれて、死ぬほど演奏し続けることが出来るとすれば、それ以上の幸せがこの世にあるだろうか?。次なる旅は、少しでもそこに近づきたいのである。
 大西先生が辞める直前、パリで「ヌーベル・ジェネラシォン」というグループが結成された。これはかつての第二期ビバ・ラ・ムジカの歌手だったリジョ・クウェンパ、ファファ・デ・モロカイ、ルシアナ、ファタキを中心に、ギターのボンゴ・ウェンデ、ドラムのアウィロ・ロンゴンバなどが、ウェンバに反旗を翻す形でビバを脱退して結成されたものである。パパ・ウェンバはかつて七〇年代後半には確かに若者の代弁者であったし、若い音楽の改革の闘士であったことは事実である。それを彼は自らの甲高い声とロック魂で実現してきた。しかしそれから十五年が過ぎ、彼の威光も自分で築き上げた古くさい権威主義の煤けた霞の中で、その輝きを鈍らせつつあった。それに反発する者が出てくるのは当然である。彼等にとってウェンバは、もはや自分たちの音楽の代弁者ではなく、単なる気むずかしい親分だった。しかも怒らせるとただでは済まない厄介な独裁者だった。彼等は長い間親分の顔色をうかがいながら歌い、演奏することを余儀なくされてきた。第二期ビバの結成からほぼ一〇年目にして、彼等の忍耐は限界に来てしまったのである。
大西先生が辞める直前、パリで「ヌーベル・ジェネラシォン」というグループが結成された。これはかつての第二期ビバ・ラ・ムジカの歌手だったリジョ・クウェンパ、ファファ・デ・モロカイ、ルシアナ、ファタキを中心に、ギターのボンゴ・ウェンデ、ドラムのアウィロ・ロンゴンバなどが、ウェンバに反旗を翻す形でビバを脱退して結成されたものである。パパ・ウェンバはかつて七〇年代後半には確かに若者の代弁者であったし、若い音楽の改革の闘士であったことは事実である。それを彼は自らの甲高い声とロック魂で実現してきた。しかしそれから十五年が過ぎ、彼の威光も自分で築き上げた古くさい権威主義の煤けた霞の中で、その輝きを鈍らせつつあった。それに反発する者が出てくるのは当然である。彼等にとってウェンバは、もはや自分たちの音楽の代弁者ではなく、単なる気むずかしい親分だった。しかも怒らせるとただでは済まない厄介な独裁者だった。彼等は長い間親分の顔色をうかがいながら歌い、演奏することを余儀なくされてきた。第二期ビバの結成からほぼ一〇年目にして、彼等の忍耐は限界に来てしまったのである。  それはシモロだった。彼は、キンシャサでカルチェ・ラタンをやりながら、国立パーカッション楽団のメンバーも務めていたが、そのヨーロッパ・ツアー中にそこを抜け出してパリに落ち着いたのである。私は思いがけない友人との再会を喜んだ。そのうち再びレペが始められた。それはわれわれが感じたとおりのエキサイティングな内容だった。
それはシモロだった。彼は、キンシャサでカルチェ・ラタンをやりながら、国立パーカッション楽団のメンバーも務めていたが、そのヨーロッパ・ツアー中にそこを抜け出してパリに落ち着いたのである。私は思いがけない友人との再会を喜んだ。そのうち再びレペが始められた。それはわれわれが感じたとおりのエキサイティングな内容だった。  そうしてコンセールの日がやってきた。会場は、サン・ドニ郊外にあるLSCという公会堂のようなところだった。われわれは夕方からリハーサルに付き合った。スタッフ面をして楽器類のセッティングを手伝い、音響のバランスを整えるのは楽しいものだった。リラックスして体をほぐしているメンバーとともに、様々な曲のおさらいをした。アウィロがトイレでキメている間に順番が来たので、私がドラムを叩いたりした。それはそれで楽しいものだったが、われわれにはひとつの心配があった。先日のレペが終わって打ち上げをやっていた時に、みんなで酔っぱらったあげく、リジョが自分の名曲「セシ・セラ」をわれわれを交えて演奏したいと言いだしたからである。
そうしてコンセールの日がやってきた。会場は、サン・ドニ郊外にあるLSCという公会堂のようなところだった。われわれは夕方からリハーサルに付き合った。スタッフ面をして楽器類のセッティングを手伝い、音響のバランスを整えるのは楽しいものだった。リラックスして体をほぐしているメンバーとともに、様々な曲のおさらいをした。アウィロがトイレでキメている間に順番が来たので、私がドラムを叩いたりした。それはそれで楽しいものだったが、われわれにはひとつの心配があった。先日のレペが終わって打ち上げをやっていた時に、みんなで酔っぱらったあげく、リジョが自分の名曲「セシ・セラ」をわれわれを交えて演奏したいと言いだしたからである。 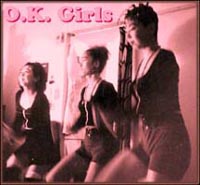 そんな一九九四年の春のことだった。私の住んでいた古くさいアパートに、実にコケティッシュでお茶目な女の子が引っ越してきた。彼女は大阪にある音楽とダンスと舞台芸術を教える専門学校に通う学生だった。私とは十四も歳が離れている。彼女は学校でダンスを専攻していて、夜な夜な廊下でステップの練習をしているのが見られたものだった。さらに服装がレゲエやラップのスタイルだったので、私はバンドにダンサーとして入ってみないかと誘ってみた。当時、パリから輸入されたばかりのオロミデ率いるカルチェ・ラタンのビデオを見せ、だいたいこんな感じのことをやりたいんだけど持ちかけてみると、彼女は非常に面白がり、その次の練習の日に友達をふたり連れてやって来た。
そんな一九九四年の春のことだった。私の住んでいた古くさいアパートに、実にコケティッシュでお茶目な女の子が引っ越してきた。彼女は大阪にある音楽とダンスと舞台芸術を教える専門学校に通う学生だった。私とは十四も歳が離れている。彼女は学校でダンスを専攻していて、夜な夜な廊下でステップの練習をしているのが見られたものだった。さらに服装がレゲエやラップのスタイルだったので、私はバンドにダンサーとして入ってみないかと誘ってみた。当時、パリから輸入されたばかりのオロミデ率いるカルチェ・ラタンのビデオを見せ、だいたいこんな感じのことをやりたいんだけど持ちかけてみると、彼女は非常に面白がり、その次の練習の日に友達をふたり連れてやって来た。