『地震をめぐる空想』
第二章、地震翌日から脱出までのあらまし
 「高級アパート宝山荘」は、昭和三十年代に建てられた実に瀟酒なアパートだった。それが建っていたのは、六甲山から流れ出る、桜の名所としても名高いある小川の近くである。当時はまだアパートで暮らすのは贅沢なことだとされていたので、建物の内部にはその時代の気品を感じさせるような造作が随所に見られた。建物の基礎がおかれていた位置は地面より七十センチほど高く、これは過去にこの付近一帯を襲った大水害のさいには威力を発揮した。さらにそこから数段上がると、薄く切った石を並べたポーチになっており、タイル張りの二本の柱に支えられた庇がついていた。この二本の柱は、家主や管理人までもがコンクリートの無垢だと思っていたのに、倒れたあと切り口を見てみると、芯は木材で、しかも白蟻が食ってぼろぼろになっていた。そこを入ると、盆栽や観葉植物の飾られたタイル張りの玄関になっていて、一枚岩の御影石の上がりかまちがあった。全体として温泉旅館を思わせる風情があって、玄関で靴を脱ぎ、ずらりと並んだ部屋番号つきの下駄箱に各自靴を入れ、スリッパにはきかえて上がるのである。木造二階建て、中央に廊下があって両側に部屋が並ぶという、典型的な昭和のアパートの造りであった。その廊下は歩くと音のするところから、住人たちから鴬張りの廊下と呼ばれていた。それは管理人が実にきれい好きで、毎日よくもまあ続くもんだと誰もが感心するぐらい念の入った掃除をしたため、廊下は常にぴかぴか、木材のきしむ音と磨き上げられた表面でスリッパのこすれる音が、微妙なハーモニーを奏でていた。その掃除の仕方とは、通り一遍のはたきがけと掃きそうじのあと、水に濡らして細かくちぎった新聞紙を固く絞って廊下中にふり撒き、それをほうきで掃き集めるという古色蒼然としたものだった。毎朝亭主を送り出してから、せわしないもの音をたてて一階から掃除が始まり、人が寝ていようがなにしてようがお構いなしに、廊下側の窓をばんばんはたくので、おかげで病気のときも仮病のときも、二日酔いのときも徹夜仕事を終えてようやく眠りに落ちかけたときも、こちらの都合には全くおかまいなしに、毎日決まった時刻に文字通り叩き起こされる羽目になった。 しかしその超人的な、飽くことのないたゆまぬ努力のおかげで、住人たちから二百年のときを超えたほまれ高きその名をいただくことになったのである。その廊下は地震のおかげで真っ先に地面に没してしまったけれども、その光沢は、自分の財産の保全のために若い連中が夜っぴて瓦礫と化したアパートの底をほじくりかえしていたときにも、その手許を下からそっと照らして財産のありかを指し示してやるほどだった。その廊下の北側の突き当たりには、二階に上がる階段があり、その前に金だらいがよく似合うタイル張りの洗面所があった。各部屋にも流しがあったが、その洗面所はとても共同住宅臭くて、寒い冬の朝など、なんとも知れぬ情緒を漂わせていたものである。階段の裏手は共同の便所になっていて、最近になって水洗化された。その天井には大きなまるい電球カバーがあって、それがまた昔の夜汽車の客室のような暖かい光をやさしく投げかけていた。それとならんで、すでに物置となって久しい共同の風呂場があったが、これもタイル張りでまるい天井を持っていた。階段を上がるとちょっとした踊り場があり、そこの窓からは、暮れなずむ夕焼けに浮かぶ教会の尖塔が、シルエットとなって眺められたものである。上がりきった二階にも大体同じような洗面所と便所があって、非常階段のついた古い木製のベランダがあった。これら住人が共同で利用する各部所には、管理人直筆の注意書がそこかしこに貼られてあった。カイダンノノボリオリハシズカニ、ゴミハキマッタヒニダシマセウ、ベンキニタバコヲステルナ、セイリノカミハクズカゴニステマセウ、微に入り際に入ったその文句はなんとも忘れられないものだった。各部屋は、手前が三畳弱の台所のついた板の間で、奥が四畳半の畳の間だった。窓は出窓になっていて大きく、その下に便利な戸袋までついていた。私の部屋は二階の南端の東側にあって、その廊下の突き当たりには、われわれが真っ先に脱出した例の鉄の階段のついたベランダがあった。はじめて不動産屋とともにこのアパートを訪れたとき、窓が大きいためか全体として明るい印象を受けたことを覚えている。私はかわいらしいこの部屋が一発で気に入り、その場で契約書にはんこを押した。しかし美しく見えたこの大きな窓が壁の強度を損なう結果となり、一階の部屋を跡形もなく押し潰すことになろうとは、夢にも思わなかった。
「高級アパート宝山荘」は、昭和三十年代に建てられた実に瀟酒なアパートだった。それが建っていたのは、六甲山から流れ出る、桜の名所としても名高いある小川の近くである。当時はまだアパートで暮らすのは贅沢なことだとされていたので、建物の内部にはその時代の気品を感じさせるような造作が随所に見られた。建物の基礎がおかれていた位置は地面より七十センチほど高く、これは過去にこの付近一帯を襲った大水害のさいには威力を発揮した。さらにそこから数段上がると、薄く切った石を並べたポーチになっており、タイル張りの二本の柱に支えられた庇がついていた。この二本の柱は、家主や管理人までもがコンクリートの無垢だと思っていたのに、倒れたあと切り口を見てみると、芯は木材で、しかも白蟻が食ってぼろぼろになっていた。そこを入ると、盆栽や観葉植物の飾られたタイル張りの玄関になっていて、一枚岩の御影石の上がりかまちがあった。全体として温泉旅館を思わせる風情があって、玄関で靴を脱ぎ、ずらりと並んだ部屋番号つきの下駄箱に各自靴を入れ、スリッパにはきかえて上がるのである。木造二階建て、中央に廊下があって両側に部屋が並ぶという、典型的な昭和のアパートの造りであった。その廊下は歩くと音のするところから、住人たちから鴬張りの廊下と呼ばれていた。それは管理人が実にきれい好きで、毎日よくもまあ続くもんだと誰もが感心するぐらい念の入った掃除をしたため、廊下は常にぴかぴか、木材のきしむ音と磨き上げられた表面でスリッパのこすれる音が、微妙なハーモニーを奏でていた。その掃除の仕方とは、通り一遍のはたきがけと掃きそうじのあと、水に濡らして細かくちぎった新聞紙を固く絞って廊下中にふり撒き、それをほうきで掃き集めるという古色蒼然としたものだった。毎朝亭主を送り出してから、せわしないもの音をたてて一階から掃除が始まり、人が寝ていようがなにしてようがお構いなしに、廊下側の窓をばんばんはたくので、おかげで病気のときも仮病のときも、二日酔いのときも徹夜仕事を終えてようやく眠りに落ちかけたときも、こちらの都合には全くおかまいなしに、毎日決まった時刻に文字通り叩き起こされる羽目になった。 しかしその超人的な、飽くことのないたゆまぬ努力のおかげで、住人たちから二百年のときを超えたほまれ高きその名をいただくことになったのである。その廊下は地震のおかげで真っ先に地面に没してしまったけれども、その光沢は、自分の財産の保全のために若い連中が夜っぴて瓦礫と化したアパートの底をほじくりかえしていたときにも、その手許を下からそっと照らして財産のありかを指し示してやるほどだった。その廊下の北側の突き当たりには、二階に上がる階段があり、その前に金だらいがよく似合うタイル張りの洗面所があった。各部屋にも流しがあったが、その洗面所はとても共同住宅臭くて、寒い冬の朝など、なんとも知れぬ情緒を漂わせていたものである。階段の裏手は共同の便所になっていて、最近になって水洗化された。その天井には大きなまるい電球カバーがあって、それがまた昔の夜汽車の客室のような暖かい光をやさしく投げかけていた。それとならんで、すでに物置となって久しい共同の風呂場があったが、これもタイル張りでまるい天井を持っていた。階段を上がるとちょっとした踊り場があり、そこの窓からは、暮れなずむ夕焼けに浮かぶ教会の尖塔が、シルエットとなって眺められたものである。上がりきった二階にも大体同じような洗面所と便所があって、非常階段のついた古い木製のベランダがあった。これら住人が共同で利用する各部所には、管理人直筆の注意書がそこかしこに貼られてあった。カイダンノノボリオリハシズカニ、ゴミハキマッタヒニダシマセウ、ベンキニタバコヲステルナ、セイリノカミハクズカゴニステマセウ、微に入り際に入ったその文句はなんとも忘れられないものだった。各部屋は、手前が三畳弱の台所のついた板の間で、奥が四畳半の畳の間だった。窓は出窓になっていて大きく、その下に便利な戸袋までついていた。私の部屋は二階の南端の東側にあって、その廊下の突き当たりには、われわれが真っ先に脱出した例の鉄の階段のついたベランダがあった。はじめて不動産屋とともにこのアパートを訪れたとき、窓が大きいためか全体として明るい印象を受けたことを覚えている。私はかわいらしいこの部屋が一発で気に入り、その場で契約書にはんこを押した。しかし美しく見えたこの大きな窓が壁の強度を損なう結果となり、一階の部屋を跡形もなく押し潰すことになろうとは、夢にも思わなかった。

このアパートには、妙にひなびた落ちつける雰囲気があって、一人暮らしを密かに楽しむにはもってこいだった。不思議なくらい時の流れから切り離された雰囲気に満ちていたので、部屋にいることそのものが楽しかった。日がな一日、じっと部屋に差し込む光の変化を眺めながら、季節感を味わう日も多かった。大きな窓を全開にすると、まるで巨大なキャンバスのように、季節によってゆっくりとうつろいゆく外の風景に溶け込むことができた。春は、桜の名所が近いため、浮かれる花見客の歓声とともに、西からの風に乗って花びらが部屋に舞い込んだ。新緑の季節には、霞に和らげられた光と湿った南風の薫に胸をおどらせ、草いきれとともに来襲しはじめる蚊の大群を迎え撃つために、はやばやと蚊取り線香を焚いた。長い梅雨の頃は、分厚い雨のカーテンと深い緑のむせるような吐息のなかで、時が音をたてて錆び付いていくのを感じ、窓から迷い込んだ魚がベランダから泳いで出て行けるかと思われるほどの濃厚な湿気に耐えた。夏は、夜明けとともに襲いかかる強烈な陽射しに耐えかねて、廊下で目を覚ますこともしばしばだった。特に宝山荘最後の夏は、室内の温度が人間の体温をはるかに上回る殺人的な猛暑だった。陽炎の立つ廊下を、住人たちはのぼせた頭で、ふらふらと亡霊のように歩いたものだった。三ヵ月を越える長い長い夏が過ぎて、やっとの事で気温が下がりはじめたとき、よくもまあ死人が出なかったものだ、とためいき混じりに話し合ったものである。秋は、斜めからはかなく差し込むようになった陽光に、全てのものが金色に光り輝く様を見て涙ぐみ、その美しい陽射しに我を忘れていると、いつの間にか部屋が枯葉で埋め尽くされていた。冬の寂しさはひとしきりで、隙間風と厳しい寒さに身も凍るばかりだったが、独りですする鍋ものの湯気にガラスが鈍く曇るのを見て、なんとも孤独な感傷に浸ることができた。貧しくはあったが、全く気ままで誰にも邪魔されることのない生活だった。風呂はなかったが、そのかわり大きな神社が近かったので、近所に銭湯が四軒もあり、行き帰りには桜で有名な川べりの公園をぶらぶらと散歩しながら通ったものである。無論、いいことばかりではなかった。台所に換気扇がないために、炒めものの油が細かい霧となって飛散し、部屋じゅうのものに膜を張って、それにほこりがこびりついた。土壁のため砂ぼこりが多く、ちょっと掃除を怠ると畳がざらついた。夜中に白蟻が木をかじる音がしたり、屋根裏を鼠が駆け回る音がしたりした。数年前からは、前をトラックが通るたびに建物が軽く揺れるようになり、全体がわずかに傾いてきたのか、開けた扉が勝手に閉まるようになった。しかし古い建物だからと、誰も気にする様子はなかった。よく住人たちと、ここが朽ち果てるまで住み続けてやると言い合っていたものだが、それがこんなに早く、しかもこんな形で実現されようとは夢にも思わなかった。「まあ、どっちみちあの建物の寿命は、いくばくもなかったのさ。」

避難所で一夜を明かした翌朝も快晴だった。昨夜は食料の配給のあと、怪我人や病人の収容などがあって、若い者はたいがい明け方近くまで走り回っていた。今朝は早くから一部の人が朝食用の食料の手配を試みていたが、結局うまくいかなかったと放送されていた。緊張感からか、丸一日なにも食べていないにもかかわらず空腹感はなかった。宝山荘の住人たちは誰からとなく集まってきて、とりあえずアパートまで行ってみようということになった。みんな落ち着いたもんだった。早朝から避難所の電話に並んで、依然として通話が不可能なことも確認していたので、今さらじたばたしても始まらないと思ったからである。また昨夜遅くに団体で避難してきた駅前の高層マンションの住人たちから、テレビやラジオで何が報道されているかを人づてに聞いていたので、自分たちが大体どのような状況におかれているのかも、察しがついていたからである。そのマンションは、かつてはそこに住むことが偉大なステータス・シンボルだったのだが、今では僅かに傾いていた。相変わらずあたりは、もうもうとまき上がるすなけむりと、渦巻くサイレンの音で埋め尽くされていた。私は避難所で失敬してきたスリッパを突っかけて、眼鏡がないのでおぼつかぬ足どりで、砂の積もった通りを宝山荘へ向かった。昨日は生存者の救出のために駆けずり回っていたので、ゆっくりあたりを見回す暇もなかったが、こうして朝の光のなかで宝山荘までの数ブロックを歩いてみただけでも、街の面影がすっかり変わってしまったことが見て取れた。街は満身創痍の状態だった。道路の復旧や、倒壊家屋の処理など、あまりにも現場が多すぎて、全く手のつけようがなかったのである。主要な幹線道路や国道でさえ、使えなくなったところは、やっと通行止めの立て札やバリケードが配置されるようになったばかりだった。ちょっと奥に入った生活道路に至っては、家や塀や電信柱など、ありとあらゆるものが倒れこんで積み重なり、車はおろか歩行者ですら、歩くところがないってんで、ドブん中を這って歩いたものだった。それでも通れないところは、仕方なく道路に崩れ落ちた家の窓から中に入り、お茶漬けをすすっている家族に軽く会釈したあと、ベランダから出て行く始末だった。たしか二階建ての家があったはずだが、生け垣の向こうには空しか見えないところもあった。一階の駐車場に鎮座した高級外車の上から、覆い被さるように座り込んでしまった邸宅もあった。立派な石垣や植え込みが通り一面に散乱し、その奥の真っ白な家の壁が無残にも崩れ落ちて、もはや単なる土砂木屑の山となってしまったところもそこかしこに見られた。一階を改装したばかりのクリーニング屋は、前のめりにくずおれて二階が通りに転がり、預かりものの立派なドレスやスーツが土砂にまみれて散乱していた。東西に走る通りでは、並んで立っていた家々が揃って東に向かって倒れたために、東の端の家がまるごと通りに飛び出してばらばらになっていた。それはもう、倒壊というより破壊だった。どれが壁でどれが床なのかわからず、通りを埋め尽くした夥しい木切れや瓦や壁土の海のなかに、家具とおぼしき部屋の内容物が散らばっていた。あとから聞いた話だが、そこで寝ていた女性は結局上から押し潰されることがなかったために、無事アスファルトの上で目を覚ましたそうである。一瞬のことで、目覚める前に家が破壊されたからだった。正直言って、恐怖を感じる暇もなくこうなってしまったというのが、われわれの一致した実感である。こうして町を歩きながら、冬の穏やかな光の中で、われわれは一瞬のうちにあたりを一変させてしまった自然の猛威をかみしめていた。もはやあたりには、電信柱をはじめまっすぐ立っているものはなく、道路でさえぐにゃぐにゃだった。老人たちはそんな街を見ていくにつれて、次第に気分が悪くなってきたと言って、次々と避難所に引き返す始末だった。

通りは人であふれていた。家が倒壊してしまったので入るところがなかったからである。頑固で有名だったかどの歯医者のおやじは、やり場のない怒りを治療機具にぶつけて、二階のものを一階に、一階のものを二階にぶつぶつ言いながらあわただしく運んでいた。その二階の治療室は、壁いっぱいに開かれた大きな窓が自慢で、彼はさんさんと降りそそぐ太陽の光のなかで、せっせと治療に励んだものである。どこか気むづかしい、教育者めいたところのある人だったが、その朴訥とした性格が気に入っていたのでよく診てもらいに行った。そのとなりは内科医院だった。厳格な雰囲気の、学者じみたその父は数年前に他界していて、どこか皇室の人じみた、おっとりとした雰囲気のある息子が跡を継いでいた。ストーブで腕を暖めて注射したり、ステンレスの器から徐ろにピンセットで脱脂綿をつまんだりする、そのいかにも医者らしい仕草と、やはり昭和三十年代に建てられたと思われる木造の診察室や、タイル張りのトイレや洗面所が好きで、ちょっと具合が悪くなっただけでもすぐに駆けつけたものである。しかし今や見るからに力仕事には不向きと思われる彼も、ちっとも似合わないヘルメットとマスク姿で、いかにも不器用そうに重たい内視鏡の装置を運び出そうとしていた。そこから東へ行くと、古くは阪神間の文化人が集ったという古い喫茶店があった。最近ではもう営業しなくなっていたが、確か数回そこで濃いにがいコーヒーを飲んだことがある。店内は深いブルーに彩られ、シュールな絵や沈欝なトーンの素描が壁いっぱいに描かれていた。上品なおばあちゃんがいて、その格調高いアカデミックな雰囲気にもかかわらず、モータウン系のソウル・ミュージックが最近のお気に入りだと言ってしきりにかけてくれた。その喫茶店の建物は、多分そのおばあちゃんの、亡くなった旦那が建てたか改築したのだろう、洋館風のバルコニーやテラスを備えた、ほかではちょっとお目にかかれないヨーロッパ風のサロンを思わせる趣があった。それもかなり傾いているので、程なく取り壊されることになるだろう。その先には行きつけの散髪屋があった。その店舗は木造平屋建てで、コロニアル風の真っ白な外壁が異国情緒を漂わせていた。内部はていねいなタイル仕上げになっていて、本物の大理石でできた豪華な洗面台があった。そのほかの器具や造りつけの設備も良いものが多く、とても居心地のよい、正しい散髪屋だった。しかも、そのおやじは、ごくごく普通の職人肌の、いわゆる真面目な散髪屋のおやじだった。私が、黒人に多く見られるような、頭頂部を僅かに残しサイドを剃り上げて、その境目にくっきりとラインを入れた極短髪という、当時としては突飛なヘアスタイルを要求すると、彼はさまざまな試行錯誤を繰り返しながら、黙ってその要求に応えようとした。内心は、こんな頭はどこぞのチャラチャラした店へでも行ってたのめばよいものをと思っていたに違いない。律儀なおやじは、トップとサイドの境目に、はさみによるていねいなぼかしを入れようと苦心していたのだが、私がその心も知らないで、「ぼかしなんか入れなくても良い」などと言い、でき上がった頭に私が不満げな顔をしたために、何度か店の裏口から外に出さされたことがある。しかし、そのヘアスタイルは二週間に一度は手入れを要したため、私は次第にその店に通うようになり、だんだん私の考えていることがおやじにもわかってもらえるようになった。はじめは難しい顔をしていたおやじも、三ヵ月も通う頃には面白がって私専用の究極のバリカンを新調してくれるまでになった。そして、当時まだあまりやる人のなかったそのヘアスタイルの作り方を極め、すっかり仲良くなって、ここへ来れば黙って座っただけでそのカットをしてもらえると私が言いふらしたために、方々から私のようなうさん臭いミュージシャンがやって来るようになった。その見事な白壁の店も、今や縦横に大きな亀裂が入り、入口の分厚いガラスも割れて中が丸見えだった。倒壊を免れたのはまさに奇跡だった。それは平屋建てだったからだと思われる。このように、ここらあたりは古い住宅街で、下町風の人情に満ちた人が多かったが、全体としては阪神間を代表する高級住宅街の一画に属していた。近所に大きなスーパーが二軒、ちょっと足を延ばせば輸入食材の豊富にそろった店や老舗の写真材料店、うまいコーヒー豆を挽き売りにしてくれる喫茶店や、ホームメイドベーカリーなど、労せずしていろんなものが手にはいる絶好の環境だった。さらに、多くの美術館や私設の博物館、由緒ある喫茶店や教会、緑に覆われた美しい公園が随所にあり、住んでいる人や商売をしている人にも、なんとも知れぬ余裕に満ちた気品が感じられたものである。しかも、アパートの家賃は信じられないほど安く、これまた格安の駐車場を借りることができたので、金を使わずによい環境で暮らすのに、これほど適したところはなかった。しかし、そうした美術館や博物館などは、かけがえのない収蔵品ごとそのほとんどが全壊した。緑の公園も、美しかった小川のほとりも、地底からの絶大な力によってずたずたにされた。要するにこの界隈が持っていた、文化的なものを大切にする、開放的な雰囲気が一瞬にして吹っ飛んでしまった。これも、自然の営みのひとつだったのである。
今は見る影もなくなったとはいえ、かつてはこれほどの条件がそろっていたところだったから、宝山荘は常に満室だった。管理人夫婦は実に仲の良いさばけた性格で、夏の夕暮れなど、連れ立って銭湯へ行く姿がよく見られたものである。亭主は漫画のキャラクターの大きく入ったTシャツやトレーナーが好きで、その茶目っ気たっぷりなルックスが、老人であるにもかかわらずよく似合っていた。最も古い住人は、宝山荘ができてすぐに入居した女性だった。宗教関係者と思われる彼女は独特の雰囲気を漂わせ、住人とはほとんどつきあいがなかったようだが、早くに亭主と死に別れたのか、三十年以上の年月をこのアパートとともに過ごし、もはや誰も塗り替えることのできない最長記録を段突首位で逃げ切った。彼女は体が弱かったためか、救出されたあと療養施設に運ばれた。次に古い人は、見事なまでに健康的に太った中年の女性である。彼女は明るく快活で、ユーモアのセンスに富んでいた。私の古くからの友人がここに住んでいた、数年前のある暑さの厳しい夏の午後のことである。あまりの息苦しさに耐えかねて、その友人と鴬張りの廊下で体を冷やしていたところ、その健康的なまるまるとした顔をほころばせながら、彼女が実に見事なタイミングで、よく冷えたすいかを持ってきてくれたのである。われわれは思わず感動し、このことは、後々まで懐かしい思い出として語り継がれることになる。私が夜の仕事で楽器を車に積み込んでいると、「夜逃げでもするの」と声をかけられた。春に、いかなごの釘煮を作っていると、においをかぎつけてやって来た。気のおけない人なつこさとさばさばした性格や、長年の苦労と豊かな経験と、それらによって研ぎ澄まされた聡明さが、そのまるい体型のなかに見事に結晶していた。ほかにもいろんな住人がいた。新聞配達をしながらプロダンサーをめざす少女。彼女は、われわれのバンドのダンサーだったのだが、揺れが起こったときは、自転車で配達をしながら田んぼの脇の道を事務所へ戻る途中だった。いきなり自転車から振り落とされ、何が起こったのかわからない目の前で、地面そのものが大波となって何度も迫ってくるのを見たと言っている。そこが田んぼの脇だったことが彼女の命を救った。その近辺も、通りを埋め尽くすほどに家々が倒れ込んでいたからである。さらに、共産主義に心酔して、政府転覆の計画を隠密に進めていた青年闘士、接骨院でバイトしながら理学療法士の道を目指す体育会系のにいちゃん、定年退職して隠居生活に入った、山登りと書道が趣味の画家の先生、アパートに三つも部屋を借りて、季節ごとに移動する独り暮しのおばあちゃん、毎晩酔っ払って帰ってきて、便所によく財布を忘れるくせに、自分は高級マンションの管理人をしているという気楽なおっちゃんなど。過去にはさらに落語家の卵、ヘビメタのギタリスト、毎朝早くから起き出して大音響をたてて洗濯をする耳の遠い二人のばあちゃん、なんともお色気たっぷりな芦屋のお嬢さんがほんの気なぐさみに借りていたこともあった。三十年以上をこのアパートとともに過ごした管理人夫婦にとってみれば、いま私が思い出したものの何倍もの住人の記憶が、鮮やかに甦ってきたに違いない。管理人の亭主はたったひと言、その思いを断ち切るように言った。「むごいもんだな。」
 事実、むごいもんだった。宝山荘は見るも無惨に引き裂かれていた。建物はその中央で縦にまっぷたつに割れ、ぱっくりとその口を空に向けて開いていた。一階は当然の事ながら跡形もなく全滅し、わずか数十センチの高さに押し固められていて、そこへ二階の部屋が思い思いの向きで覆い被さっていた。その二階の部屋でさえ、多くは重い瓦屋根によって破壊され、窓枠ごと通りに散らばっているようなありさまだった。私の部屋とその隣は、まだ外側の形が残っていただけましだった。私は、一階の住人を助け出すために叩き壊された、二階の隣の部屋の僅かな隙間からアパートの中に入っていった。自分の部屋の窓際におかれたベッドのあたりをよく見ると、直径三十センチはあろうかというような重い梁が、枕許に落ちかかって敷布団に食い込んでいた。その梁の先には、別の梁や柱に打ちつけてあったと思われるかなり太い釘がむき出しになっていた。あのときそちらのほうへ寝返りでも打っていようものなら、私は間違いなくあの世だった。ちょうど、屋根の中央の一番高いところから連鎖的に崩れはじめた重い屋根瓦が、怒涛のような流れとなって建物をまっぷたつに引き裂き、まず手前の台所や廊下を直撃して地面に沈めたあと、残りが部屋の窓側部分をベッドごと通りに押し出した形になっていた。そんななかで、自分の寝ていたところだけが、まるでゆりかごのように無傷なのを見て、つくづく自分の運の強さを感じた。しかし、私の持っていたものの全てが、今やこの瓦礫の下に埋もれてしまっていた。家具や服などばかりではない。今の私を作り上げてきた全てのもの、自分で書きためたり作りためたりしたもの、要するにこれまでの人生の証となるものが、全てこの土砂の下敷きになっていた。それは気の遠くなるようなことだった。しかし考えてみれば、あと十五分地震が遅かったら、私は廊下側の台所へ出てコーヒーでも沸かしているところだった。そうすれば、引き裂かれた屋根とともに地面の底に叩き付けられ、崩れてきた建物に押し潰されていたに違いない。のみならず、あと十五分地震が遅かったら、少なくとも管理人夫婦と六人の独居老人は、起き出してまず火を使っていただろうから、当然火災となり、押し潰された住人は瓦礫の中で蒸し焼きにされたあげく、今ごろは煤けた骨と化していたことだろう。運よく命ばかりは助かったとしても、これまでの人生の証とやらは、全て焼かれてなにも残らなかったに違いない。まだこうしてそれらがここにあると思えるだけましというものだった。そればかりではない。あと十五分地震が遅かったら、おそらくあたり一面が火の海となり、列車事故、自動車事故など、とてもこんなものでは済まされない大惨事となっていたことだろう。もっと膨大な人の命が失なわれ、膨大な財産と人々の営みの証が消えていったに違いない。あの時刻は、まだ世の中が目覚める直前だった。誰もが夢見心地で、そろそろ起きようか、いやあと五分と、夜明け前の冷たい空気を予感しつつ、暖かい布団の中でまどろんでいた。だからあれだけの被害にとどまったのである。何百年に一回という自然の活動が、誤差十五分というぎりぎりのタイミングを計ったとしか思えなかった。崩れ落ちた建物の頂点に立って見下ろしながら、かび臭い砂だらけの風に吹かれてそんなことを考えていると、柄にもなく背筋が寒くなるのを覚えた。
事実、むごいもんだった。宝山荘は見るも無惨に引き裂かれていた。建物はその中央で縦にまっぷたつに割れ、ぱっくりとその口を空に向けて開いていた。一階は当然の事ながら跡形もなく全滅し、わずか数十センチの高さに押し固められていて、そこへ二階の部屋が思い思いの向きで覆い被さっていた。その二階の部屋でさえ、多くは重い瓦屋根によって破壊され、窓枠ごと通りに散らばっているようなありさまだった。私の部屋とその隣は、まだ外側の形が残っていただけましだった。私は、一階の住人を助け出すために叩き壊された、二階の隣の部屋の僅かな隙間からアパートの中に入っていった。自分の部屋の窓際におかれたベッドのあたりをよく見ると、直径三十センチはあろうかというような重い梁が、枕許に落ちかかって敷布団に食い込んでいた。その梁の先には、別の梁や柱に打ちつけてあったと思われるかなり太い釘がむき出しになっていた。あのときそちらのほうへ寝返りでも打っていようものなら、私は間違いなくあの世だった。ちょうど、屋根の中央の一番高いところから連鎖的に崩れはじめた重い屋根瓦が、怒涛のような流れとなって建物をまっぷたつに引き裂き、まず手前の台所や廊下を直撃して地面に沈めたあと、残りが部屋の窓側部分をベッドごと通りに押し出した形になっていた。そんななかで、自分の寝ていたところだけが、まるでゆりかごのように無傷なのを見て、つくづく自分の運の強さを感じた。しかし、私の持っていたものの全てが、今やこの瓦礫の下に埋もれてしまっていた。家具や服などばかりではない。今の私を作り上げてきた全てのもの、自分で書きためたり作りためたりしたもの、要するにこれまでの人生の証となるものが、全てこの土砂の下敷きになっていた。それは気の遠くなるようなことだった。しかし考えてみれば、あと十五分地震が遅かったら、私は廊下側の台所へ出てコーヒーでも沸かしているところだった。そうすれば、引き裂かれた屋根とともに地面の底に叩き付けられ、崩れてきた建物に押し潰されていたに違いない。のみならず、あと十五分地震が遅かったら、少なくとも管理人夫婦と六人の独居老人は、起き出してまず火を使っていただろうから、当然火災となり、押し潰された住人は瓦礫の中で蒸し焼きにされたあげく、今ごろは煤けた骨と化していたことだろう。運よく命ばかりは助かったとしても、これまでの人生の証とやらは、全て焼かれてなにも残らなかったに違いない。まだこうしてそれらがここにあると思えるだけましというものだった。そればかりではない。あと十五分地震が遅かったら、おそらくあたり一面が火の海となり、列車事故、自動車事故など、とてもこんなものでは済まされない大惨事となっていたことだろう。もっと膨大な人の命が失なわれ、膨大な財産と人々の営みの証が消えていったに違いない。あの時刻は、まだ世の中が目覚める直前だった。誰もが夢見心地で、そろそろ起きようか、いやあと五分と、夜明け前の冷たい空気を予感しつつ、暖かい布団の中でまどろんでいた。だからあれだけの被害にとどまったのである。何百年に一回という自然の活動が、誤差十五分というぎりぎりのタイミングを計ったとしか思えなかった。崩れ落ちた建物の頂点に立って見下ろしながら、かび臭い砂だらけの風に吹かれてそんなことを考えていると、柄にもなく背筋が寒くなるのを覚えた。
 物思いに耽っている暇はなかった。住人のうち若い連中は、二日目の朝から行方不明者の捜索に協力するかたわら、自分の財産の保全のために、絶え間なく続く余震のなかを、崩れ落ちた部屋に勇気を奮い起こして立ち入った。私のほうも、全財産といえばまさに今着ているものだけという状態で、財布や車のキーはおろか、眼鏡や靴までないというありさまだった。上着や靴下にいたっては借り物だった。とにかく眼鏡、これがないとほとんど何もできなかった。私は、崩れた壁や落ちた梁の下にもぐり、手のつけられるところから自分の持ち物を出しはじめようとした。とはいっても、今やとても部屋とは呼べなくなったこの土砂の山から何か自分のものを見つけ出すには、まずこの空間を埋め尽くした膨大な量の瓦や木材を、いちいち取り除かなければならなかった。柱など大きいものには手がつけられなかったので、小さい木切れから少しずつ掘っては人のいないところに向けて放り投げていった。床がなくなっているので、自分の踏んでいるところも、いつ落ちるかわからない材木のあやふやな積み重なりの上である。ある程度部屋の内容にたどり着くと、懐中電灯で照らしながら壁や柱の間に首を突っ込み、もぐり込んでいった。それでもどこからどうやって迷い込んできたものか、自分のものしかあるはずのない部屋の隅っこから、明らかに自分のものではないものが次々と出てきた。あとで避難所で住人に見せて回ると、ふたつ向こうの部屋のおばちゃんの持ち物だったり、一階の画家の先生の道具だったりした。このようにひとつの空間から、あらゆる部屋のものが出てくるので、自分用と他人用のふたつの籠を拾ってきて、仕分けしながら掘り出さなければならなくなった。途中で何度か人間の救出活動にも呼ばれて加わった。お向かいの全壊した法律事務所の家の奥さんが電話を貸してくれたので、両親やバイト先への電話も試みたが、依然全くの不通状態だった。こうなったら自分が誰かを助けたら、親も誰かに助けられているに違いないと信じるよりほかはなかった。公的な立場で業務に当たっている人は赤リボン、市民のボランティアは黄リボンをつけて走り回っていた。
物思いに耽っている暇はなかった。住人のうち若い連中は、二日目の朝から行方不明者の捜索に協力するかたわら、自分の財産の保全のために、絶え間なく続く余震のなかを、崩れ落ちた部屋に勇気を奮い起こして立ち入った。私のほうも、全財産といえばまさに今着ているものだけという状態で、財布や車のキーはおろか、眼鏡や靴までないというありさまだった。上着や靴下にいたっては借り物だった。とにかく眼鏡、これがないとほとんど何もできなかった。私は、崩れた壁や落ちた梁の下にもぐり、手のつけられるところから自分の持ち物を出しはじめようとした。とはいっても、今やとても部屋とは呼べなくなったこの土砂の山から何か自分のものを見つけ出すには、まずこの空間を埋め尽くした膨大な量の瓦や木材を、いちいち取り除かなければならなかった。柱など大きいものには手がつけられなかったので、小さい木切れから少しずつ掘っては人のいないところに向けて放り投げていった。床がなくなっているので、自分の踏んでいるところも、いつ落ちるかわからない材木のあやふやな積み重なりの上である。ある程度部屋の内容にたどり着くと、懐中電灯で照らしながら壁や柱の間に首を突っ込み、もぐり込んでいった。それでもどこからどうやって迷い込んできたものか、自分のものしかあるはずのない部屋の隅っこから、明らかに自分のものではないものが次々と出てきた。あとで避難所で住人に見せて回ると、ふたつ向こうの部屋のおばちゃんの持ち物だったり、一階の画家の先生の道具だったりした。このようにひとつの空間から、あらゆる部屋のものが出てくるので、自分用と他人用のふたつの籠を拾ってきて、仕分けしながら掘り出さなければならなくなった。途中で何度か人間の救出活動にも呼ばれて加わった。お向かいの全壊した法律事務所の家の奥さんが電話を貸してくれたので、両親やバイト先への電話も試みたが、依然全くの不通状態だった。こうなったら自分が誰かを助けたら、親も誰かに助けられているに違いないと信じるよりほかはなかった。公的な立場で業務に当たっている人は赤リボン、市民のボランティアは黄リボンをつけて走り回っていた。
近くの全壊した一戸建住宅から遺体を二体収容して通りに出たとき、バンドのメンバーが、何人かアパートの前に来ていた。テレビやラジオでこちら方面の惨状を知り、古い宝山荘はまず駄目だろうと思って、念のためにと黒っぽい服を着て、白い花まで持ってくる手回しの良さだった。つい三日前に練習で会ったばかりなのに、とても久しぶりのような気がした。そこでいろいろ具体的な情報を得た。東隣の市との境を流れる大きな川の向こう側はたいした被害がないこと。被害はここから西の神戸方面に行くほど激しく広がっていて、震源地はさらに西の、くにうみの神話にまつわる島の北端に近い、とある海峡であること。彼等は宝山荘の北側で崩れ落ちた高架鉄道の一つ東の駅から、一時間近くをかけてここまで歩いてきたこと。その駅が、東方からこちらへ入る交通機関の最前線になっていて、列車はそこで折り返し運転をしていること。ほかの鉄道はもっとずたずたで、大阪市内でさえ、地下鉄の一部や高速道路が止まっているということなど、人命救助と財産の保全に没頭するあまり、自分のおかれている状況について何も知らない私に、彼等は口々に教え諭すように情報を与えてくれた。なかでも震源地の位置が心配だった。というのも、そこには地震の前夜に赤い月を見た、あのベーシストが住んでいるところだったからである。ここでこんなに壊滅しているんだから、震源地の近くはさぞかしだろうと、われわれは最悪の事態を予想した。しかし、その時点では確たる情報もなく、そんなところまで歩いて行くことなど考えられないことだった。しばらく通りでそんな時間を過ごしたあと、彼等はほかのメンバーや友人を尋ねて去ってゆき、私は再び瓦礫の中にもぐり込んでいった。一回目の捜索で、私がメインに使っていたコンタックスのカメラセットと眼鏡が出てきた。それはまさに奇跡というよりほかはない。隣の家の通路からアパートの一階の廊下の部分が見通せたので、柵越しに傘の柄をつっこんで手当りしだいにまさぐっていたら、ウエストポーチに入ったカメラのセットが引っかかってきたのである。喜び勇んでそれを表の植木にくくりつけ、今度は通りの側から室内を探索していると、砂にまみれた畳の上をまさぐっていたその手に、眼鏡の華奢なフレームが当たったのである。もうレンズは駄目だろうと思って引き上げてみると、なんと無傷だった。ああ、とりあえずこれでいい、これで物もはっきり見えるし、現状をフィルムに収めておくこともできる。何だかとても落ち着いた気分になった。バケツに川の水を入れて運んでいた近所のおばちゃんに、眼鏡を洗うためにひとすくいの水を求めた。ほぼ一日半ぶりにすっきりと物を見渡すことができた。続いて六百本を超えるテープコレクションの一部が箱ごと出てきた。これには、過去に私が行なった二度にわたるザイール旅行での、日本にふたつとない現地録音の一部が含まれていた。次にラジカセ、こいつは役に立つだろう。電池も入れてあったので、スイッチを入れてみたら生きていた。そのあと日没までに、ベッドの近辺に散乱したレコードと若干の書物、楽器類の一部、何着かのスーツを引きずり出した。その日は肉体的にも精神的にもそれくらいが限界だった。荷物は両手で辛うじて持てるだけのもの、しかも足場の悪い瓦礫や丸太の架け橋をこえ、バランスを崩さずに傾いた鉄のベランダを持って降りられるだけの量に限られていた。また、いつ次の大きな余震が来るかわからなかったので、せっかく助かったのに自分の財産に未練を残したばっかりに、再び瓦礫の下敷きになって果てたんではしゃれにもならんからである。事実、部屋の中の抜き差しならぬ柱や壁の下にもぐり込んでいたときに、大きな地響きを上げて強い余震が襲ってきたことがあった。再び崩れ落ちてきた瓦や木屑の中に危うく埋りそうになり、あたふたと通りに転がり出てへたり込んでしまうていたらくだった。
 そんなこともあって、この日はとにかく命だけは助かったのだから、あまり持ち物に執着を感じるとろくなことにならないと思って捜索を中止した。自分はいったん無一文になったのだから、今日の最小限で重要な収穫だけでも満足しなければならないと自分に言い聞かせ、そうして持ち出してきたものは、置く場所がないので、止むを得ず道端に並べてボロきれをかぶせておいた。夕方に避難所へ戻ると、瓦礫から掘り起こしたもので自分のものではないものを、籠ごと住人たちに見せて回った。そのうちのかなりの数が、本来の持主の手許へ帰っていった。そのあと、管理人がとっておいてくれた配給のおにぎりを食べた。それは、ほぼ二日ぶりの食事だった。そして、地震後はじめて新聞を読んだ。この地震二日目の夕刊が、正式な情報に接する実に初めての機会だった。地震からこのかた、われわれは何の情報も与えられずに、ただ目の前に埋っている人を掘り起こし、自分の財産が失なわれないように気を揉んでいた。携帯ラジオを持ち出せた人もいなかったし、新聞などやっては来なかった。正直なところ、ただならぬ事態だとは思っていたが、いったい世間でどういうことが起こって、周りや遠くはどうなっているのか、風のうわさ以外に知る術はなかったのである。それでも上空を耐えずマスコミのものと思われるヘリが行き来し、不安をあおった。彼等の責任ではないが、彼等はどんどん持ち出すばかりで、われわれには何一つ与えてはくれなかった。やっとのことでありついた新聞によると、友人達の話の通り、広大な範囲に被害が及んでいた。広い範囲で火災に見舞われた西方の地区、ここからすぐ近所の四十五度に傾いたマンション、横倒しになった高速道路、ビルまでがひっくりかえった神戸の中心部。大伸ばしにされた写真を見るたびに息をのんだ。「なんだこれは、これじゃあまるで街ごとなくなったもおんなじじゃないか」沿岸部の主要なベルト地帯が幅二キロ、長さ三十キロにもわたって完璧にやられていた。そこには、いくつもの救出劇や脱出の顛末が記されていた。その後のいろいろな人々の体験談も併せて考えると、いかに気丈な人間がそばに多くいたかということや、いかに近所の人たちとつながりがあったかということ、さらに、そのときどれだけ声を張り上げて自分の所在を周囲に知らせることができたかが、人の生命を左右したことを思い知らされた。それは実のある話だった。ここにいるみんなが、実際にそうやって出て来たからである。それに対して、その時点で発表されていた犠牲者や負傷者、倒壊した建物の数などは、少なすぎて話にもならなかった。「宝山荘の前の通り一本であれだけ死んでるんだぞ。こんなもんじゃない。」二日たつのに当局の状況把握がいかに出来ていないか、いかに情報が混乱しているのかを如実に物語っていた。しかし今から思うに、市や県や、果ては国などが、状況把握に時間がかかったからといっても、あの状態では決して責められるものではない。最も早くから救助活動をしていた当のわれわれでさえ、熟知しているはずの近所の状況ですら、正しく把握していたわけではなかったからである。かえって渦中のわれわれよりも、周辺部に住んでいたあのバンドのメンバーたちのほうが、状況を的確に把握していたくらいだった。ここへ来る途中で、延べにして何十人もの人を助け出していたからである。千里眼をもった人間が何人もいたのならいざ知らず、所詮ただの人間のやることだから、この広大で複雑な災害の全体を混乱なく把握することなど、物理的に不可能な話だった。災害そのものがとてつもなく大きすぎたのである。新聞の下半分を使って大きく載せられた大阪の百貨店の広告がわれわれの神経を逆なでした。「被災された皆様に心からお見舞申し上げます」と書いてあるその横で、それで死んだかも知れない人間がごまんといるというのに、倒れてきたらいかにも痛そうな立派な家具の写真を掲載して、大売り出しを宣伝していたからである。
そんなこともあって、この日はとにかく命だけは助かったのだから、あまり持ち物に執着を感じるとろくなことにならないと思って捜索を中止した。自分はいったん無一文になったのだから、今日の最小限で重要な収穫だけでも満足しなければならないと自分に言い聞かせ、そうして持ち出してきたものは、置く場所がないので、止むを得ず道端に並べてボロきれをかぶせておいた。夕方に避難所へ戻ると、瓦礫から掘り起こしたもので自分のものではないものを、籠ごと住人たちに見せて回った。そのうちのかなりの数が、本来の持主の手許へ帰っていった。そのあと、管理人がとっておいてくれた配給のおにぎりを食べた。それは、ほぼ二日ぶりの食事だった。そして、地震後はじめて新聞を読んだ。この地震二日目の夕刊が、正式な情報に接する実に初めての機会だった。地震からこのかた、われわれは何の情報も与えられずに、ただ目の前に埋っている人を掘り起こし、自分の財産が失なわれないように気を揉んでいた。携帯ラジオを持ち出せた人もいなかったし、新聞などやっては来なかった。正直なところ、ただならぬ事態だとは思っていたが、いったい世間でどういうことが起こって、周りや遠くはどうなっているのか、風のうわさ以外に知る術はなかったのである。それでも上空を耐えずマスコミのものと思われるヘリが行き来し、不安をあおった。彼等の責任ではないが、彼等はどんどん持ち出すばかりで、われわれには何一つ与えてはくれなかった。やっとのことでありついた新聞によると、友人達の話の通り、広大な範囲に被害が及んでいた。広い範囲で火災に見舞われた西方の地区、ここからすぐ近所の四十五度に傾いたマンション、横倒しになった高速道路、ビルまでがひっくりかえった神戸の中心部。大伸ばしにされた写真を見るたびに息をのんだ。「なんだこれは、これじゃあまるで街ごとなくなったもおんなじじゃないか」沿岸部の主要なベルト地帯が幅二キロ、長さ三十キロにもわたって完璧にやられていた。そこには、いくつもの救出劇や脱出の顛末が記されていた。その後のいろいろな人々の体験談も併せて考えると、いかに気丈な人間がそばに多くいたかということや、いかに近所の人たちとつながりがあったかということ、さらに、そのときどれだけ声を張り上げて自分の所在を周囲に知らせることができたかが、人の生命を左右したことを思い知らされた。それは実のある話だった。ここにいるみんなが、実際にそうやって出て来たからである。それに対して、その時点で発表されていた犠牲者や負傷者、倒壊した建物の数などは、少なすぎて話にもならなかった。「宝山荘の前の通り一本であれだけ死んでるんだぞ。こんなもんじゃない。」二日たつのに当局の状況把握がいかに出来ていないか、いかに情報が混乱しているのかを如実に物語っていた。しかし今から思うに、市や県や、果ては国などが、状況把握に時間がかかったからといっても、あの状態では決して責められるものではない。最も早くから救助活動をしていた当のわれわれでさえ、熟知しているはずの近所の状況ですら、正しく把握していたわけではなかったからである。かえって渦中のわれわれよりも、周辺部に住んでいたあのバンドのメンバーたちのほうが、状況を的確に把握していたくらいだった。ここへ来る途中で、延べにして何十人もの人を助け出していたからである。千里眼をもった人間が何人もいたのならいざ知らず、所詮ただの人間のやることだから、この広大で複雑な災害の全体を混乱なく把握することなど、物理的に不可能な話だった。災害そのものがとてつもなく大きすぎたのである。新聞の下半分を使って大きく載せられた大阪の百貨店の広告がわれわれの神経を逆なでした。「被災された皆様に心からお見舞申し上げます」と書いてあるその横で、それで死んだかも知れない人間がごまんといるというのに、倒れてきたらいかにも痛そうな立派な家具の写真を掲載して、大売り出しを宣伝していたからである。
避難所では、相変わらず行方不明者を問い合わせるアナウンスが大音響で響きわたっていた。避難者たちは、もうずいぶん慣れたよと笑っていたが、なんとも騒然とした緊張感だけはどうしようもなかった。こうした緊張感から少しでも逃れたいのだろう、老人を中心に断定的にものを言う人の話を鵜呑みにして、そこからなんともばかばかしいデマが流れる兆しが、早くもみえはじめていた。「この地震は南海地震の前兆である、今度はもっと大きい奴が今世紀中にはやって来る、その震度は8ぐらいになるだろうから、今のうちに北へ逃げる段取りをしておいたほうがいい。」などと顔を紅潮させてまくしたてている初老のうさん臭い男に、不安げな顔つきのばあさんが何人も膝を進めてはうなずいていた。 「明朝五時四十六分に最大級の余震が来る。」初めはわれわれも笑って取り合わなかったが、「地震の発生時刻に夜間が多いのは何故だと思う、それは月の引力が関係しているからだ。」という話には、それはそうかも知れないなと思った。私のいた教室には段ボールでいくつも服や食器を持ち込み、あきれたことに吠えかかる犬まで持ち込んだ人もいるというのに、ラジオを持ってきた人がひとりもいなかった。私は瓦礫から掘り起こしたラジカセを出してきて、必要なときにいつでも使ってくださいと周りの人に伝えたが、結局そこが閉鎖されるまで誰ひとりとしてそれに触れる者はなかった。そのくせ明け方になると、余震が来る余震が来ると言って、座布団をかぶってひとを踏みつけながら教室の真ん中にいざりより、ぶるぶるふるえて動こうとしない老人たちを見たとき、私はもはや何を言う気も失くしてしまった。似たようなことはまだあった。その夜、この寒いのに避難所でも最も寒い玄関の下駄箱の横で震えている青年がいた。何故よりによって扉の開閉や人通りの多い、寒風の吹きすさぶその場所を選んだのか全く理解できなかったが、唇の色がなかったので一緒に教室まで来るように勧めた。いくら教室に人が多いといってもひとりやふたり入れんことはないと思ったからである。しかし彼は、教室は人がいっぱいで自分が行くと迷惑になると言った。それは違うだろうと少し問答になったが、あまり頑固なのでやめてしまった。翌日、同じ場所でじっとうずくまっている青ざめた彼を何度も見かけた。やれやれ、元気に働く体力と冷静な判断のできる頭脳を持っているはずの若い連中でさえそういうのが少なくなかった。その夜遅くに、近所でボヤがあったと放送された。その町名はどのへんかと尋ねる人がいたので、いつも私が行くあの散髪屋のある町だと答えたところ、翌朝にはそれがどう伝わったのか、その散髪屋が火事を出したという話になってしまい、おやじがかんかんになって怒っていた。「わしの店は見事な白壁が自慢だ。その壁の白さは今だってすこしもくすんじゃいない。・・・ちょっとひびが入ってるだけだ。」このようにして、避難所で三日目の朝を迎えたのだが、所内の自治体制や住民間のルールづくり、連絡体制や名簿づくりなどは徐々に整備され、その頃には驚くほどきちんと運用されていた。外来者が尋ねてきても、いれば必ず会うことができたし、外出している人への伝言も確実に伝えられるようになっていた。これは大したもんだった。あとで私はほかの地域の避難所へもよく顔を出すようになったのだが、たいていは自治組織など機能していないのか、名簿などという気の利いたものはなく、情報をとりまとめる窓口もなく、乱雑に壁に貼り出された何百枚という紙切れに全部目を通さないと、捜し求める人がそこにいるのかいないのかさえわからない状態だった。多くの避難所は、全体が殺伐とした厳しい雰囲気に包まれていた。何人もの人が尋ね人にめぐりあえず、ほかの避難所がどこにあるのかさえわからないので、不案内な道を通りかかる人に尋ねながら、疲れ切った表情で立ち去る姿が見られたものである。
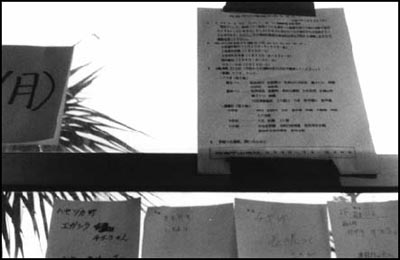 しかし、ルールがいかに確立したとはいっても、食糧や生活用水など、ないものは依然としてなかった。始まったばかりの配給のおにぎりは、氷のように冷たくて固かったし、初めの頃は熱いお茶でさえ手に入らなかった。避難所に据え付けられた電話器もその頃にはかなり増設され、長い時間並ぶこともなくなったが、依然として不通状態が続いていたため、並んだ人の多くは徒労に終わった。これからどうなるのだろう、救出活動も一段落し、崩れ落ちた建物の周りに、なにするということなく集まってきた人々からそんな声が聞かれた。なんとか立っている家の人でさえ、粉々になった食器や家具を片付けなければならないことはわかり切っていたが、多くの人はとてもそんな気にはなれなかった。どうせまた潰されるという思いのほうが強かったからである。「こんなでかい地震、来るんやったら来るで、なんで一声かけてからにしてくれへんかったんや。」今日は燃えないごみの日だったが、それを思い出した人が一体どれだけいただろう。目の前が、いわばもう使い物にならない巨大なごみの山だった。こんなに膨大なごみをどうやって片付けるのだろうか、なんとも気の遠くなるような話だった。倒壊した高架鉄道の北側にあったスーパーは、建物の損壊のため、駐車場に建てた仮設テントに生活必需品のみを拾い集めて業務を再開した。しかし営業時間も大幅に限定され、夜になると寒さのなかでたき火にあたりながら寝ずの番をする、顔見知りの店員の姿が見られたものである。毎日閉店後に行われる恐怖のくじびきが、店員のその夜の運命を決めるのだった。山の手の別の大型スーパーでは、建物の損傷がひどいため、地下のピロティ部分でのごく小規模な営業となっていた。本来なら着飾った客でごった返すはずの店内は、ジャージやスポーツウェア姿の客ばかりで、人がいるのに異様に静まり返っていた。電気は来ていたが、節電のため、BGMも空調も止まっていたからである。避難した住民たちは、まずは自分たちがその日食うものの確保でほぼ手一杯だった。余力のある若い連中は、忙しい人や手の足りない人を助けたり、自分たちの財産の保全に忙しかった。商売をしている人は、店と自宅と避難所の間を、多くは自転車やバイクで、さらに手のこんだ人は、緊急車両と大書した横断幕を前面に張り付けた車で走り回っていた。復旧への草の根の第一歩が始まっていた。それは荒っぽい、どさくさまぎれのサバイバルゲームの様相を呈していたが、それは致し方のないことだった。より一層、気丈な人間が物事を有利に運べる状況が強まっていったのである。お向かいの法律事務所のおやじさんも、どこからか軽トラックを借りてきて「緊急車両」と大書していた。「なにかまうもんか、みなさんの大切な土地や建物を管理しとるんだ。」彼の行動は驚くほど素早かった。三日目にしてすでに新しい事務所兼住居用の物件を押さえていた。の話によると、もう阪神間はおろか、大阪やその周辺部の主だった賃貸物件は、すでに大企業によって従業員の避難用にほとんど押さえられてしまっているとのことだった。「今のうちになんとかしておかないと、本当に住むところがなくなってしまうぞ。」
しかし、ルールがいかに確立したとはいっても、食糧や生活用水など、ないものは依然としてなかった。始まったばかりの配給のおにぎりは、氷のように冷たくて固かったし、初めの頃は熱いお茶でさえ手に入らなかった。避難所に据え付けられた電話器もその頃にはかなり増設され、長い時間並ぶこともなくなったが、依然として不通状態が続いていたため、並んだ人の多くは徒労に終わった。これからどうなるのだろう、救出活動も一段落し、崩れ落ちた建物の周りに、なにするということなく集まってきた人々からそんな声が聞かれた。なんとか立っている家の人でさえ、粉々になった食器や家具を片付けなければならないことはわかり切っていたが、多くの人はとてもそんな気にはなれなかった。どうせまた潰されるという思いのほうが強かったからである。「こんなでかい地震、来るんやったら来るで、なんで一声かけてからにしてくれへんかったんや。」今日は燃えないごみの日だったが、それを思い出した人が一体どれだけいただろう。目の前が、いわばもう使い物にならない巨大なごみの山だった。こんなに膨大なごみをどうやって片付けるのだろうか、なんとも気の遠くなるような話だった。倒壊した高架鉄道の北側にあったスーパーは、建物の損壊のため、駐車場に建てた仮設テントに生活必需品のみを拾い集めて業務を再開した。しかし営業時間も大幅に限定され、夜になると寒さのなかでたき火にあたりながら寝ずの番をする、顔見知りの店員の姿が見られたものである。毎日閉店後に行われる恐怖のくじびきが、店員のその夜の運命を決めるのだった。山の手の別の大型スーパーでは、建物の損傷がひどいため、地下のピロティ部分でのごく小規模な営業となっていた。本来なら着飾った客でごった返すはずの店内は、ジャージやスポーツウェア姿の客ばかりで、人がいるのに異様に静まり返っていた。電気は来ていたが、節電のため、BGMも空調も止まっていたからである。避難した住民たちは、まずは自分たちがその日食うものの確保でほぼ手一杯だった。余力のある若い連中は、忙しい人や手の足りない人を助けたり、自分たちの財産の保全に忙しかった。商売をしている人は、店と自宅と避難所の間を、多くは自転車やバイクで、さらに手のこんだ人は、緊急車両と大書した横断幕を前面に張り付けた車で走り回っていた。復旧への草の根の第一歩が始まっていた。それは荒っぽい、どさくさまぎれのサバイバルゲームの様相を呈していたが、それは致し方のないことだった。より一層、気丈な人間が物事を有利に運べる状況が強まっていったのである。お向かいの法律事務所のおやじさんも、どこからか軽トラックを借りてきて「緊急車両」と大書していた。「なにかまうもんか、みなさんの大切な土地や建物を管理しとるんだ。」彼の行動は驚くほど素早かった。三日目にしてすでに新しい事務所兼住居用の物件を押さえていた。の話によると、もう阪神間はおろか、大阪やその周辺部の主だった賃貸物件は、すでに大企業によって従業員の避難用にほとんど押さえられてしまっているとのことだった。「今のうちになんとかしておかないと、本当に住むところがなくなってしまうぞ。」
< font size="2"> しかし住民の多くは、これから住むところの心配はおろか、今まで住んでいたところのことでさえ、気持ちの整理などついていなかった。特に全壊した木造の集合住宅の人々にとっては、崩れ果てたわが家のありさまに呆然とするばかりで、車を持っている人でさえ、自分が車で動くことなど全くぴんとこなかった。私でさえそのときはじめて自分の車のことを思い出し、あわてて駐車場へ走って見に行ったほどである。青空駐車場だったのが幸いして車は無傷だった。しかし、整然と並んでいるはずの車は、駐車場のなかでごったがえしていた。なかには真ん中の通路を通り越して向かい側の車の列に危うく接触しかかっているものもあった。広い駐車場は全体が波打ち、ところどころに地割れができていた。キーさえあれば、荷台にとりあえず自分の荷物を積むことだってできたのだが、どうしようもないのでそこをあとにし、近所の様子を見ながらアパートへ戻った。ボヤをだしたと噂された散髪屋のおやじは、崩れかけた店から器具を運び出していた。声をかけると、少し笑って力無く肩をすくめると、割れた分厚いガラスのドアの向こうに消えていった。途中、早くも他府県ナンバーの、明らかに見物に来たとわかるアベックの乗ったスポーツカーを見かけた。彼等のもの珍しそうな目つきは、どうしても一部の住民の神経を逆なでしたに違いない。砂だらけの風のなか、誰もが薄汚れた服を着て肩を落としてうろつき回っているというのに、美しく光り輝くその赤い車は、いかにも場所に不相応に見えたからである。その日は、午前中に芦屋の老舗の写真材料店で手に入れた、古いライカのボディが見つかった。それは本棚と柱に挟まれ、さらに上から壁がのしかかっていたのでびくともしなかった。おまけに壁土にまみれていた。それを見たとき、思わず涙がこぼれそうになったが、露出していた巻き上げノブをチリチリとまわし、シャッターを切ってみると、「シャッ」という確かな音がした。その音で私は我に返った。太い木を捜してきてテコの原理でゆっくりと柱を浮かせ、救出にとりかかった。本棚の側板が割れたものの、何度めかの試みでそれをうまく引きずり出すことができた。砂にまみれているとはいえ、小さくてずっしりと重いその感触は、私に勇気を与えてくれた。それに気をよくして、私はずんずん掘り進んでいった。それに従って色々なものが姿を現わした。柱や梁が硬く壁に食い込んだ柵の向こうに、恩師ブレッソンのフォトポートレートやその他の高価な写真集、ザイールの奥地で私の命を救ったひとりの木こりがプレゼントしてくれた木彫の人形、愛用のマッキントッシュの本体とバックアップのフロッピーのケースなどが見えた。さらに崩れ落ちた押入の下に、十年ほど前に三宮でバーをやっていたジャマイカ系アイルランド黒人が譲ってくれた古いコンガや、近くのホールで買い換えのために処分されかかっていたのを格安で買い上げたドラムセットなどが見えた。しかし、それらは見えていても柱や壁が重たくのしかかって、一人の力ではびくともしない複雑な格子の向こうになっていた。
font size="2"> しかし住民の多くは、これから住むところの心配はおろか、今まで住んでいたところのことでさえ、気持ちの整理などついていなかった。特に全壊した木造の集合住宅の人々にとっては、崩れ果てたわが家のありさまに呆然とするばかりで、車を持っている人でさえ、自分が車で動くことなど全くぴんとこなかった。私でさえそのときはじめて自分の車のことを思い出し、あわてて駐車場へ走って見に行ったほどである。青空駐車場だったのが幸いして車は無傷だった。しかし、整然と並んでいるはずの車は、駐車場のなかでごったがえしていた。なかには真ん中の通路を通り越して向かい側の車の列に危うく接触しかかっているものもあった。広い駐車場は全体が波打ち、ところどころに地割れができていた。キーさえあれば、荷台にとりあえず自分の荷物を積むことだってできたのだが、どうしようもないのでそこをあとにし、近所の様子を見ながらアパートへ戻った。ボヤをだしたと噂された散髪屋のおやじは、崩れかけた店から器具を運び出していた。声をかけると、少し笑って力無く肩をすくめると、割れた分厚いガラスのドアの向こうに消えていった。途中、早くも他府県ナンバーの、明らかに見物に来たとわかるアベックの乗ったスポーツカーを見かけた。彼等のもの珍しそうな目つきは、どうしても一部の住民の神経を逆なでしたに違いない。砂だらけの風のなか、誰もが薄汚れた服を着て肩を落としてうろつき回っているというのに、美しく光り輝くその赤い車は、いかにも場所に不相応に見えたからである。その日は、午前中に芦屋の老舗の写真材料店で手に入れた、古いライカのボディが見つかった。それは本棚と柱に挟まれ、さらに上から壁がのしかかっていたのでびくともしなかった。おまけに壁土にまみれていた。それを見たとき、思わず涙がこぼれそうになったが、露出していた巻き上げノブをチリチリとまわし、シャッターを切ってみると、「シャッ」という確かな音がした。その音で私は我に返った。太い木を捜してきてテコの原理でゆっくりと柱を浮かせ、救出にとりかかった。本棚の側板が割れたものの、何度めかの試みでそれをうまく引きずり出すことができた。砂にまみれているとはいえ、小さくてずっしりと重いその感触は、私に勇気を与えてくれた。それに気をよくして、私はずんずん掘り進んでいった。それに従って色々なものが姿を現わした。柱や梁が硬く壁に食い込んだ柵の向こうに、恩師ブレッソンのフォトポートレートやその他の高価な写真集、ザイールの奥地で私の命を救ったひとりの木こりがプレゼントしてくれた木彫の人形、愛用のマッキントッシュの本体とバックアップのフロッピーのケースなどが見えた。さらに崩れ落ちた押入の下に、十年ほど前に三宮でバーをやっていたジャマイカ系アイルランド黒人が譲ってくれた古いコンガや、近くのホールで買い換えのために処分されかかっていたのを格安で買い上げたドラムセットなどが見えた。しかし、それらは見えていても柱や壁が重たくのしかかって、一人の力ではびくともしない複雑な格子の向こうになっていた。
昼過ぎになって私は捜索を一時中断し、昨日出てきたコンタックスのセットを持って街の状況を撮影して回ることにした。捜索の過程で、フィルムが何本か転がり出てきたからである。まず宝山荘の破壊状況を克明に記録した。これは後日何かの役に立つだろうという考えからだった。次に落橋した高架鉄道のねじれ落ちたレールを、そして駅へ行き、そこに立ち往生していた電車を撮った。その下り電車はホームに到着した直後だったのだろう、からくも手前の落橋した高架に巻き込まれるのを免れていた。電車の来なくなったレールの上を、夥しい人が歩いて来る。その向こうに危うく鉄路に落ちかかりそうになったマンションが見えた。駅前のスーパーのある大きな建物に入った。非常照明だけの店内は当然どこも閉まったままで、死んだように静まりかえっていた。その建物の周囲も地割れがひどく、地面には砂やガラスが積もっていた。そこを出て小川の両岸の激しい地割れを撮った。その川に架かる橋もいくつか落ちていた。さらに南下して、新聞にも報道された四十五度に傾いたマンションや、東西に走る国道の猛烈な渋滞、そこに群がるバイクと歩行者と自転車の流れ、橋げたが落下した高速道路の周辺など、手持ちのフィルムがなくなるまで撮った。無論、近辺でフィルムなど何処にも売ってはいなかった。とりあえず溜まっていた欲求を全部吐き出してしまうと再びアパートに戻り、今度は落下した二階の廊下と一階の壁に挟まれていた自転車の救出を試みた。この自転車は、二十五年ほど前に自分でパーツを選んで組み立てた、当時スポルティフと呼ばれていた古いスタイルのものである。ほとんど諦めていたのだが、意外と挟まっていた場所からうまくはずれた。それを落ちていた縄で上のベランダまでつり上げ、脚立を使って慎重に柵の外に担ぎ降ろした。ハンドルステムのネジが緩んでいただけで、乗ってみてもクランクやペダルを含めて奇跡的に歪みひとつなかった。愛着もあり、もう二度と作れない規格のものだけに、喜びもひとしおだった。

そのようにして、その日は概ね宝山荘の前にいた。住人のなかには知り合いのところに身を寄せている人や、その後の連絡が途絶えている人もいたし、付近の住民の安否を尋ねてくる人や、自衛隊や警察の事情聴取があったりで、なにかとしなければならないことが多かったからである。一方、老人たちはほぼ一日中、避難所で寝ていた。救援物資や義援金の募集が叫ばれ、避難所の運営を手伝いに来た、穏やかな笑みを絶やさぬボランティアの若い連中をちらほら見かけだしたのもこの頃である。自衛隊の給水活動が始まり、家屋の全壊で入れ物を持ち出せなかったので、ペット・ボトルや小さな鍋を持った人が、何時間もの長蛇の列を作ったのもこの頃である。近隣の商店やスーパーもそろそろ開店しはじめていたが、シャッターを開けるが早いか品物が売り切れた。静かで混乱こそないが、明らかに不安心理から発したパニックが徐々に始まっていた。私はそんな状況を横目で見ながら、自分はまだ持ちこたえられると判断していた。そんなふうに争って水や食料を我勝ちに確保しなくても死にはしない、状況が変わったんだから、この期に及んで今まで通りの生活を維持しようとしても所詮無駄なことだと考えていた。ここ数日を乗り切れば、あとは少し落ち着いてくるだろう、かなり遠いところから人も来ているようなので、本当に必要なときが来れば脱出することもできるはずだと考えていた。その前にやっておかねばならんことがいっぱいある、今は何時間も行列に並んでいる場合ではない。私の場合、あの部屋の下敷きになっているものを、できるだけ多く救い出すことのほうが先決だった。こうしてその日以降、自分の財産をひとつでも多く救出しようとする執念の炎を徐々に燃えたぎらせていった私は、ほぼ一ヵ月にわたって、行政の対応の遅れから瓦礫が放置されているのをいいことに、はじめはそこらで調達したヘルメットや綿入れのツナギに身をつつみ、しまいにはつるはしやバールで武装して、今ではたんなる瓦礫の山と化した宝山荘の中を、文字どおり寝食を忘れて飽くことなく這いずり回ることになる。
 この頃から、自衛隊の捜索の主眼は行方不明者の救出から犠牲者の収容に移り、高架鉄道の北側からオリーブ色の制服姿の自衛隊員が、頭まですっぽりと毛布をかけられた遺体を畳に乗せて運ぶ姿が頻繁に見られるようになった。上空を爆音をたてて飛んで来るヘリコプターの数も増えた。地上では依然四方八方がサイレンとクラクションの騒音の渦で、まるで街全体が唸りを上げているかのようだった。瓦礫の砂が舞上げられて、風景全体が黄色く濁って見えた。この緊張感のみなぎる騒然とした空気のおかげで、ここがついおとといまで安楽に暮らしていた同じ場所とはとても思えなかった。舌がざらつく。絶えずガスと瓦礫の臭気が鼻をつく。ふと顔に手をやると、砂でざらざらだった。瓦礫との戦いは、この砂との戦いでもあった。西のほうから夥しい人の群れが目の前を通りすぎるようになった。彼等は、宝山荘の北側で落橋した鉄道の折り返し地点を目指して、何十キロという道のりを、遥か西方の土地から、はるばる歩いてきたのである。毛布にくるまっていたり、乳母車を押していたり、誰も彼もがじっとりと重い、疲れた雰囲気をたたえていた。なかには代八車に家財一式と思われるほど荷物を積んで転がしている男たちもいたが、多くは身一つか軽装だった。そのなかに、火災の激しかった西の方の地域から一日中歩き通しだという老人がいた。東へ行ってどうするのかと聞くと、とりあえずあてはないが、出てきたところよりはましだろうと言うので、手持ちの水を渡して、ここらで避難所へもぐり込んでみたらと勧めた。というのも、ここから東へ行くと被害が軽くなり、避難所もまばらになるだろうと思ったからである。行列は夕方になるにしたがって増え、夜になっても衰える気配はなかった。逆に東から西へ、大きなリュックをかついだ人の行列が流れていくのが見られはじめた。周辺地域からのお見舞いや、救援のボランティアの始まりである。西へ向かう人は、東へ逃げる人と違って、服装もこぎれいで快活だった。中には派手に崩れた鉄道の高架をバックに記念写真を撮る人まであった。そんな人の流れは、宝山荘の前ばかりでなく、少し南側の国道から、はるか南方の海岸部を走る幹線道路までの通りという通りを埋め尽くしていたのである。まさに、民族の大移動といった様相を呈していた。その流れに乗って、西からバンドのメンバーのひとりが嫁さんとともにやってきた。自宅が全壊してしまったので、なんとか電車に乗って川向こうへ行くつもりだと言う。一緒に行こうと勧められたが、私はここでもう少しやりたいことがあるのでまた今度にすると答えた。翌日、その友人は自宅のあとかたづけに戻る途中、私のために食料や飲料と、荷物を運ぶための折り畳み式のキャリアを持って来てくれた。私はそれをありがたく受け取り、昼過ぎに再び彼が帰りがけにここを訪れたとき、まとめられるだけの重要な荷物をまとめて彼と同行することにした。瓦礫の山から引きずり出して、通りに積み上げられていた私の持ち物が、ただならぬ量になってきたからである。先の見通しは全く立たなかったが、いざとなれば素手ででも全部運んでやる覚悟だった。さらに、彼が川向こうは本当に何事もなかったかのように正常に動いていると、何度も力説したからである。私はそれをにわかには信じられなかったが、もし本当ならそれを見てみたかった。「こんなところにいつまでもいられるわけがない」と、彼は私を強く促した。
この頃から、自衛隊の捜索の主眼は行方不明者の救出から犠牲者の収容に移り、高架鉄道の北側からオリーブ色の制服姿の自衛隊員が、頭まですっぽりと毛布をかけられた遺体を畳に乗せて運ぶ姿が頻繁に見られるようになった。上空を爆音をたてて飛んで来るヘリコプターの数も増えた。地上では依然四方八方がサイレンとクラクションの騒音の渦で、まるで街全体が唸りを上げているかのようだった。瓦礫の砂が舞上げられて、風景全体が黄色く濁って見えた。この緊張感のみなぎる騒然とした空気のおかげで、ここがついおとといまで安楽に暮らしていた同じ場所とはとても思えなかった。舌がざらつく。絶えずガスと瓦礫の臭気が鼻をつく。ふと顔に手をやると、砂でざらざらだった。瓦礫との戦いは、この砂との戦いでもあった。西のほうから夥しい人の群れが目の前を通りすぎるようになった。彼等は、宝山荘の北側で落橋した鉄道の折り返し地点を目指して、何十キロという道のりを、遥か西方の土地から、はるばる歩いてきたのである。毛布にくるまっていたり、乳母車を押していたり、誰も彼もがじっとりと重い、疲れた雰囲気をたたえていた。なかには代八車に家財一式と思われるほど荷物を積んで転がしている男たちもいたが、多くは身一つか軽装だった。そのなかに、火災の激しかった西の方の地域から一日中歩き通しだという老人がいた。東へ行ってどうするのかと聞くと、とりあえずあてはないが、出てきたところよりはましだろうと言うので、手持ちの水を渡して、ここらで避難所へもぐり込んでみたらと勧めた。というのも、ここから東へ行くと被害が軽くなり、避難所もまばらになるだろうと思ったからである。行列は夕方になるにしたがって増え、夜になっても衰える気配はなかった。逆に東から西へ、大きなリュックをかついだ人の行列が流れていくのが見られはじめた。周辺地域からのお見舞いや、救援のボランティアの始まりである。西へ向かう人は、東へ逃げる人と違って、服装もこぎれいで快活だった。中には派手に崩れた鉄道の高架をバックに記念写真を撮る人まであった。そんな人の流れは、宝山荘の前ばかりでなく、少し南側の国道から、はるか南方の海岸部を走る幹線道路までの通りという通りを埋め尽くしていたのである。まさに、民族の大移動といった様相を呈していた。その流れに乗って、西からバンドのメンバーのひとりが嫁さんとともにやってきた。自宅が全壊してしまったので、なんとか電車に乗って川向こうへ行くつもりだと言う。一緒に行こうと勧められたが、私はここでもう少しやりたいことがあるのでまた今度にすると答えた。翌日、その友人は自宅のあとかたづけに戻る途中、私のために食料や飲料と、荷物を運ぶための折り畳み式のキャリアを持って来てくれた。私はそれをありがたく受け取り、昼過ぎに再び彼が帰りがけにここを訪れたとき、まとめられるだけの重要な荷物をまとめて彼と同行することにした。瓦礫の山から引きずり出して、通りに積み上げられていた私の持ち物が、ただならぬ量になってきたからである。先の見通しは全く立たなかったが、いざとなれば素手ででも全部運んでやる覚悟だった。さらに、彼が川向こうは本当に何事もなかったかのように正常に動いていると、何度も力説したからである。私はそれをにわかには信じられなかったが、もし本当ならそれを見てみたかった。「こんなところにいつまでもいられるわけがない」と、彼は私を強く促した。
 私は、使えそうな段ボールをいくつも拾ってきて、大事なものから順に詰めてゆき、キャリアに縛りつけて出発した。避難所に外出先を伝言し、アパートの住人に声をかけて、東へ向かう行列に加わった。われわれは、瓦礫に塞がれた通りを迂回しようとして右往左往する人々をやりすごし、なんとか一本通っている道をみつけて進んだ。人々の服装は、ほぼ例外なくスポーツ・ウェアかジャージ姿で、大きなリュックを背負っていたり、荷物を満載したキャリアを引いていたりした。京都へ延びる古い街道筋に並行する国道までは、だいたい宝山荘のあたりと同じで、木造家屋のほとんどが全壊していた。四日たって、いくらかこの光景が見慣れたものになったとはいっても、それはやはり悲惨な眺めだった。見慣れた街並みがほとんど崩れ去り、鉄筋コンクリートの建物でさえ、大きく傾いているものが多かった。ところが不思議なことに、その街道を越えると急にあたりの様子が一変した。なにか、街並みが目にすっきりと整然としたものになったのである。もちろん瓦が落ちていたり、壁が剥がれていたりはするのだが、まっすぐなものはだいたいまっすぐに建っていた。建物の破壊の程度が比較にならないほど軽かったのである。これは不思議な現象だった。その後あちこちで、全く無傷な家並みの真ん中に突然ずたずたになった区画がかたまって出現したり、通り一本をはさんだ街の両側の様子がありありと違うという光景を何度も目にした。あとになって、それは地震波の屈折と集中が主な原因だという報道を聞いた。広い道はどこも例外なく車であふれ返り、それらは猛烈な渋滞のためにぴくりとも動かなかった。脇道や路地から人が通りに溢れ出していた。人々は瓦礫で埋め尽くされた歩道を避けて、車道の動かぬ車の間にまで入り込み、そのせまい隙間でひしめき合っていた。そこへ自衛隊の装甲車やトラックやバスがけたたましいサイレンを鳴り響かせながら何台も編隊を組んで押し寄せ、道を譲ろうとする車が夥しい歩行者の列に突っ込んだために叫び声が上がったりした。堂々たるいかつい面構えで、道をあけなさいとがなりながら進んでくるその姿に、いかな黒塗のベンツといえども、圧倒されてしぶしぶ道を譲った。しかし、自分を追い越していく救急車に追従することは、決して忘れなかった。自衛隊の双発ヘリコプターが何機も下腹に応えるほどの爆音を轟かせて上空を飛び去って行った。「戒厳令とはこんなもんだろうな。」友人に話しかけたその声も届かなかった。そんななか、お祭り騒ぎと勘違いしたのか、または食べ物屋の少ない状況のなかで、すこしでも暖かい食事をというボランティア精神の現われか、はたまたどんなときにも商売を忘れぬ浪速商人のど根性か、実に様々な屋台がちょっと前の十日戎さながらに、幹線道路に繰り広げられていたのには目を見張ってしまった。乗用車いっぱいに菓子パンを積んで一個二百円均一で売っているうさん臭い二人連れの男がいた。一個三千円もするヤキイモ屋が現われた。「いらっしゃいいらっしゃい」という威勢のいいかけ声も、通りの騒音にかき消されがちだったが、子供に与える風船やヨーヨー釣りまでやっていたのには恐れ入った。タクシーを降りた婦人が料金をめぐって運転手とやりあっていた。バイクの兄ちゃんが大きなリュックを背負った男と値段の交渉をしていた。 粗末な机を持ち出して、携帯電話を無料貸出ししているコーナーがあったが、これは今後の顧客拡大を狙ったものだったのだろう。しかし後日、携帯電話からは、一一九番にシステム上繋がらないことになっていることが大々的に報じられたり、また復興に名を借りた様々なビジネスに悪用されたり、解約についてのユーザーへの説明が不十分だったりして、はからずもその欠点を広く世に知らしめる結果となってしまった。たいていがこのどさくさに、他人の足許を見透かしたような商売をする輩どもだったが、もちろん、そんなわるいやつらばかりではなかった。駅前のあるスーパーの店頭では、なんと幕の内弁当が暖かい味噌汁つきでたったの百円で売られていた。無料といわれると何だかプライドを傷つけられたような気がするが、百円というその絶妙の値段設定にちょっと心が動きそうになった。しかしぐっとこらえてその場をやりすごした。また、街の角という角には、付近の地図をコピーして現在地を示し、不案内な訪問者に便宜をはかったり、さらには、その地図のコピーを無料配布しているところがあちこちにあった。さらに、飲料や食料、訪問者がうっかり忘れてきそうな被災地での生活必需品を並べて売っているところもあった。政治的には犬猿の仲の隣どうしのふたつの国が、対立を越えて互いの援助を申し出る貼紙も見られた。そんなこんなで、道中は結構物見遊山の状態だった。とはいっても、やはり誰もが気忙しいのか、店に立ち寄る人はまばらだった。のみならずこのへんまで来ると、あちこちからこの駅を目指してきた人たちで道路は道幅いっぱいに埋め尽くされ、とても店の前まで行ったり、足を止めたりできるような状態ではなかった。
私は、使えそうな段ボールをいくつも拾ってきて、大事なものから順に詰めてゆき、キャリアに縛りつけて出発した。避難所に外出先を伝言し、アパートの住人に声をかけて、東へ向かう行列に加わった。われわれは、瓦礫に塞がれた通りを迂回しようとして右往左往する人々をやりすごし、なんとか一本通っている道をみつけて進んだ。人々の服装は、ほぼ例外なくスポーツ・ウェアかジャージ姿で、大きなリュックを背負っていたり、荷物を満載したキャリアを引いていたりした。京都へ延びる古い街道筋に並行する国道までは、だいたい宝山荘のあたりと同じで、木造家屋のほとんどが全壊していた。四日たって、いくらかこの光景が見慣れたものになったとはいっても、それはやはり悲惨な眺めだった。見慣れた街並みがほとんど崩れ去り、鉄筋コンクリートの建物でさえ、大きく傾いているものが多かった。ところが不思議なことに、その街道を越えると急にあたりの様子が一変した。なにか、街並みが目にすっきりと整然としたものになったのである。もちろん瓦が落ちていたり、壁が剥がれていたりはするのだが、まっすぐなものはだいたいまっすぐに建っていた。建物の破壊の程度が比較にならないほど軽かったのである。これは不思議な現象だった。その後あちこちで、全く無傷な家並みの真ん中に突然ずたずたになった区画がかたまって出現したり、通り一本をはさんだ街の両側の様子がありありと違うという光景を何度も目にした。あとになって、それは地震波の屈折と集中が主な原因だという報道を聞いた。広い道はどこも例外なく車であふれ返り、それらは猛烈な渋滞のためにぴくりとも動かなかった。脇道や路地から人が通りに溢れ出していた。人々は瓦礫で埋め尽くされた歩道を避けて、車道の動かぬ車の間にまで入り込み、そのせまい隙間でひしめき合っていた。そこへ自衛隊の装甲車やトラックやバスがけたたましいサイレンを鳴り響かせながら何台も編隊を組んで押し寄せ、道を譲ろうとする車が夥しい歩行者の列に突っ込んだために叫び声が上がったりした。堂々たるいかつい面構えで、道をあけなさいとがなりながら進んでくるその姿に、いかな黒塗のベンツといえども、圧倒されてしぶしぶ道を譲った。しかし、自分を追い越していく救急車に追従することは、決して忘れなかった。自衛隊の双発ヘリコプターが何機も下腹に応えるほどの爆音を轟かせて上空を飛び去って行った。「戒厳令とはこんなもんだろうな。」友人に話しかけたその声も届かなかった。そんななか、お祭り騒ぎと勘違いしたのか、または食べ物屋の少ない状況のなかで、すこしでも暖かい食事をというボランティア精神の現われか、はたまたどんなときにも商売を忘れぬ浪速商人のど根性か、実に様々な屋台がちょっと前の十日戎さながらに、幹線道路に繰り広げられていたのには目を見張ってしまった。乗用車いっぱいに菓子パンを積んで一個二百円均一で売っているうさん臭い二人連れの男がいた。一個三千円もするヤキイモ屋が現われた。「いらっしゃいいらっしゃい」という威勢のいいかけ声も、通りの騒音にかき消されがちだったが、子供に与える風船やヨーヨー釣りまでやっていたのには恐れ入った。タクシーを降りた婦人が料金をめぐって運転手とやりあっていた。バイクの兄ちゃんが大きなリュックを背負った男と値段の交渉をしていた。 粗末な机を持ち出して、携帯電話を無料貸出ししているコーナーがあったが、これは今後の顧客拡大を狙ったものだったのだろう。しかし後日、携帯電話からは、一一九番にシステム上繋がらないことになっていることが大々的に報じられたり、また復興に名を借りた様々なビジネスに悪用されたり、解約についてのユーザーへの説明が不十分だったりして、はからずもその欠点を広く世に知らしめる結果となってしまった。たいていがこのどさくさに、他人の足許を見透かしたような商売をする輩どもだったが、もちろん、そんなわるいやつらばかりではなかった。駅前のあるスーパーの店頭では、なんと幕の内弁当が暖かい味噌汁つきでたったの百円で売られていた。無料といわれると何だかプライドを傷つけられたような気がするが、百円というその絶妙の値段設定にちょっと心が動きそうになった。しかしぐっとこらえてその場をやりすごした。また、街の角という角には、付近の地図をコピーして現在地を示し、不案内な訪問者に便宜をはかったり、さらには、その地図のコピーを無料配布しているところがあちこちにあった。さらに、飲料や食料、訪問者がうっかり忘れてきそうな被災地での生活必需品を並べて売っているところもあった。政治的には犬猿の仲の隣どうしのふたつの国が、対立を越えて互いの援助を申し出る貼紙も見られた。そんなこんなで、道中は結構物見遊山の状態だった。とはいっても、やはり誰もが気忙しいのか、店に立ち寄る人はまばらだった。のみならずこのへんまで来ると、あちこちからこの駅を目指してきた人たちで道路は道幅いっぱいに埋め尽くされ、とても店の前まで行ったり、足を止めたりできるような状態ではなかった。
駅前広場に通じる最後の角を曲がったときに行進はぴたりと止まり、入場制限による何時間もの長い膠着状態に陥った。広場は行列の整理のためにロープで迷路が作られていて、それに沿って何分かに何歩かずつ、今は懐かしき社会党の牛歩戦術もかくやと思われるほどのペースで進まされた。全く身動きのとれない人ごみの中で喘ぎながら、今この瞬間にわれわれに向かって無差別発砲が行なわれたら、逃げ場を失なった群衆はなす術もなくこの場に折り重なり、間違いなくわれわれの生存の事実はかき消されることだろうなどと想像した。駅まで行けば便所の一つもあると期待していた人も多かったが、駅前の公衆便所はおろか、近所の無傷だった商店の便所でさえ、排水ができないために使用禁止になっていた。仮設トイレなどはまだ作られていなかった頃のことだから、なかには汚ないどぶ川に降りて用を足す若い女性の姿も見られたほどである。座ることもできない気の遠くなるような時間がなすすべもなく過ぎて、やっと構内に入り、さらに延々と並んで切符を買い、改札を抜け、構内に張り巡らされたいくつもの迷路を通り抜けてホームに達したとき、もうすでに出発してから四時間近くが経過していた。退屈さと足腰の痛みに我を忘れかけていたが、見慣れた電車が入ってきたときにはなんとも言い知れぬ感動を覚えたものである。その電車は、車庫で屋根に損傷を受けたのか、パンタグラフの一つがもげていた。 さすがに窓にぶら下がったり、屋根によじのぼったりする人は一人もいなかったが、乗り込みの瞬間はホーム全体に緊張が走った。そして乗った電車が動きだし、聞き慣れた懐かしいリズミカルな振動が始まったとき、長い幽閉生活に耐えて何年振りかで沙婆へ出ていくような、なんとも言えない郷愁のようなものを感じたものである。やがて電車は、東隣の市との境を流れる大きな川を渡りはじめた。西の方に大きく六甲の山並みが見渡せた。それは、新春の霞に包まれた、実に穏やかな眺めだった。その時、川岸の夕陽の中で犬を散歩させているひとりの男の姿が目に入った。犬はあちこちの木にマーキングしながら、主人のまわりをはねまわっていた。私はその光景に思わず釘付けになってしまった。川を越えると、確かに友人たちが言っていたように風景が一変した。正常な街並みが目の前に広がったのである。しかし、地盤が不安定だったためか、電車は常に徐行運転を続けていた。その重々しい足どりは、外の明るい風景とは対照的に、非常に不気味な響きとなって、今も私の記憶に鮮明に残っている。われわれはふたつ目の駅でその電車を降りた。
改札を出て愕然とした。駅前には煌々と電燈が灯り、魚屋や八百屋などはおろか、あろうことかハンバーガー屋や喫茶店まで、何事もなかったかのように平常通り営業していたからである。アーケードには賑やかな音楽まで流れていた。まるで初めて都会に出てきた田舎もん状態だった。「喫茶店だぞ。」十キロと隔れてはいないはずだった。しかしそこはまるで別世界だった。それを見たとたん、私の緊張の糸は、ぷっつりと切れてしまった。こんなに近くに、何不自由のないいつもの生活があったとは・・・。ここでは、ごく普通の買い物時間で、あたりまえの物が買えるのだ。この世の終わりなんかではなかった。にぎりめし一個を手にいれるのにも、水や防寒具を手に入れるにも、いちいち何時間も並ぶ必要なんかない。はるか遠方から人々が差し入れを背負って延々と歩いて来ることもない。「川を渡れば、いくらでも物が手に入るぞ。」その一言で、自転車やバイクで買い出しに出る者がいくらでもいたはずである。ほとんどの人が、特に老人たちはこれを知らされていないのだ。東から来たボランティアの若いのも、こんな事は教えてくれなかったし、テレビやラジオもこのことには触れなかった。もっと西のほうは別として、少なくとも川向こうの奴らは何をぼやぼやしているんだろう。この事実を知っているのか。何時間も行列に並ばせるより、もっと先にすべきことがあったのである。物資が手にはいる情報をもっと流し、動ける奴は外へ出て物資の調達に従事し、それで浮いた分をもっと深刻なところへ回すべきだったのである。そこまで考えたとたん、私は二度と避難所で寝る気をなくしてしまった。少なくとも、私のいた近辺の避難所は、自分たちで炊き出しでもやろうと思えばやれる環境が整っていた。
目的地のメンバーの家へ行った。なんと彼は仕事に出ていた。嫁さんの話によると、彼は昨日から通常業務に戻っているという。川ひとつ越えた向こうは毎日が水の確保、食料の調達という、実に原始的な生活の手だてに窮々として、とても仕事どころではないというのに。私は呆気にとられてしまった。そしてその家で、私は地震以来はじめてテレビを見た。それはまるで、刺激のきつい娯楽映画のように見えた。火災現場や家屋の倒壊現場、避難所の現状などが映し出され、「あそこも燃えていますここも燃えています。」と、ヒステリックなアナウンサーの金切り声が聞こえ、「今一番したいことはなんですか。」と、毛布をかぶった老人にマイクを突きつけるレポーターの姿があった。その映像から受ける印象は、その同じ風景から出て来た私にとっても、悲惨きわまりないものに見えた。この映像を見て、私の友人たちも慌てて私を見舞いに来たのに違いなかった。両親と仕事先にも難無く電話が通じた。母は電話口で泣いて喜んだ。私の実家は山の手にあって無事だった。父も母も怪我ひとつなかったらしい。とりあえず安心した。仕事先でも私を心配してくれていたが、案の定、私の仕事は全て中止となり、現状の報告とできるだけ早期の出社、各得意先の状況の把握を指示された。ここは全てが平常通りだった。何だか悪い夢を見せられているような気分だった。ようやく人心地つきはじめた頃、仕事からここの主が帰ってきた。ほどなくバンドの若手のギタリストから電話がはいった。彼は大阪で仕事をしていたのだが、仕事仲間がまるで地震なんか他人事みたいな口のきき方をするので、ぶん殴りたくなったといきまいていた。「おいおい、そんなに力があり余ってるのなら・・・」ということで、翌日は彼に加勢してもらって、財産の更なる捜索をすることにした。暖かい食事と風呂を勧められて久しぶりに満足感に浸っていると、「やっと笑いが戻ったな。」と言われてしまった。
homepage> earthquake> 前ページへ | 次ページへ
 「高級アパート宝山荘」は、昭和三十年代に建てられた実に瀟酒なアパートだった。それが建っていたのは、六甲山から流れ出る、桜の名所としても名高いある小川の近くである。当時はまだアパートで暮らすのは贅沢なことだとされていたので、建物の内部にはその時代の気品を感じさせるような造作が随所に見られた。建物の基礎がおかれていた位置は地面より七十センチほど高く、これは過去にこの付近一帯を襲った大水害のさいには威力を発揮した。さらにそこから数段上がると、薄く切った石を並べたポーチになっており、タイル張りの二本の柱に支えられた庇がついていた。この二本の柱は、家主や管理人までもがコンクリートの無垢だと思っていたのに、倒れたあと切り口を見てみると、芯は木材で、しかも白蟻が食ってぼろぼろになっていた。そこを入ると、盆栽や観葉植物の飾られたタイル張りの玄関になっていて、一枚岩の御影石の上がりかまちがあった。全体として温泉旅館を思わせる風情があって、玄関で靴を脱ぎ、ずらりと並んだ部屋番号つきの下駄箱に各自靴を入れ、スリッパにはきかえて上がるのである。木造二階建て、中央に廊下があって両側に部屋が並ぶという、典型的な昭和のアパートの造りであった。その廊下は歩くと音のするところから、住人たちから鴬張りの廊下と呼ばれていた。それは管理人が実にきれい好きで、毎日よくもまあ続くもんだと誰もが感心するぐらい念の入った掃除をしたため、廊下は常にぴかぴか、木材のきしむ音と磨き上げられた表面でスリッパのこすれる音が、微妙なハーモニーを奏でていた。その掃除の仕方とは、通り一遍のはたきがけと掃きそうじのあと、水に濡らして細かくちぎった新聞紙を固く絞って廊下中にふり撒き、それをほうきで掃き集めるという古色蒼然としたものだった。毎朝亭主を送り出してから、せわしないもの音をたてて一階から掃除が始まり、人が寝ていようがなにしてようがお構いなしに、廊下側の窓をばんばんはたくので、おかげで病気のときも仮病のときも、二日酔いのときも徹夜仕事を終えてようやく眠りに落ちかけたときも、こちらの都合には全くおかまいなしに、毎日決まった時刻に文字通り叩き起こされる羽目になった。 しかしその超人的な、飽くことのないたゆまぬ努力のおかげで、住人たちから二百年のときを超えたほまれ高きその名をいただくことになったのである。その廊下は地震のおかげで真っ先に地面に没してしまったけれども、その光沢は、自分の財産の保全のために若い連中が夜っぴて瓦礫と化したアパートの底をほじくりかえしていたときにも、その手許を下からそっと照らして財産のありかを指し示してやるほどだった。その廊下の北側の突き当たりには、二階に上がる階段があり、その前に金だらいがよく似合うタイル張りの洗面所があった。各部屋にも流しがあったが、その洗面所はとても共同住宅臭くて、寒い冬の朝など、なんとも知れぬ情緒を漂わせていたものである。階段の裏手は共同の便所になっていて、最近になって水洗化された。その天井には大きなまるい電球カバーがあって、それがまた昔の夜汽車の客室のような暖かい光をやさしく投げかけていた。それとならんで、すでに物置となって久しい共同の風呂場があったが、これもタイル張りでまるい天井を持っていた。階段を上がるとちょっとした踊り場があり、そこの窓からは、暮れなずむ夕焼けに浮かぶ教会の尖塔が、シルエットとなって眺められたものである。上がりきった二階にも大体同じような洗面所と便所があって、非常階段のついた古い木製のベランダがあった。これら住人が共同で利用する各部所には、管理人直筆の注意書がそこかしこに貼られてあった。カイダンノノボリオリハシズカニ、ゴミハキマッタヒニダシマセウ、ベンキニタバコヲステルナ、セイリノカミハクズカゴニステマセウ、微に入り際に入ったその文句はなんとも忘れられないものだった。各部屋は、手前が三畳弱の台所のついた板の間で、奥が四畳半の畳の間だった。窓は出窓になっていて大きく、その下に便利な戸袋までついていた。私の部屋は二階の南端の東側にあって、その廊下の突き当たりには、われわれが真っ先に脱出した例の鉄の階段のついたベランダがあった。はじめて不動産屋とともにこのアパートを訪れたとき、窓が大きいためか全体として明るい印象を受けたことを覚えている。私はかわいらしいこの部屋が一発で気に入り、その場で契約書にはんこを押した。しかし美しく見えたこの大きな窓が壁の強度を損なう結果となり、一階の部屋を跡形もなく押し潰すことになろうとは、夢にも思わなかった。
「高級アパート宝山荘」は、昭和三十年代に建てられた実に瀟酒なアパートだった。それが建っていたのは、六甲山から流れ出る、桜の名所としても名高いある小川の近くである。当時はまだアパートで暮らすのは贅沢なことだとされていたので、建物の内部にはその時代の気品を感じさせるような造作が随所に見られた。建物の基礎がおかれていた位置は地面より七十センチほど高く、これは過去にこの付近一帯を襲った大水害のさいには威力を発揮した。さらにそこから数段上がると、薄く切った石を並べたポーチになっており、タイル張りの二本の柱に支えられた庇がついていた。この二本の柱は、家主や管理人までもがコンクリートの無垢だと思っていたのに、倒れたあと切り口を見てみると、芯は木材で、しかも白蟻が食ってぼろぼろになっていた。そこを入ると、盆栽や観葉植物の飾られたタイル張りの玄関になっていて、一枚岩の御影石の上がりかまちがあった。全体として温泉旅館を思わせる風情があって、玄関で靴を脱ぎ、ずらりと並んだ部屋番号つきの下駄箱に各自靴を入れ、スリッパにはきかえて上がるのである。木造二階建て、中央に廊下があって両側に部屋が並ぶという、典型的な昭和のアパートの造りであった。その廊下は歩くと音のするところから、住人たちから鴬張りの廊下と呼ばれていた。それは管理人が実にきれい好きで、毎日よくもまあ続くもんだと誰もが感心するぐらい念の入った掃除をしたため、廊下は常にぴかぴか、木材のきしむ音と磨き上げられた表面でスリッパのこすれる音が、微妙なハーモニーを奏でていた。その掃除の仕方とは、通り一遍のはたきがけと掃きそうじのあと、水に濡らして細かくちぎった新聞紙を固く絞って廊下中にふり撒き、それをほうきで掃き集めるという古色蒼然としたものだった。毎朝亭主を送り出してから、せわしないもの音をたてて一階から掃除が始まり、人が寝ていようがなにしてようがお構いなしに、廊下側の窓をばんばんはたくので、おかげで病気のときも仮病のときも、二日酔いのときも徹夜仕事を終えてようやく眠りに落ちかけたときも、こちらの都合には全くおかまいなしに、毎日決まった時刻に文字通り叩き起こされる羽目になった。 しかしその超人的な、飽くことのないたゆまぬ努力のおかげで、住人たちから二百年のときを超えたほまれ高きその名をいただくことになったのである。その廊下は地震のおかげで真っ先に地面に没してしまったけれども、その光沢は、自分の財産の保全のために若い連中が夜っぴて瓦礫と化したアパートの底をほじくりかえしていたときにも、その手許を下からそっと照らして財産のありかを指し示してやるほどだった。その廊下の北側の突き当たりには、二階に上がる階段があり、その前に金だらいがよく似合うタイル張りの洗面所があった。各部屋にも流しがあったが、その洗面所はとても共同住宅臭くて、寒い冬の朝など、なんとも知れぬ情緒を漂わせていたものである。階段の裏手は共同の便所になっていて、最近になって水洗化された。その天井には大きなまるい電球カバーがあって、それがまた昔の夜汽車の客室のような暖かい光をやさしく投げかけていた。それとならんで、すでに物置となって久しい共同の風呂場があったが、これもタイル張りでまるい天井を持っていた。階段を上がるとちょっとした踊り場があり、そこの窓からは、暮れなずむ夕焼けに浮かぶ教会の尖塔が、シルエットとなって眺められたものである。上がりきった二階にも大体同じような洗面所と便所があって、非常階段のついた古い木製のベランダがあった。これら住人が共同で利用する各部所には、管理人直筆の注意書がそこかしこに貼られてあった。カイダンノノボリオリハシズカニ、ゴミハキマッタヒニダシマセウ、ベンキニタバコヲステルナ、セイリノカミハクズカゴニステマセウ、微に入り際に入ったその文句はなんとも忘れられないものだった。各部屋は、手前が三畳弱の台所のついた板の間で、奥が四畳半の畳の間だった。窓は出窓になっていて大きく、その下に便利な戸袋までついていた。私の部屋は二階の南端の東側にあって、その廊下の突き当たりには、われわれが真っ先に脱出した例の鉄の階段のついたベランダがあった。はじめて不動産屋とともにこのアパートを訪れたとき、窓が大きいためか全体として明るい印象を受けたことを覚えている。私はかわいらしいこの部屋が一発で気に入り、その場で契約書にはんこを押した。しかし美しく見えたこの大きな窓が壁の強度を損なう結果となり、一階の部屋を跡形もなく押し潰すことになろうとは、夢にも思わなかった。 


 事実、むごいもんだった。宝山荘は見るも無惨に引き裂かれていた。建物はその中央で縦にまっぷたつに割れ、ぱっくりとその口を空に向けて開いていた。一階は当然の事ながら跡形もなく全滅し、わずか数十センチの高さに押し固められていて、そこへ二階の部屋が思い思いの向きで覆い被さっていた。その二階の部屋でさえ、多くは重い瓦屋根によって破壊され、窓枠ごと通りに散らばっているようなありさまだった。私の部屋とその隣は、まだ外側の形が残っていただけましだった。私は、一階の住人を助け出すために叩き壊された、二階の隣の部屋の僅かな隙間からアパートの中に入っていった。自分の部屋の窓際におかれたベッドのあたりをよく見ると、直径三十センチはあろうかというような重い梁が、枕許に落ちかかって敷布団に食い込んでいた。その梁の先には、別の梁や柱に打ちつけてあったと思われるかなり太い釘がむき出しになっていた。あのときそちらのほうへ寝返りでも打っていようものなら、私は間違いなくあの世だった。ちょうど、屋根の中央の一番高いところから連鎖的に崩れはじめた重い屋根瓦が、怒涛のような流れとなって建物をまっぷたつに引き裂き、まず手前の台所や廊下を直撃して地面に沈めたあと、残りが部屋の窓側部分をベッドごと通りに押し出した形になっていた。そんななかで、自分の寝ていたところだけが、まるでゆりかごのように無傷なのを見て、つくづく自分の運の強さを感じた。しかし、私の持っていたものの全てが、今やこの瓦礫の下に埋もれてしまっていた。家具や服などばかりではない。今の私を作り上げてきた全てのもの、自分で書きためたり作りためたりしたもの、要するにこれまでの人生の証となるものが、全てこの土砂の下敷きになっていた。それは気の遠くなるようなことだった。しかし考えてみれば、あと十五分地震が遅かったら、私は廊下側の台所へ出てコーヒーでも沸かしているところだった。そうすれば、引き裂かれた屋根とともに地面の底に叩き付けられ、崩れてきた建物に押し潰されていたに違いない。のみならず、あと十五分地震が遅かったら、少なくとも管理人夫婦と六人の独居老人は、起き出してまず火を使っていただろうから、当然火災となり、押し潰された住人は瓦礫の中で蒸し焼きにされたあげく、今ごろは煤けた骨と化していたことだろう。運よく命ばかりは助かったとしても、これまでの人生の証とやらは、全て焼かれてなにも残らなかったに違いない。まだこうしてそれらがここにあると思えるだけましというものだった。そればかりではない。あと十五分地震が遅かったら、おそらくあたり一面が火の海となり、列車事故、自動車事故など、とてもこんなものでは済まされない大惨事となっていたことだろう。もっと膨大な人の命が失なわれ、膨大な財産と人々の営みの証が消えていったに違いない。あの時刻は、まだ世の中が目覚める直前だった。誰もが夢見心地で、そろそろ起きようか、いやあと五分と、夜明け前の冷たい空気を予感しつつ、暖かい布団の中でまどろんでいた。だからあれだけの被害にとどまったのである。何百年に一回という自然の活動が、誤差十五分というぎりぎりのタイミングを計ったとしか思えなかった。崩れ落ちた建物の頂点に立って見下ろしながら、かび臭い砂だらけの風に吹かれてそんなことを考えていると、柄にもなく背筋が寒くなるのを覚えた。
事実、むごいもんだった。宝山荘は見るも無惨に引き裂かれていた。建物はその中央で縦にまっぷたつに割れ、ぱっくりとその口を空に向けて開いていた。一階は当然の事ながら跡形もなく全滅し、わずか数十センチの高さに押し固められていて、そこへ二階の部屋が思い思いの向きで覆い被さっていた。その二階の部屋でさえ、多くは重い瓦屋根によって破壊され、窓枠ごと通りに散らばっているようなありさまだった。私の部屋とその隣は、まだ外側の形が残っていただけましだった。私は、一階の住人を助け出すために叩き壊された、二階の隣の部屋の僅かな隙間からアパートの中に入っていった。自分の部屋の窓際におかれたベッドのあたりをよく見ると、直径三十センチはあろうかというような重い梁が、枕許に落ちかかって敷布団に食い込んでいた。その梁の先には、別の梁や柱に打ちつけてあったと思われるかなり太い釘がむき出しになっていた。あのときそちらのほうへ寝返りでも打っていようものなら、私は間違いなくあの世だった。ちょうど、屋根の中央の一番高いところから連鎖的に崩れはじめた重い屋根瓦が、怒涛のような流れとなって建物をまっぷたつに引き裂き、まず手前の台所や廊下を直撃して地面に沈めたあと、残りが部屋の窓側部分をベッドごと通りに押し出した形になっていた。そんななかで、自分の寝ていたところだけが、まるでゆりかごのように無傷なのを見て、つくづく自分の運の強さを感じた。しかし、私の持っていたものの全てが、今やこの瓦礫の下に埋もれてしまっていた。家具や服などばかりではない。今の私を作り上げてきた全てのもの、自分で書きためたり作りためたりしたもの、要するにこれまでの人生の証となるものが、全てこの土砂の下敷きになっていた。それは気の遠くなるようなことだった。しかし考えてみれば、あと十五分地震が遅かったら、私は廊下側の台所へ出てコーヒーでも沸かしているところだった。そうすれば、引き裂かれた屋根とともに地面の底に叩き付けられ、崩れてきた建物に押し潰されていたに違いない。のみならず、あと十五分地震が遅かったら、少なくとも管理人夫婦と六人の独居老人は、起き出してまず火を使っていただろうから、当然火災となり、押し潰された住人は瓦礫の中で蒸し焼きにされたあげく、今ごろは煤けた骨と化していたことだろう。運よく命ばかりは助かったとしても、これまでの人生の証とやらは、全て焼かれてなにも残らなかったに違いない。まだこうしてそれらがここにあると思えるだけましというものだった。そればかりではない。あと十五分地震が遅かったら、おそらくあたり一面が火の海となり、列車事故、自動車事故など、とてもこんなものでは済まされない大惨事となっていたことだろう。もっと膨大な人の命が失なわれ、膨大な財産と人々の営みの証が消えていったに違いない。あの時刻は、まだ世の中が目覚める直前だった。誰もが夢見心地で、そろそろ起きようか、いやあと五分と、夜明け前の冷たい空気を予感しつつ、暖かい布団の中でまどろんでいた。だからあれだけの被害にとどまったのである。何百年に一回という自然の活動が、誤差十五分というぎりぎりのタイミングを計ったとしか思えなかった。崩れ落ちた建物の頂点に立って見下ろしながら、かび臭い砂だらけの風に吹かれてそんなことを考えていると、柄にもなく背筋が寒くなるのを覚えた。  物思いに耽っている暇はなかった。住人のうち若い連中は、二日目の朝から行方不明者の捜索に協力するかたわら、自分の財産の保全のために、絶え間なく続く余震のなかを、崩れ落ちた部屋に勇気を奮い起こして立ち入った。私のほうも、全財産といえばまさに今着ているものだけという状態で、財布や車のキーはおろか、眼鏡や靴までないというありさまだった。上着や靴下にいたっては借り物だった。とにかく眼鏡、これがないとほとんど何もできなかった。私は、崩れた壁や落ちた梁の下にもぐり、手のつけられるところから自分の持ち物を出しはじめようとした。とはいっても、今やとても部屋とは呼べなくなったこの土砂の山から何か自分のものを見つけ出すには、まずこの空間を埋め尽くした膨大な量の瓦や木材を、いちいち取り除かなければならなかった。柱など大きいものには手がつけられなかったので、小さい木切れから少しずつ掘っては人のいないところに向けて放り投げていった。床がなくなっているので、自分の踏んでいるところも、いつ落ちるかわからない材木のあやふやな積み重なりの上である。ある程度部屋の内容にたどり着くと、懐中電灯で照らしながら壁や柱の間に首を突っ込み、もぐり込んでいった。それでもどこからどうやって迷い込んできたものか、自分のものしかあるはずのない部屋の隅っこから、明らかに自分のものではないものが次々と出てきた。あとで避難所で住人に見せて回ると、ふたつ向こうの部屋のおばちゃんの持ち物だったり、一階の画家の先生の道具だったりした。このようにひとつの空間から、あらゆる部屋のものが出てくるので、自分用と他人用のふたつの籠を拾ってきて、仕分けしながら掘り出さなければならなくなった。途中で何度か人間の救出活動にも呼ばれて加わった。お向かいの全壊した法律事務所の家の奥さんが電話を貸してくれたので、両親やバイト先への電話も試みたが、依然全くの不通状態だった。こうなったら自分が誰かを助けたら、親も誰かに助けられているに違いないと信じるよりほかはなかった。公的な立場で業務に当たっている人は赤リボン、市民のボランティアは黄リボンをつけて走り回っていた。
物思いに耽っている暇はなかった。住人のうち若い連中は、二日目の朝から行方不明者の捜索に協力するかたわら、自分の財産の保全のために、絶え間なく続く余震のなかを、崩れ落ちた部屋に勇気を奮い起こして立ち入った。私のほうも、全財産といえばまさに今着ているものだけという状態で、財布や車のキーはおろか、眼鏡や靴までないというありさまだった。上着や靴下にいたっては借り物だった。とにかく眼鏡、これがないとほとんど何もできなかった。私は、崩れた壁や落ちた梁の下にもぐり、手のつけられるところから自分の持ち物を出しはじめようとした。とはいっても、今やとても部屋とは呼べなくなったこの土砂の山から何か自分のものを見つけ出すには、まずこの空間を埋め尽くした膨大な量の瓦や木材を、いちいち取り除かなければならなかった。柱など大きいものには手がつけられなかったので、小さい木切れから少しずつ掘っては人のいないところに向けて放り投げていった。床がなくなっているので、自分の踏んでいるところも、いつ落ちるかわからない材木のあやふやな積み重なりの上である。ある程度部屋の内容にたどり着くと、懐中電灯で照らしながら壁や柱の間に首を突っ込み、もぐり込んでいった。それでもどこからどうやって迷い込んできたものか、自分のものしかあるはずのない部屋の隅っこから、明らかに自分のものではないものが次々と出てきた。あとで避難所で住人に見せて回ると、ふたつ向こうの部屋のおばちゃんの持ち物だったり、一階の画家の先生の道具だったりした。このようにひとつの空間から、あらゆる部屋のものが出てくるので、自分用と他人用のふたつの籠を拾ってきて、仕分けしながら掘り出さなければならなくなった。途中で何度か人間の救出活動にも呼ばれて加わった。お向かいの全壊した法律事務所の家の奥さんが電話を貸してくれたので、両親やバイト先への電話も試みたが、依然全くの不通状態だった。こうなったら自分が誰かを助けたら、親も誰かに助けられているに違いないと信じるよりほかはなかった。公的な立場で業務に当たっている人は赤リボン、市民のボランティアは黄リボンをつけて走り回っていた。  そんなこともあって、この日はとにかく命だけは助かったのだから、あまり持ち物に執着を感じるとろくなことにならないと思って捜索を中止した。自分はいったん無一文になったのだから、今日の最小限で重要な収穫だけでも満足しなければならないと自分に言い聞かせ、そうして持ち出してきたものは、置く場所がないので、止むを得ず道端に並べてボロきれをかぶせておいた。夕方に避難所へ戻ると、瓦礫から掘り起こしたもので自分のものではないものを、籠ごと住人たちに見せて回った。そのうちのかなりの数が、本来の持主の手許へ帰っていった。そのあと、管理人がとっておいてくれた配給のおにぎりを食べた。それは、ほぼ二日ぶりの食事だった。そして、地震後はじめて新聞を読んだ。この地震二日目の夕刊が、正式な情報に接する実に初めての機会だった。地震からこのかた、われわれは何の情報も与えられずに、ただ目の前に埋っている人を掘り起こし、自分の財産が失なわれないように気を揉んでいた。携帯ラジオを持ち出せた人もいなかったし、新聞などやっては来なかった。正直なところ、ただならぬ事態だとは思っていたが、いったい世間でどういうことが起こって、周りや遠くはどうなっているのか、風のうわさ以外に知る術はなかったのである。それでも上空を耐えずマスコミのものと思われるヘリが行き来し、不安をあおった。彼等の責任ではないが、彼等はどんどん持ち出すばかりで、われわれには何一つ与えてはくれなかった。やっとのことでありついた新聞によると、友人達の話の通り、広大な範囲に被害が及んでいた。広い範囲で火災に見舞われた西方の地区、ここからすぐ近所の四十五度に傾いたマンション、横倒しになった高速道路、ビルまでがひっくりかえった神戸の中心部。大伸ばしにされた写真を見るたびに息をのんだ。「なんだこれは、これじゃあまるで街ごとなくなったもおんなじじゃないか」沿岸部の主要なベルト地帯が幅二キロ、長さ三十キロにもわたって完璧にやられていた。そこには、いくつもの救出劇や脱出の顛末が記されていた。その後のいろいろな人々の体験談も併せて考えると、いかに気丈な人間がそばに多くいたかということや、いかに近所の人たちとつながりがあったかということ、さらに、そのときどれだけ声を張り上げて自分の所在を周囲に知らせることができたかが、人の生命を左右したことを思い知らされた。それは実のある話だった。ここにいるみんなが、実際にそうやって出て来たからである。それに対して、その時点で発表されていた犠牲者や負傷者、倒壊した建物の数などは、少なすぎて話にもならなかった。「宝山荘の前の通り一本であれだけ死んでるんだぞ。こんなもんじゃない。」二日たつのに当局の状況把握がいかに出来ていないか、いかに情報が混乱しているのかを如実に物語っていた。しかし今から思うに、市や県や、果ては国などが、状況把握に時間がかかったからといっても、あの状態では決して責められるものではない。最も早くから救助活動をしていた当のわれわれでさえ、熟知しているはずの近所の状況ですら、正しく把握していたわけではなかったからである。かえって渦中のわれわれよりも、周辺部に住んでいたあのバンドのメンバーたちのほうが、状況を的確に把握していたくらいだった。ここへ来る途中で、延べにして何十人もの人を助け出していたからである。千里眼をもった人間が何人もいたのならいざ知らず、所詮ただの人間のやることだから、この広大で複雑な災害の全体を混乱なく把握することなど、物理的に不可能な話だった。災害そのものがとてつもなく大きすぎたのである。新聞の下半分を使って大きく載せられた大阪の百貨店の広告がわれわれの神経を逆なでした。「被災された皆様に心からお見舞申し上げます」と書いてあるその横で、それで死んだかも知れない人間がごまんといるというのに、倒れてきたらいかにも痛そうな立派な家具の写真を掲載して、大売り出しを宣伝していたからである。
そんなこともあって、この日はとにかく命だけは助かったのだから、あまり持ち物に執着を感じるとろくなことにならないと思って捜索を中止した。自分はいったん無一文になったのだから、今日の最小限で重要な収穫だけでも満足しなければならないと自分に言い聞かせ、そうして持ち出してきたものは、置く場所がないので、止むを得ず道端に並べてボロきれをかぶせておいた。夕方に避難所へ戻ると、瓦礫から掘り起こしたもので自分のものではないものを、籠ごと住人たちに見せて回った。そのうちのかなりの数が、本来の持主の手許へ帰っていった。そのあと、管理人がとっておいてくれた配給のおにぎりを食べた。それは、ほぼ二日ぶりの食事だった。そして、地震後はじめて新聞を読んだ。この地震二日目の夕刊が、正式な情報に接する実に初めての機会だった。地震からこのかた、われわれは何の情報も与えられずに、ただ目の前に埋っている人を掘り起こし、自分の財産が失なわれないように気を揉んでいた。携帯ラジオを持ち出せた人もいなかったし、新聞などやっては来なかった。正直なところ、ただならぬ事態だとは思っていたが、いったい世間でどういうことが起こって、周りや遠くはどうなっているのか、風のうわさ以外に知る術はなかったのである。それでも上空を耐えずマスコミのものと思われるヘリが行き来し、不安をあおった。彼等の責任ではないが、彼等はどんどん持ち出すばかりで、われわれには何一つ与えてはくれなかった。やっとのことでありついた新聞によると、友人達の話の通り、広大な範囲に被害が及んでいた。広い範囲で火災に見舞われた西方の地区、ここからすぐ近所の四十五度に傾いたマンション、横倒しになった高速道路、ビルまでがひっくりかえった神戸の中心部。大伸ばしにされた写真を見るたびに息をのんだ。「なんだこれは、これじゃあまるで街ごとなくなったもおんなじじゃないか」沿岸部の主要なベルト地帯が幅二キロ、長さ三十キロにもわたって完璧にやられていた。そこには、いくつもの救出劇や脱出の顛末が記されていた。その後のいろいろな人々の体験談も併せて考えると、いかに気丈な人間がそばに多くいたかということや、いかに近所の人たちとつながりがあったかということ、さらに、そのときどれだけ声を張り上げて自分の所在を周囲に知らせることができたかが、人の生命を左右したことを思い知らされた。それは実のある話だった。ここにいるみんなが、実際にそうやって出て来たからである。それに対して、その時点で発表されていた犠牲者や負傷者、倒壊した建物の数などは、少なすぎて話にもならなかった。「宝山荘の前の通り一本であれだけ死んでるんだぞ。こんなもんじゃない。」二日たつのに当局の状況把握がいかに出来ていないか、いかに情報が混乱しているのかを如実に物語っていた。しかし今から思うに、市や県や、果ては国などが、状況把握に時間がかかったからといっても、あの状態では決して責められるものではない。最も早くから救助活動をしていた当のわれわれでさえ、熟知しているはずの近所の状況ですら、正しく把握していたわけではなかったからである。かえって渦中のわれわれよりも、周辺部に住んでいたあのバンドのメンバーたちのほうが、状況を的確に把握していたくらいだった。ここへ来る途中で、延べにして何十人もの人を助け出していたからである。千里眼をもった人間が何人もいたのならいざ知らず、所詮ただの人間のやることだから、この広大で複雑な災害の全体を混乱なく把握することなど、物理的に不可能な話だった。災害そのものがとてつもなく大きすぎたのである。新聞の下半分を使って大きく載せられた大阪の百貨店の広告がわれわれの神経を逆なでした。「被災された皆様に心からお見舞申し上げます」と書いてあるその横で、それで死んだかも知れない人間がごまんといるというのに、倒れてきたらいかにも痛そうな立派な家具の写真を掲載して、大売り出しを宣伝していたからである。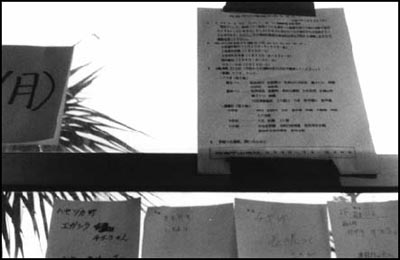 しかし、ルールがいかに確立したとはいっても、食糧や生活用水など、ないものは依然としてなかった。始まったばかりの配給のおにぎりは、氷のように冷たくて固かったし、初めの頃は熱いお茶でさえ手に入らなかった。避難所に据え付けられた電話器もその頃にはかなり増設され、長い時間並ぶこともなくなったが、依然として不通状態が続いていたため、並んだ人の多くは徒労に終わった。これからどうなるのだろう、救出活動も一段落し、崩れ落ちた建物の周りに、なにするということなく集まってきた人々からそんな声が聞かれた。なんとか立っている家の人でさえ、粉々になった食器や家具を片付けなければならないことはわかり切っていたが、多くの人はとてもそんな気にはなれなかった。どうせまた潰されるという思いのほうが強かったからである。「こんなでかい地震、来るんやったら来るで、なんで一声かけてからにしてくれへんかったんや。」今日は燃えないごみの日だったが、それを思い出した人が一体どれだけいただろう。目の前が、いわばもう使い物にならない巨大なごみの山だった。こんなに膨大なごみをどうやって片付けるのだろうか、なんとも気の遠くなるような話だった。倒壊した高架鉄道の北側にあったスーパーは、建物の損壊のため、駐車場に建てた仮設テントに生活必需品のみを拾い集めて業務を再開した。しかし営業時間も大幅に限定され、夜になると寒さのなかでたき火にあたりながら寝ずの番をする、顔見知りの店員の姿が見られたものである。毎日閉店後に行われる恐怖のくじびきが、店員のその夜の運命を決めるのだった。山の手の別の大型スーパーでは、建物の損傷がひどいため、地下のピロティ部分でのごく小規模な営業となっていた。本来なら着飾った客でごった返すはずの店内は、ジャージやスポーツウェア姿の客ばかりで、人がいるのに異様に静まり返っていた。電気は来ていたが、節電のため、BGMも空調も止まっていたからである。避難した住民たちは、まずは自分たちがその日食うものの確保でほぼ手一杯だった。余力のある若い連中は、忙しい人や手の足りない人を助けたり、自分たちの財産の保全に忙しかった。商売をしている人は、店と自宅と避難所の間を、多くは自転車やバイクで、さらに手のこんだ人は、緊急車両と大書した横断幕を前面に張り付けた車で走り回っていた。復旧への草の根の第一歩が始まっていた。それは荒っぽい、どさくさまぎれのサバイバルゲームの様相を呈していたが、それは致し方のないことだった。より一層、気丈な人間が物事を有利に運べる状況が強まっていったのである。お向かいの法律事務所のおやじさんも、どこからか軽トラックを借りてきて「緊急車両」と大書していた。「なにかまうもんか、みなさんの大切な土地や建物を管理しとるんだ。」彼の行動は驚くほど素早かった。三日目にしてすでに新しい事務所兼住居用の物件を押さえていた。の話によると、もう阪神間はおろか、大阪やその周辺部の主だった賃貸物件は、すでに大企業によって従業員の避難用にほとんど押さえられてしまっているとのことだった。「今のうちになんとかしておかないと、本当に住むところがなくなってしまうぞ。」
しかし、ルールがいかに確立したとはいっても、食糧や生活用水など、ないものは依然としてなかった。始まったばかりの配給のおにぎりは、氷のように冷たくて固かったし、初めの頃は熱いお茶でさえ手に入らなかった。避難所に据え付けられた電話器もその頃にはかなり増設され、長い時間並ぶこともなくなったが、依然として不通状態が続いていたため、並んだ人の多くは徒労に終わった。これからどうなるのだろう、救出活動も一段落し、崩れ落ちた建物の周りに、なにするということなく集まってきた人々からそんな声が聞かれた。なんとか立っている家の人でさえ、粉々になった食器や家具を片付けなければならないことはわかり切っていたが、多くの人はとてもそんな気にはなれなかった。どうせまた潰されるという思いのほうが強かったからである。「こんなでかい地震、来るんやったら来るで、なんで一声かけてからにしてくれへんかったんや。」今日は燃えないごみの日だったが、それを思い出した人が一体どれだけいただろう。目の前が、いわばもう使い物にならない巨大なごみの山だった。こんなに膨大なごみをどうやって片付けるのだろうか、なんとも気の遠くなるような話だった。倒壊した高架鉄道の北側にあったスーパーは、建物の損壊のため、駐車場に建てた仮設テントに生活必需品のみを拾い集めて業務を再開した。しかし営業時間も大幅に限定され、夜になると寒さのなかでたき火にあたりながら寝ずの番をする、顔見知りの店員の姿が見られたものである。毎日閉店後に行われる恐怖のくじびきが、店員のその夜の運命を決めるのだった。山の手の別の大型スーパーでは、建物の損傷がひどいため、地下のピロティ部分でのごく小規模な営業となっていた。本来なら着飾った客でごった返すはずの店内は、ジャージやスポーツウェア姿の客ばかりで、人がいるのに異様に静まり返っていた。電気は来ていたが、節電のため、BGMも空調も止まっていたからである。避難した住民たちは、まずは自分たちがその日食うものの確保でほぼ手一杯だった。余力のある若い連中は、忙しい人や手の足りない人を助けたり、自分たちの財産の保全に忙しかった。商売をしている人は、店と自宅と避難所の間を、多くは自転車やバイクで、さらに手のこんだ人は、緊急車両と大書した横断幕を前面に張り付けた車で走り回っていた。復旧への草の根の第一歩が始まっていた。それは荒っぽい、どさくさまぎれのサバイバルゲームの様相を呈していたが、それは致し方のないことだった。より一層、気丈な人間が物事を有利に運べる状況が強まっていったのである。お向かいの法律事務所のおやじさんも、どこからか軽トラックを借りてきて「緊急車両」と大書していた。「なにかまうもんか、みなさんの大切な土地や建物を管理しとるんだ。」彼の行動は驚くほど素早かった。三日目にしてすでに新しい事務所兼住居用の物件を押さえていた。の話によると、もう阪神間はおろか、大阪やその周辺部の主だった賃貸物件は、すでに大企業によって従業員の避難用にほとんど押さえられてしまっているとのことだった。「今のうちになんとかしておかないと、本当に住むところがなくなってしまうぞ。」  font size="2"> しかし住民の多くは、これから住むところの心配はおろか、今まで住んでいたところのことでさえ、気持ちの整理などついていなかった。特に全壊した木造の集合住宅の人々にとっては、崩れ果てたわが家のありさまに呆然とするばかりで、車を持っている人でさえ、自分が車で動くことなど全くぴんとこなかった。私でさえそのときはじめて自分の車のことを思い出し、あわてて駐車場へ走って見に行ったほどである。青空駐車場だったのが幸いして車は無傷だった。しかし、整然と並んでいるはずの車は、駐車場のなかでごったがえしていた。なかには真ん中の通路を通り越して向かい側の車の列に危うく接触しかかっているものもあった。広い駐車場は全体が波打ち、ところどころに地割れができていた。キーさえあれば、荷台にとりあえず自分の荷物を積むことだってできたのだが、どうしようもないのでそこをあとにし、近所の様子を見ながらアパートへ戻った。ボヤをだしたと噂された散髪屋のおやじは、崩れかけた店から器具を運び出していた。声をかけると、少し笑って力無く肩をすくめると、割れた分厚いガラスのドアの向こうに消えていった。途中、早くも他府県ナンバーの、明らかに見物に来たとわかるアベックの乗ったスポーツカーを見かけた。彼等のもの珍しそうな目つきは、どうしても一部の住民の神経を逆なでしたに違いない。砂だらけの風のなか、誰もが薄汚れた服を着て肩を落としてうろつき回っているというのに、美しく光り輝くその赤い車は、いかにも場所に不相応に見えたからである。その日は、午前中に芦屋の老舗の写真材料店で手に入れた、古いライカのボディが見つかった。それは本棚と柱に挟まれ、さらに上から壁がのしかかっていたのでびくともしなかった。おまけに壁土にまみれていた。それを見たとき、思わず涙がこぼれそうになったが、露出していた巻き上げノブをチリチリとまわし、シャッターを切ってみると、「シャッ」という確かな音がした。その音で私は我に返った。太い木を捜してきてテコの原理でゆっくりと柱を浮かせ、救出にとりかかった。本棚の側板が割れたものの、何度めかの試みでそれをうまく引きずり出すことができた。砂にまみれているとはいえ、小さくてずっしりと重いその感触は、私に勇気を与えてくれた。それに気をよくして、私はずんずん掘り進んでいった。それに従って色々なものが姿を現わした。柱や梁が硬く壁に食い込んだ柵の向こうに、恩師ブレッソンのフォトポートレートやその他の高価な写真集、ザイールの奥地で私の命を救ったひとりの木こりがプレゼントしてくれた木彫の人形、愛用のマッキントッシュの本体とバックアップのフロッピーのケースなどが見えた。さらに崩れ落ちた押入の下に、十年ほど前に三宮でバーをやっていたジャマイカ系アイルランド黒人が譲ってくれた古いコンガや、近くのホールで買い換えのために処分されかかっていたのを格安で買い上げたドラムセットなどが見えた。しかし、それらは見えていても柱や壁が重たくのしかかって、一人の力ではびくともしない複雑な格子の向こうになっていた。
font size="2"> しかし住民の多くは、これから住むところの心配はおろか、今まで住んでいたところのことでさえ、気持ちの整理などついていなかった。特に全壊した木造の集合住宅の人々にとっては、崩れ果てたわが家のありさまに呆然とするばかりで、車を持っている人でさえ、自分が車で動くことなど全くぴんとこなかった。私でさえそのときはじめて自分の車のことを思い出し、あわてて駐車場へ走って見に行ったほどである。青空駐車場だったのが幸いして車は無傷だった。しかし、整然と並んでいるはずの車は、駐車場のなかでごったがえしていた。なかには真ん中の通路を通り越して向かい側の車の列に危うく接触しかかっているものもあった。広い駐車場は全体が波打ち、ところどころに地割れができていた。キーさえあれば、荷台にとりあえず自分の荷物を積むことだってできたのだが、どうしようもないのでそこをあとにし、近所の様子を見ながらアパートへ戻った。ボヤをだしたと噂された散髪屋のおやじは、崩れかけた店から器具を運び出していた。声をかけると、少し笑って力無く肩をすくめると、割れた分厚いガラスのドアの向こうに消えていった。途中、早くも他府県ナンバーの、明らかに見物に来たとわかるアベックの乗ったスポーツカーを見かけた。彼等のもの珍しそうな目つきは、どうしても一部の住民の神経を逆なでしたに違いない。砂だらけの風のなか、誰もが薄汚れた服を着て肩を落としてうろつき回っているというのに、美しく光り輝くその赤い車は、いかにも場所に不相応に見えたからである。その日は、午前中に芦屋の老舗の写真材料店で手に入れた、古いライカのボディが見つかった。それは本棚と柱に挟まれ、さらに上から壁がのしかかっていたのでびくともしなかった。おまけに壁土にまみれていた。それを見たとき、思わず涙がこぼれそうになったが、露出していた巻き上げノブをチリチリとまわし、シャッターを切ってみると、「シャッ」という確かな音がした。その音で私は我に返った。太い木を捜してきてテコの原理でゆっくりと柱を浮かせ、救出にとりかかった。本棚の側板が割れたものの、何度めかの試みでそれをうまく引きずり出すことができた。砂にまみれているとはいえ、小さくてずっしりと重いその感触は、私に勇気を与えてくれた。それに気をよくして、私はずんずん掘り進んでいった。それに従って色々なものが姿を現わした。柱や梁が硬く壁に食い込んだ柵の向こうに、恩師ブレッソンのフォトポートレートやその他の高価な写真集、ザイールの奥地で私の命を救ったひとりの木こりがプレゼントしてくれた木彫の人形、愛用のマッキントッシュの本体とバックアップのフロッピーのケースなどが見えた。さらに崩れ落ちた押入の下に、十年ほど前に三宮でバーをやっていたジャマイカ系アイルランド黒人が譲ってくれた古いコンガや、近くのホールで買い換えのために処分されかかっていたのを格安で買い上げたドラムセットなどが見えた。しかし、それらは見えていても柱や壁が重たくのしかかって、一人の力ではびくともしない複雑な格子の向こうになっていた。 
 この頃から、自衛隊の捜索の主眼は行方不明者の救出から犠牲者の収容に移り、高架鉄道の北側からオリーブ色の制服姿の自衛隊員が、頭まですっぽりと毛布をかけられた遺体を畳に乗せて運ぶ姿が頻繁に見られるようになった。上空を爆音をたてて飛んで来るヘリコプターの数も増えた。地上では依然四方八方がサイレンとクラクションの騒音の渦で、まるで街全体が唸りを上げているかのようだった。瓦礫の砂が舞上げられて、風景全体が黄色く濁って見えた。この緊張感のみなぎる騒然とした空気のおかげで、ここがついおとといまで安楽に暮らしていた同じ場所とはとても思えなかった。舌がざらつく。絶えずガスと瓦礫の臭気が鼻をつく。ふと顔に手をやると、砂でざらざらだった。瓦礫との戦いは、この砂との戦いでもあった。西のほうから夥しい人の群れが目の前を通りすぎるようになった。彼等は、宝山荘の北側で落橋した鉄道の折り返し地点を目指して、何十キロという道のりを、遥か西方の土地から、はるばる歩いてきたのである。毛布にくるまっていたり、乳母車を押していたり、誰も彼もがじっとりと重い、疲れた雰囲気をたたえていた。なかには代八車に家財一式と思われるほど荷物を積んで転がしている男たちもいたが、多くは身一つか軽装だった。そのなかに、火災の激しかった西の方の地域から一日中歩き通しだという老人がいた。東へ行ってどうするのかと聞くと、とりあえずあてはないが、出てきたところよりはましだろうと言うので、手持ちの水を渡して、ここらで避難所へもぐり込んでみたらと勧めた。というのも、ここから東へ行くと被害が軽くなり、避難所もまばらになるだろうと思ったからである。行列は夕方になるにしたがって増え、夜になっても衰える気配はなかった。逆に東から西へ、大きなリュックをかついだ人の行列が流れていくのが見られはじめた。周辺地域からのお見舞いや、救援のボランティアの始まりである。西へ向かう人は、東へ逃げる人と違って、服装もこぎれいで快活だった。中には派手に崩れた鉄道の高架をバックに記念写真を撮る人まであった。そんな人の流れは、宝山荘の前ばかりでなく、少し南側の国道から、はるか南方の海岸部を走る幹線道路までの通りという通りを埋め尽くしていたのである。まさに、民族の大移動といった様相を呈していた。その流れに乗って、西からバンドのメンバーのひとりが嫁さんとともにやってきた。自宅が全壊してしまったので、なんとか電車に乗って川向こうへ行くつもりだと言う。一緒に行こうと勧められたが、私はここでもう少しやりたいことがあるのでまた今度にすると答えた。翌日、その友人は自宅のあとかたづけに戻る途中、私のために食料や飲料と、荷物を運ぶための折り畳み式のキャリアを持って来てくれた。私はそれをありがたく受け取り、昼過ぎに再び彼が帰りがけにここを訪れたとき、まとめられるだけの重要な荷物をまとめて彼と同行することにした。瓦礫の山から引きずり出して、通りに積み上げられていた私の持ち物が、ただならぬ量になってきたからである。先の見通しは全く立たなかったが、いざとなれば素手ででも全部運んでやる覚悟だった。さらに、彼が川向こうは本当に何事もなかったかのように正常に動いていると、何度も力説したからである。私はそれをにわかには信じられなかったが、もし本当ならそれを見てみたかった。「こんなところにいつまでもいられるわけがない」と、彼は私を強く促した。
この頃から、自衛隊の捜索の主眼は行方不明者の救出から犠牲者の収容に移り、高架鉄道の北側からオリーブ色の制服姿の自衛隊員が、頭まですっぽりと毛布をかけられた遺体を畳に乗せて運ぶ姿が頻繁に見られるようになった。上空を爆音をたてて飛んで来るヘリコプターの数も増えた。地上では依然四方八方がサイレンとクラクションの騒音の渦で、まるで街全体が唸りを上げているかのようだった。瓦礫の砂が舞上げられて、風景全体が黄色く濁って見えた。この緊張感のみなぎる騒然とした空気のおかげで、ここがついおとといまで安楽に暮らしていた同じ場所とはとても思えなかった。舌がざらつく。絶えずガスと瓦礫の臭気が鼻をつく。ふと顔に手をやると、砂でざらざらだった。瓦礫との戦いは、この砂との戦いでもあった。西のほうから夥しい人の群れが目の前を通りすぎるようになった。彼等は、宝山荘の北側で落橋した鉄道の折り返し地点を目指して、何十キロという道のりを、遥か西方の土地から、はるばる歩いてきたのである。毛布にくるまっていたり、乳母車を押していたり、誰も彼もがじっとりと重い、疲れた雰囲気をたたえていた。なかには代八車に家財一式と思われるほど荷物を積んで転がしている男たちもいたが、多くは身一つか軽装だった。そのなかに、火災の激しかった西の方の地域から一日中歩き通しだという老人がいた。東へ行ってどうするのかと聞くと、とりあえずあてはないが、出てきたところよりはましだろうと言うので、手持ちの水を渡して、ここらで避難所へもぐり込んでみたらと勧めた。というのも、ここから東へ行くと被害が軽くなり、避難所もまばらになるだろうと思ったからである。行列は夕方になるにしたがって増え、夜になっても衰える気配はなかった。逆に東から西へ、大きなリュックをかついだ人の行列が流れていくのが見られはじめた。周辺地域からのお見舞いや、救援のボランティアの始まりである。西へ向かう人は、東へ逃げる人と違って、服装もこぎれいで快活だった。中には派手に崩れた鉄道の高架をバックに記念写真を撮る人まであった。そんな人の流れは、宝山荘の前ばかりでなく、少し南側の国道から、はるか南方の海岸部を走る幹線道路までの通りという通りを埋め尽くしていたのである。まさに、民族の大移動といった様相を呈していた。その流れに乗って、西からバンドのメンバーのひとりが嫁さんとともにやってきた。自宅が全壊してしまったので、なんとか電車に乗って川向こうへ行くつもりだと言う。一緒に行こうと勧められたが、私はここでもう少しやりたいことがあるのでまた今度にすると答えた。翌日、その友人は自宅のあとかたづけに戻る途中、私のために食料や飲料と、荷物を運ぶための折り畳み式のキャリアを持って来てくれた。私はそれをありがたく受け取り、昼過ぎに再び彼が帰りがけにここを訪れたとき、まとめられるだけの重要な荷物をまとめて彼と同行することにした。瓦礫の山から引きずり出して、通りに積み上げられていた私の持ち物が、ただならぬ量になってきたからである。先の見通しは全く立たなかったが、いざとなれば素手ででも全部運んでやる覚悟だった。さらに、彼が川向こうは本当に何事もなかったかのように正常に動いていると、何度も力説したからである。私はそれをにわかには信じられなかったが、もし本当ならそれを見てみたかった。「こんなところにいつまでもいられるわけがない」と、彼は私を強く促した。  私は、使えそうな段ボールをいくつも拾ってきて、大事なものから順に詰めてゆき、キャリアに縛りつけて出発した。避難所に外出先を伝言し、アパートの住人に声をかけて、東へ向かう行列に加わった。われわれは、瓦礫に塞がれた通りを迂回しようとして右往左往する人々をやりすごし、なんとか一本通っている道をみつけて進んだ。人々の服装は、ほぼ例外なくスポーツ・ウェアかジャージ姿で、大きなリュックを背負っていたり、荷物を満載したキャリアを引いていたりした。京都へ延びる古い街道筋に並行する国道までは、だいたい宝山荘のあたりと同じで、木造家屋のほとんどが全壊していた。四日たって、いくらかこの光景が見慣れたものになったとはいっても、それはやはり悲惨な眺めだった。見慣れた街並みがほとんど崩れ去り、鉄筋コンクリートの建物でさえ、大きく傾いているものが多かった。ところが不思議なことに、その街道を越えると急にあたりの様子が一変した。なにか、街並みが目にすっきりと整然としたものになったのである。もちろん瓦が落ちていたり、壁が剥がれていたりはするのだが、まっすぐなものはだいたいまっすぐに建っていた。建物の破壊の程度が比較にならないほど軽かったのである。これは不思議な現象だった。その後あちこちで、全く無傷な家並みの真ん中に突然ずたずたになった区画がかたまって出現したり、通り一本をはさんだ街の両側の様子がありありと違うという光景を何度も目にした。あとになって、それは地震波の屈折と集中が主な原因だという報道を聞いた。広い道はどこも例外なく車であふれ返り、それらは猛烈な渋滞のためにぴくりとも動かなかった。脇道や路地から人が通りに溢れ出していた。人々は瓦礫で埋め尽くされた歩道を避けて、車道の動かぬ車の間にまで入り込み、そのせまい隙間でひしめき合っていた。そこへ自衛隊の装甲車やトラックやバスがけたたましいサイレンを鳴り響かせながら何台も編隊を組んで押し寄せ、道を譲ろうとする車が夥しい歩行者の列に突っ込んだために叫び声が上がったりした。堂々たるいかつい面構えで、道をあけなさいとがなりながら進んでくるその姿に、いかな黒塗のベンツといえども、圧倒されてしぶしぶ道を譲った。しかし、自分を追い越していく救急車に追従することは、決して忘れなかった。自衛隊の双発ヘリコプターが何機も下腹に応えるほどの爆音を轟かせて上空を飛び去って行った。「戒厳令とはこんなもんだろうな。」友人に話しかけたその声も届かなかった。そんななか、お祭り騒ぎと勘違いしたのか、または食べ物屋の少ない状況のなかで、すこしでも暖かい食事をというボランティア精神の現われか、はたまたどんなときにも商売を忘れぬ浪速商人のど根性か、実に様々な屋台がちょっと前の十日戎さながらに、幹線道路に繰り広げられていたのには目を見張ってしまった。乗用車いっぱいに菓子パンを積んで一個二百円均一で売っているうさん臭い二人連れの男がいた。一個三千円もするヤキイモ屋が現われた。「いらっしゃいいらっしゃい」という威勢のいいかけ声も、通りの騒音にかき消されがちだったが、子供に与える風船やヨーヨー釣りまでやっていたのには恐れ入った。タクシーを降りた婦人が料金をめぐって運転手とやりあっていた。バイクの兄ちゃんが大きなリュックを背負った男と値段の交渉をしていた。 粗末な机を持ち出して、携帯電話を無料貸出ししているコーナーがあったが、これは今後の顧客拡大を狙ったものだったのだろう。しかし後日、携帯電話からは、一一九番にシステム上繋がらないことになっていることが大々的に報じられたり、また復興に名を借りた様々なビジネスに悪用されたり、解約についてのユーザーへの説明が不十分だったりして、はからずもその欠点を広く世に知らしめる結果となってしまった。たいていがこのどさくさに、他人の足許を見透かしたような商売をする輩どもだったが、もちろん、そんなわるいやつらばかりではなかった。駅前のあるスーパーの店頭では、なんと幕の内弁当が暖かい味噌汁つきでたったの百円で売られていた。無料といわれると何だかプライドを傷つけられたような気がするが、百円というその絶妙の値段設定にちょっと心が動きそうになった。しかしぐっとこらえてその場をやりすごした。また、街の角という角には、付近の地図をコピーして現在地を示し、不案内な訪問者に便宜をはかったり、さらには、その地図のコピーを無料配布しているところがあちこちにあった。さらに、飲料や食料、訪問者がうっかり忘れてきそうな被災地での生活必需品を並べて売っているところもあった。政治的には犬猿の仲の隣どうしのふたつの国が、対立を越えて互いの援助を申し出る貼紙も見られた。そんなこんなで、道中は結構物見遊山の状態だった。とはいっても、やはり誰もが気忙しいのか、店に立ち寄る人はまばらだった。のみならずこのへんまで来ると、あちこちからこの駅を目指してきた人たちで道路は道幅いっぱいに埋め尽くされ、とても店の前まで行ったり、足を止めたりできるような状態ではなかった。
私は、使えそうな段ボールをいくつも拾ってきて、大事なものから順に詰めてゆき、キャリアに縛りつけて出発した。避難所に外出先を伝言し、アパートの住人に声をかけて、東へ向かう行列に加わった。われわれは、瓦礫に塞がれた通りを迂回しようとして右往左往する人々をやりすごし、なんとか一本通っている道をみつけて進んだ。人々の服装は、ほぼ例外なくスポーツ・ウェアかジャージ姿で、大きなリュックを背負っていたり、荷物を満載したキャリアを引いていたりした。京都へ延びる古い街道筋に並行する国道までは、だいたい宝山荘のあたりと同じで、木造家屋のほとんどが全壊していた。四日たって、いくらかこの光景が見慣れたものになったとはいっても、それはやはり悲惨な眺めだった。見慣れた街並みがほとんど崩れ去り、鉄筋コンクリートの建物でさえ、大きく傾いているものが多かった。ところが不思議なことに、その街道を越えると急にあたりの様子が一変した。なにか、街並みが目にすっきりと整然としたものになったのである。もちろん瓦が落ちていたり、壁が剥がれていたりはするのだが、まっすぐなものはだいたいまっすぐに建っていた。建物の破壊の程度が比較にならないほど軽かったのである。これは不思議な現象だった。その後あちこちで、全く無傷な家並みの真ん中に突然ずたずたになった区画がかたまって出現したり、通り一本をはさんだ街の両側の様子がありありと違うという光景を何度も目にした。あとになって、それは地震波の屈折と集中が主な原因だという報道を聞いた。広い道はどこも例外なく車であふれ返り、それらは猛烈な渋滞のためにぴくりとも動かなかった。脇道や路地から人が通りに溢れ出していた。人々は瓦礫で埋め尽くされた歩道を避けて、車道の動かぬ車の間にまで入り込み、そのせまい隙間でひしめき合っていた。そこへ自衛隊の装甲車やトラックやバスがけたたましいサイレンを鳴り響かせながら何台も編隊を組んで押し寄せ、道を譲ろうとする車が夥しい歩行者の列に突っ込んだために叫び声が上がったりした。堂々たるいかつい面構えで、道をあけなさいとがなりながら進んでくるその姿に、いかな黒塗のベンツといえども、圧倒されてしぶしぶ道を譲った。しかし、自分を追い越していく救急車に追従することは、決して忘れなかった。自衛隊の双発ヘリコプターが何機も下腹に応えるほどの爆音を轟かせて上空を飛び去って行った。「戒厳令とはこんなもんだろうな。」友人に話しかけたその声も届かなかった。そんななか、お祭り騒ぎと勘違いしたのか、または食べ物屋の少ない状況のなかで、すこしでも暖かい食事をというボランティア精神の現われか、はたまたどんなときにも商売を忘れぬ浪速商人のど根性か、実に様々な屋台がちょっと前の十日戎さながらに、幹線道路に繰り広げられていたのには目を見張ってしまった。乗用車いっぱいに菓子パンを積んで一個二百円均一で売っているうさん臭い二人連れの男がいた。一個三千円もするヤキイモ屋が現われた。「いらっしゃいいらっしゃい」という威勢のいいかけ声も、通りの騒音にかき消されがちだったが、子供に与える風船やヨーヨー釣りまでやっていたのには恐れ入った。タクシーを降りた婦人が料金をめぐって運転手とやりあっていた。バイクの兄ちゃんが大きなリュックを背負った男と値段の交渉をしていた。 粗末な机を持ち出して、携帯電話を無料貸出ししているコーナーがあったが、これは今後の顧客拡大を狙ったものだったのだろう。しかし後日、携帯電話からは、一一九番にシステム上繋がらないことになっていることが大々的に報じられたり、また復興に名を借りた様々なビジネスに悪用されたり、解約についてのユーザーへの説明が不十分だったりして、はからずもその欠点を広く世に知らしめる結果となってしまった。たいていがこのどさくさに、他人の足許を見透かしたような商売をする輩どもだったが、もちろん、そんなわるいやつらばかりではなかった。駅前のあるスーパーの店頭では、なんと幕の内弁当が暖かい味噌汁つきでたったの百円で売られていた。無料といわれると何だかプライドを傷つけられたような気がするが、百円というその絶妙の値段設定にちょっと心が動きそうになった。しかしぐっとこらえてその場をやりすごした。また、街の角という角には、付近の地図をコピーして現在地を示し、不案内な訪問者に便宜をはかったり、さらには、その地図のコピーを無料配布しているところがあちこちにあった。さらに、飲料や食料、訪問者がうっかり忘れてきそうな被災地での生活必需品を並べて売っているところもあった。政治的には犬猿の仲の隣どうしのふたつの国が、対立を越えて互いの援助を申し出る貼紙も見られた。そんなこんなで、道中は結構物見遊山の状態だった。とはいっても、やはり誰もが気忙しいのか、店に立ち寄る人はまばらだった。のみならずこのへんまで来ると、あちこちからこの駅を目指してきた人たちで道路は道幅いっぱいに埋め尽くされ、とても店の前まで行ったり、足を止めたりできるような状態ではなかった。