私の初めての海外旅行の目的地は、アフリカ中部のザイール共和国(現在のコンゴ民主共和国)の首都キンシャサだった。アメリカやヨーロッパではなく、何故よりによってそんなところを目的地に選んだのかとよく人に訊かれるのだが、それを明らかにするのはそう簡単なことではない。しかしひとつだけすぐに答えられるのは、私の旅の目的は、アフリカを訪れる人たちの大半がそうであるように、サファリ・ツアーやアウト・ドア指向の観光旅行、さらにはバック・パッカーに代表されるような流浪の旅や冒険旅行にあったのではなく、ただひとつ音楽の為だけにあったという事だ。しかも私はドラムとパーカッションをやっていたので、現地へ行って音楽を聴くことだけでなく、それを修得することが第一の目的だったのである。
当時、私は「カーリー・ショッケール」というバンドでコンガを叩いていた。それは「リンガラ・ポップス」というアフリカのダンス・ミュージックを日本語のオリジナルで演奏するバンドだったが、結成されて間もない当初は、とりあえず好き者どうしが集まってレコードを聴いたり、コピーに頼らず日本語で自分たちの歌を歌うという、高い理想を掲げたりしてはしていたものの、やっていることといえば、数少ないレコードの気に入ったフレーズを聴きまねでつま弾いてみたり、日本語の持つ五・七調のリズムを、アフリカ的に歌いこなすことが出来ずに苦しんでいた。そんなわけで、実際の我々の演奏は、何の実質も伴わない猿まね以下の状態だった。そしてその主な原因は、なんと言ってもリズム・セクションの弱さにあったのだが、それはこの手の音楽にとっては実に致命的なことだった。だからまず第一に、自分がリズム・セクションの一翼を担う以上、自分でこの限界を克服し、リズムを引っ張っていけるだけの何か確たるものを身につける必要を感じたのである。それはレコードをいくら聴いても、日本でドラム・スクールなどに通ってみても、とうていかなわないことのように思われた。さらにこのリンガラ・ポップスという謎めいた音楽は、長い時間や様々な苦労と引き替えにしてでも、探っていくに足ると思われるほど、当時の私には魅力的なものに感じられた。だから仕事も棒に振り、予告された様々な危険も省みず、迷わず行くことを決心したのである。
私はリズムセクションの担当だったが、性格からいっても、体力からいっても、むしろメロディやハーモニーを担当するのに向いているはずだった。ところが私はそんな自分の素質とは裏腹に、子どもの頃からリズム楽器に強い関心を持っていた。話はかなりさかのぼるが、中学に入っていわゆる軽音楽というものを実際にやってみるチャンスに出会うと、即座にあこがれのドラム・セットの前に座った。しかし、持ち前の反骨精神と人に物事を指図されることに対する嫌気から、基礎からきっちり手順を学ぶということはついになく、我流も我流で、自分のやりたいことだけをやりたいようにやってきた。つまり鍛錬に欠けていたのである。さらに当時、すなわち一九七〇年代後半は、私の回りで連れが聴いていた音楽の潮流は、今よりもずっと精神的な感触を大切にする傾向にあったし、私の関心もご多分に漏れず頭までどっぷりとヨーロッパ指向であった。今でこそリズム・マシーンなんてガキでも買える世の中だが、当時は高嶺の花で、私がドラムを叩いていたのも、そのときのバンドにリズム・マシーンを買う金がなかったからにほかならない。ドラムなんて誰も注意して聞いていなかった。ややもすると、「変なおかずなんて入れんな。」と、文句を言われる始末だった。出来るだけ機械的にたたくことが求められていたからである。当時の私の連れは、ミュージック・シーンのメインストリームから大きくはずれてアングラなシーンに走り、世の中を斜に構えた変な奴等が多かった。当時の我々のドラムについての関心なんて、クラウス・ディンガーの驚異の右足だとか、ヴェルナー・デイエルマイヤーのあの不思議な金属音だとか、ジャキ・リーベツァイトの植物的なリズムの感触だとか、そんなことばかりで、グルーヴ感だとか肉体的動物的な躍動感などというものは、どちらかというと軽んじられる傾向にあった。当時の私も全く同感で、普通のドラマーなら、フット・ライトを浴びて派手なセットに座って両手を広げ、スティックをクルクル回すということをやってみたがるもんだが、私はそんなことには一切目もくれず、一枚のシンバルをたたくにあたって、シンバルのどの部分をどんな重さのスティックでどんなタッチでたたけばどんな音色がするかという事を、またそれは一体何故なのかという事を、静かな音楽室の片隅にうずくまって、いつまでも難しい顔をしながら考え込んでいるような少年だった。
紆余曲折があったとはいうものの、大体そのままで大きくなったものだから、ふとしたきっかけでアフリカの音楽にのめり込んでからも、ドラムやパーカッションでうねりを出すなどということは大の苦手で、むしろ細かい音でちょこまかと音色を楽しむ方に向いていた。つまり、パーカッションでいうと、コンガの野太い音で全体のグルーヴ感をどうこうすることより、ウッド・ブロックやカウベルで、歯切れの良い細かなのりを刻んでいくことの方が得意だった。得意なことだけで満足していれば何の苦労もなかったはずである。しかし私は、常に自分の手に入り得ないものを欲しがる悪い癖がある。そして一旦手に入れようと思ったら、自分の力量も省みずに、言いだしたら聞かない天の邪鬼なところが強かった。すなわちザイールの音楽にふれてそれにのめり込むにつれ、だんだんとうねりやグルーヴ感の大切さを理解するようになり、それを自分の手で出したくなってきたのである。しかしそんなことをやる素養もなく、鍛錬も全く出来ていなかったから、バンドで演奏しはじめてもすぐに行き詰まってしまった。それはなかなか越えられない壁だった。レコードを聴いてそのままのリズム・パターンで音を取っているはずなのに、全体の印象はまるで違うものになった。いくら分析しても解明できなかった。今でもその原因はこれだと言い当てることは出来ないが、おそらくは、オン・リズムからの何十分の一秒、いや何百分の一秒という微妙なためやつっこみ、ドラムでいうと、ハイハットやスネアの各パーツの音のバランスや、タッチの違いが、全体ののりやグルーヴを支配しているとしか考えようがなかった。それは現地へ行って、ドラマーやパーカッショニストがたたいているのをこの目で見て、体で覚えるよりほかに方法がないと思われた。だからザイールに行ったのである。
もともとの私の音楽的な指向
さて、では何故ザイールの音楽に関心を持ったのか。これは少し重要なことである。もともと私の音楽的な指向は、精神的、宇宙的なものを模索するような音楽、ひらたく言えば、一九七〇年代当時プログレと呼ばれていた音楽の流れに向いていた。しかも今から考えると、かなり極端にアンダー・グラウンドなシーンにはまりこんでいた。これについて長く書きたいのは山々だが、本題から果てしなくそれていくのでまたの機会にする。しかし、本来奔放であるはずの少年期を、スポーツやレジャーというものをほとんど拒否して、何ともじじむさい観念的な世界に埋没し、何枚ものレコードを抱えて時間や空間についての抽象的な理屈をつぶやきながら、ひとり道を歩いていたのは、今から考えればなんとも勿体ないことである。それは、今もつきあいのある中学時代からの二人の連れの影響によるものだった。私の青春時代は、この二人によって完膚無きまでにむしばまれてしまったと言っても過言ではない。それさえなければ、多分私はまっとうにロックの王道をきわめ、一般的な同世代の誰もが聞くように、ビートルズやストーンズを聞き、リズム・アンド・ブルースやソウルなどから、黒人音楽のグルーヴ感についての見識を深めていったに違いないと思われるからである。少なくとも、ドラムやパーカッションでこんなに苦労させられることはなかったはずだし、そもそもこんな硬い文章を書くようになったことそのものが、彼ら二人の悪友のもはや私の中では消すことの出来ない影響なのである。まあそんなことは今となってはどうでもいい。とにかく、なるべくしてなったとはいえ、私の持って生まれた素養のある特殊な部分が、彼ら二人によって異常なまでに開発されてしまったことだけは確かである。「プログレ」と呼びならわされていたその音楽は、当時まだ開発の途上にあったシンセサイザーをはじめとする様々な電子楽器を使って、多彩な実験を試みる音楽だった。そしてその音楽性は、実用性や具体性、現実性などというものを厳しく排し、実験室あるいは温室の中で、無限の宇宙を模索する意識の果てしない遊泳を楽しむかのような、抽象的で思索的な、一種独特の感触があった。今となっては頭の痛くなるような音だが、当時はやはり子どもだったからか、何も知らずにその感触の中におぼれていった。そして長い年月を経て、徐々にそうした音の世界を深めてゆき、次第にヨーロッパの精神的な伝統を深く愛するようになった。
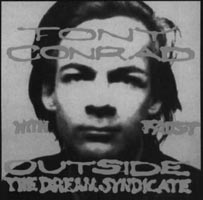 たしかあれは高校三年の頃だった。その悪友の一人から、あるテープを手に入れた。「トニー・コンラッド・ウィズ・ファウスト」。忘れもしないその音は、暗いと言うよりもごつごつに黒い音だった。しかもそれは、肉体的な黒さではなく、絶望的なまでに精神的な黒さだった。その黒さは暗さが極限にまで凝縮されて、どんな物質よりも固く、すべての光を吸い尽くし、自身の重さによって永遠に収縮し続けるかと思われるほどに深い黒、なにものの感情移入をもひたすら拒み続け、一切の人間的現実性をはるかに超越した純粋な意識を、厳しくこちらに突きつけてくるような冷徹で無機的な黒だった。気が遠くなるくらい単調で、背骨の芯から凍り付くような恐ろしさを持ったその音に、私は全身でのめり込んでいった。人と口をきかなくなり、物事の現実的な有り様や関連性が遠ざかっていった。音や光を現実のものとしてではなく、抽象的な概念としてとらえるようになり、時間と空間を意識できるようになった。ただ一人部屋にこもって、食事もとらず寝る間も惜しんでいつまでも繰り返しそのテープだけを聴き続ける日々が何日も続いた。両親が心配して様子を見に来ても一切応えず、ヘッド・ホンを両手で押さえ、アンプの前にかじり付いていた。そんなある明け方のことである。テープの両側にわずかにたるみがあらわれはじめたのを見て、それを何故かこの世界の終末と勘違いし、恐怖の余りまだ真っ暗な外へ飛び出して、大声を上げながら家の前の急な坂道を駆け下り、車でさえ三〇分はかかる、幼いころ自分の通っていた幼稚園の庭を一回りして、一歩も休まずに家まで走って帰って来た。驚いて起き出した両親の不安を後目に、猛烈な空腹感から台所にあった食料をあらかた平らげ、まだそんな時間でもないのに電車に乗って学校へ行った。相変わらず人とは口を利かない日々が続いたが、音楽を聴くのはそれきりぱったりとやめてしまった。何故か頭の中で何かが切れてしまって、すべてが相対的で、自分の存在にとってはどうでもよいことのように思われだした。あらゆるものが私自身との関連性を失い、バラバラに遠ざかっていくように思われた。そんな、空虚でなにものをも信じることの出来ない精神状態の中で受験に失敗した。
たしかあれは高校三年の頃だった。その悪友の一人から、あるテープを手に入れた。「トニー・コンラッド・ウィズ・ファウスト」。忘れもしないその音は、暗いと言うよりもごつごつに黒い音だった。しかもそれは、肉体的な黒さではなく、絶望的なまでに精神的な黒さだった。その黒さは暗さが極限にまで凝縮されて、どんな物質よりも固く、すべての光を吸い尽くし、自身の重さによって永遠に収縮し続けるかと思われるほどに深い黒、なにものの感情移入をもひたすら拒み続け、一切の人間的現実性をはるかに超越した純粋な意識を、厳しくこちらに突きつけてくるような冷徹で無機的な黒だった。気が遠くなるくらい単調で、背骨の芯から凍り付くような恐ろしさを持ったその音に、私は全身でのめり込んでいった。人と口をきかなくなり、物事の現実的な有り様や関連性が遠ざかっていった。音や光を現実のものとしてではなく、抽象的な概念としてとらえるようになり、時間と空間を意識できるようになった。ただ一人部屋にこもって、食事もとらず寝る間も惜しんでいつまでも繰り返しそのテープだけを聴き続ける日々が何日も続いた。両親が心配して様子を見に来ても一切応えず、ヘッド・ホンを両手で押さえ、アンプの前にかじり付いていた。そんなある明け方のことである。テープの両側にわずかにたるみがあらわれはじめたのを見て、それを何故かこの世界の終末と勘違いし、恐怖の余りまだ真っ暗な外へ飛び出して、大声を上げながら家の前の急な坂道を駆け下り、車でさえ三〇分はかかる、幼いころ自分の通っていた幼稚園の庭を一回りして、一歩も休まずに家まで走って帰って来た。驚いて起き出した両親の不安を後目に、猛烈な空腹感から台所にあった食料をあらかた平らげ、まだそんな時間でもないのに電車に乗って学校へ行った。相変わらず人とは口を利かない日々が続いたが、音楽を聴くのはそれきりぱったりとやめてしまった。何故か頭の中で何かが切れてしまって、すべてが相対的で、自分の存在にとってはどうでもよいことのように思われだした。あらゆるものが私自身との関連性を失い、バラバラに遠ざかっていくように思われた。そんな、空虚でなにものをも信じることの出来ない精神状態の中で受験に失敗した。
以上が、大体少年期から青年期のはじめにかけての私の音楽的遍歴のあらましである。これをみてもわかるように、そのころの私は、今のようにとてもアフリカ音楽などに興味を持つような人間ではなかった。それは高校時代からの数少ない私の友人が、口を揃えて言っている。それどころか、いつも何を考えているのかよくわからない、内向的で暗い性格の持ち主だった。そのテープのおかげで、私の性向は極限にまで追いつめられ、行き場を失なってそこではじけてしまった。そして、それまで大切にしてきた自分の性格ですら、どうでもよいものに思われだした。その結果、逆にあらためて自分の周りにあるものを手近なものから順番に自分の意識の中に置き直すことが出来るようになり、どんな音楽でも楽しめるようになった。
「プログレ」にキレて「アフリカ」にハマる
 何故ザイールの音楽に興味を持ったのかを書くはずだったが、とんだ寄り道をしてしまった。その後、一年間の浪人生活の末、日本一授業料の安かった大学に進み、そこで今私の横でベースを弾いているトミヨリ氏に出会った。その出会いは私にとっては劇的だった。ある日、大学へ行きしなの天王寺の駅の売店で、当時まだ百円だった大阪のローカルな情報誌を買ったのである。無作為に開けたページの欄外に一行の広告を見た。「民俗音楽の好きなパーカッショニスト求む」それはトミヨリ氏がメンバーを募集するために出した記事だった。私はそれをまさに神の啓示だと感じ、乗りかけた電車を降りて即座に電話した。こうしてわれわれのつきあいが始まったのである。彼はレゲエやラテンをはじめ、様々なブラック・ミュージックの素晴らしいコレクションの持ち主だった。当時彼はレゲエに心酔していて、私は勧められるままにそれを聞いた。初めは何とも居心地が悪かったが、そのうち心地よくなってきた。そのころはまだ、レゲエといっても余り知られておらず、ただ汚い身なりの人をさして言う言葉としてしか使われていなかったぐらいだったが、我々はそんな人々を後目に、忘れた頃にやってくるレゲエ・ミュージシャンのコンサートには欠かさず足を運んだ。レゲエは意識して聞いたはじめての肉体的な指向の音楽だった。その後、私は彼のコレクションの中からサルサを聞くようになり、ハイチのコンパやキューバのソンなどを聞いていくにつれ、それらのリズムの面白さに惹かれていくようになった。
何故ザイールの音楽に興味を持ったのかを書くはずだったが、とんだ寄り道をしてしまった。その後、一年間の浪人生活の末、日本一授業料の安かった大学に進み、そこで今私の横でベースを弾いているトミヨリ氏に出会った。その出会いは私にとっては劇的だった。ある日、大学へ行きしなの天王寺の駅の売店で、当時まだ百円だった大阪のローカルな情報誌を買ったのである。無作為に開けたページの欄外に一行の広告を見た。「民俗音楽の好きなパーカッショニスト求む」それはトミヨリ氏がメンバーを募集するために出した記事だった。私はそれをまさに神の啓示だと感じ、乗りかけた電車を降りて即座に電話した。こうしてわれわれのつきあいが始まったのである。彼はレゲエやラテンをはじめ、様々なブラック・ミュージックの素晴らしいコレクションの持ち主だった。当時彼はレゲエに心酔していて、私は勧められるままにそれを聞いた。初めは何とも居心地が悪かったが、そのうち心地よくなってきた。そのころはまだ、レゲエといっても余り知られておらず、ただ汚い身なりの人をさして言う言葉としてしか使われていなかったぐらいだったが、我々はそんな人々を後目に、忘れた頃にやってくるレゲエ・ミュージシャンのコンサートには欠かさず足を運んだ。レゲエは意識して聞いたはじめての肉体的な指向の音楽だった。その後、私は彼のコレクションの中からサルサを聞くようになり、ハイチのコンパやキューバのソンなどを聞いていくにつれ、それらのリズムの面白さに惹かれていくようになった。
そして、ある時ナイジェリアのアーティストである「キング・サニー・アデ」の音に接した。「ジュジュ・ミュージック」というそのスタイルの音楽は、何とも言い様のない複雑で躍動的なリズムの奔流だった。単調でひたすら一定のフレーズを繰り返し、呪術的な効果をもたらすベース・ラインの上に、シェケレとドラムの舞うような軽いリズムが踊っている。そこへ何本もの音程の違うトーキング・ドラムがからみつくようにしてリズムのうねりを出し、その波に乗って、たゆたう様な伸びやかなギター・フレーズや甘いヴォーカルとコーラスが陶酔を誘う。何とも今までに経験したことのないその繊細でかつ分厚いアンサンブルにすぐに虜になり、当時まだ手に入りにくかったその手のレコードを色々と物色するようになった。その過程でフェラ・クティの音楽や「フジ」、「アパラ」など、様々なアフリカもののレコードを手にするようになった。更にサニー・アデが来日し、怒涛のように日本全国にワールド・ミュージックのブームが渦巻いていった。バブル経済の初期、一九八〇年代前半のことである。
常に音楽活動を志していたわれわれは、トミヨリ氏ともう一人、向こうでギターを弾いている大西先生と三人で演奏を始めることにした。この三人だけのグループは、バンド名もなく、ただの一度のライブもやらずに、レゲエや、その手法のひとつである「ダブ」、ジュジュやファンクなどの技法を取り入れた即興演奏を、ただひたすら自分たちの好奇心を満足させる為にのみ演奏し、録音した。このグループは何年かの後、「カーリー・ショッケール」の結成の際にそこへ発展的解消を遂げることになる。
「カーリー・ショッケール」結成のいきさつ
 「カーリー・ショッケール」結成のいきさつもまた劇的だった。当時、我々は大阪のあるレコード店でそれらの音を手に入れていたのだが、そこには、その後カーリーの主要なメンバーになる何人かが集まってきていた。音楽バカなら誰でもやっている、いわゆる日曜日のレコード屋めぐりの途中で、顔見知りになった面々である。さて、そこに集まっていた奴等というのは、これがそろいもそろってひねくれ者で、「自分はサルサやレゲエが好きだ。」などと言っておきながら、ワールド・ミュージックのムーブメントに対しては、「どうせそんなものは、珍しいものを鵜の目鷹の目で世界中から引きずり出してきては使い捨てにする、一過性の消費文化に過ぎない。」などといって最初から批判的だった。だからブームに便乗して日本に輸入された、見せかけのアフリカ音楽は初めから相手にしていなかった。アフリカにも当然、ガキどものロック・バンドがあってしかるべきだと考えていた。「アフリカ人がロックをやったらすごかろうな。」それは自然に口をついて出た、我々の思いだった。その中に、のちに大阪名物のアフリカンDJとして名を馳せることになる「プロフェッサー・ピリピリ」というおやじがいた。彼は初めてのアフリカ音楽を遍歴する決死の旅行の過程で、タンガニーカ湖を不法越境しようとしてザイールの音楽に捕まった。それは、今にも割れそうになったザイール製のドーナツ盤だった。ピリピリが持ち帰ったそれを見て、我々はなんとも呆気にとられてしまった。曲名その他がフランス語で表記されていたからである。曲名「メリナ・パリジェンヌ」、演奏「オルケストル・ビバ・ラ・ムジカ」。オルケストル?、何とも仰々しいその名前に我々は滑稽ささえ感じた。バンド名なんて、「カン」とか「ファウスト」とか、短いのをもってよしとする私の美的感覚からすれば、とてもかけ離れたものだった。しかし、それに針が落とされた瞬間、そこにいたみんなはぶっとんでしまった。「こんな音楽があったのか。」それは、サニー・アデに接したときの驚きなどとは比べものにならなかった。まさにドラムとベースとギターと声の怒涛の洪水、明らかにロックだった。我々と同じようにロックの影響を受け、バンドやろうぜ、という感覚で始められた、我々が接する最初のアフリカのロックだった。無茶苦茶で過激でスピードがあって、破壊的で美しかった。要するに最高にご機嫌だった。先進国の奴等に媚びるとか、こうすれば売れるだろうなどという打算的なものが全く感じられず、ただ出したいだけのものを出したいだけ出したというのがありありと感じられるものだった。
「カーリー・ショッケール」結成のいきさつもまた劇的だった。当時、我々は大阪のあるレコード店でそれらの音を手に入れていたのだが、そこには、その後カーリーの主要なメンバーになる何人かが集まってきていた。音楽バカなら誰でもやっている、いわゆる日曜日のレコード屋めぐりの途中で、顔見知りになった面々である。さて、そこに集まっていた奴等というのは、これがそろいもそろってひねくれ者で、「自分はサルサやレゲエが好きだ。」などと言っておきながら、ワールド・ミュージックのムーブメントに対しては、「どうせそんなものは、珍しいものを鵜の目鷹の目で世界中から引きずり出してきては使い捨てにする、一過性の消費文化に過ぎない。」などといって最初から批判的だった。だからブームに便乗して日本に輸入された、見せかけのアフリカ音楽は初めから相手にしていなかった。アフリカにも当然、ガキどものロック・バンドがあってしかるべきだと考えていた。「アフリカ人がロックをやったらすごかろうな。」それは自然に口をついて出た、我々の思いだった。その中に、のちに大阪名物のアフリカンDJとして名を馳せることになる「プロフェッサー・ピリピリ」というおやじがいた。彼は初めてのアフリカ音楽を遍歴する決死の旅行の過程で、タンガニーカ湖を不法越境しようとしてザイールの音楽に捕まった。それは、今にも割れそうになったザイール製のドーナツ盤だった。ピリピリが持ち帰ったそれを見て、我々はなんとも呆気にとられてしまった。曲名その他がフランス語で表記されていたからである。曲名「メリナ・パリジェンヌ」、演奏「オルケストル・ビバ・ラ・ムジカ」。オルケストル?、何とも仰々しいその名前に我々は滑稽ささえ感じた。バンド名なんて、「カン」とか「ファウスト」とか、短いのをもってよしとする私の美的感覚からすれば、とてもかけ離れたものだった。しかし、それに針が落とされた瞬間、そこにいたみんなはぶっとんでしまった。「こんな音楽があったのか。」それは、サニー・アデに接したときの驚きなどとは比べものにならなかった。まさにドラムとベースとギターと声の怒涛の洪水、明らかにロックだった。我々と同じようにロックの影響を受け、バンドやろうぜ、という感覚で始められた、我々が接する最初のアフリカのロックだった。無茶苦茶で過激でスピードがあって、破壊的で美しかった。要するに最高にご機嫌だった。先進国の奴等に媚びるとか、こうすれば売れるだろうなどという打算的なものが全く感じられず、ただ出したいだけのものを出したいだけ出したというのがありありと感じられるものだった。
「これはアフリカのパンクだ。」とまで言った奴がいる。「オルケストル・ビバ・ラ・ムジカ」、その格式張った仰々しい名前も、何となくすんなりと受け入れられるようになった。それからしばらくして、日本盤で彼らのアルバムが紹介されることになる。タイトルは「ベロティ」。これはあのドーナツ盤よりもいっそう強烈だった。それを聞いて、みんなが初めて聞いたときの自分たちの印象が間違っていなかったことを確認した。明らかに彼らは、ブームに乗って自分たちの音楽を切り売りしようとしているのではなく、自分たちの音のスタイルにプライドを持っていた。そのことが我々をつき動かした。それまでの我々は、救いようのない音楽バカであり、ある者はレコード・コレクターであったけれども、スタンスはあくまでも「聞き手」だった。落ち着いて良い音楽を聴くという立場を出るものではなく、みんなそれなりにミュージシャンとしての経験を積んできていたにも関わらず、あまり身を入れてやろうとは考えていなかった。しかし、そのドーナツ盤を聴いたとき、少なくとも私は、じっと安閑として聞いていられない、何か切なさに近いものを感じた。「これをやらずにはいられない。」この感じは、個人的に差はあるものの、その後メンバーとなったみんなが感じたことである。誰からともなく、これをやってみようかという事になった。それが我々の音楽活動の始まりである。このように「カーリー・ショッケール」は、実に自然発生的なバンドだった。今から思うに、自然にグループが出来上がることなんて、私の人生のうちで、もう二度とないに違いない。

「リンガラ・ポップス」その尽きぬ魅力
さて、ではそんな彼らの音楽とはわかりやすくいうとどんなものか。音楽を言葉で表現することにはもともと無理があるので、聞いてもらわないと何とも言えないのだが、スタイルとして彼らの音楽の根底にあるものは、ルンバである。これはいうまでもなくキューバに生まれ、カリブ海沿岸で育ったラテン・アメリカの音楽に共通する、独特の音楽的ニュアンスのことである。歴史的には、一九六〇年に独立を果たしてから、「ザイール共和国」では、いや当時は「コンゴ民主共和国」、そしてややこしいことに、今では再び「コンゴ民主共和国」だが、とにかくそこでは独立を喜ぶ楽天的な雰囲気から、かつてはアフリカに起源をもっていたキューバ音楽がどっと逆流し、全土で演奏されるようになった。それは、ザイールに限らず、アフリカの年と呼ばれた当時独立を果たしたほとんどすべての国々で、広く演奏されていたようである。
ザイールでは、それらは初めのうちはそのままの形で演奏されていたが、そのうちその形式を徐々に打ち破って、彼らならではの感覚がみられるようになる。つまりそれまでは、多くは彼らの母国語ではないスペイン語で、マンボやチャチャがそのままの短い歌曲として演奏されていたのだが、そのうち歌の部分が彼らの共通語であるリンガラ語に変わり、その言葉のリズムに合わせて演奏のリズムやニュアンスも変わり、歌曲のままでは短かすぎて心ゆくまで踊れないからというので、独立したダンスパートが歌の部分の後につけられるようになった。さらに、そのダンスパートに至るためにはそれなりの盛り上がりが欲しいということで歌の部分が長くなったり、カダンスと呼ばれる歌とダンスの中間的な部分が挿入されたりして、さらに演奏時間が長くなり、そのうちにシャープなラテン的なニュアンスの角も取れていって、今の形になってきたのである。
 「フランコ」と呼ばれた、今は亡きかつてのザイールの超大スター、ルアンボ・マキアディはイギリスのあるテレビのインタビューに答えて次のように言っている。「ヨーロッパやアメリカのロックよりも我々の音楽の方が何倍も優れている、ロックなんて二、三分も経ったら終わっちまうじゃないか、その点われわれのは違う、何十分も、場合によっては何時間も楽しむことが出来る。」インタビュアーは明らかに話をどうつないでいいのか困っていたが、要するに彼らの価値観では、音楽による陶酔をいかに盛り上げていって適度に長い時間もたせるかということが重要なのであって、歌詞によるメッセージ性や実験的な音楽性はそれに比べれば二の次とされていたのである。つまり、踊れない曲はいかに優れた歌詞を持っていても認められない。そうした、一種上流階級のサロン的な社交ダンスのBGMとしての風潮は、一九七〇年代の終わり頃まで続いていたようである。しかし、ザイールにも当然ロックを聴いて育ったガキどもがごまんといたから、彼らのうちで運良く芸能界入りを果たしたものから順番に、そうした風潮に檄を加えるものが出はじめた。
「フランコ」と呼ばれた、今は亡きかつてのザイールの超大スター、ルアンボ・マキアディはイギリスのあるテレビのインタビューに答えて次のように言っている。「ヨーロッパやアメリカのロックよりも我々の音楽の方が何倍も優れている、ロックなんて二、三分も経ったら終わっちまうじゃないか、その点われわれのは違う、何十分も、場合によっては何時間も楽しむことが出来る。」インタビュアーは明らかに話をどうつないでいいのか困っていたが、要するに彼らの価値観では、音楽による陶酔をいかに盛り上げていって適度に長い時間もたせるかということが重要なのであって、歌詞によるメッセージ性や実験的な音楽性はそれに比べれば二の次とされていたのである。つまり、踊れない曲はいかに優れた歌詞を持っていても認められない。そうした、一種上流階級のサロン的な社交ダンスのBGMとしての風潮は、一九七〇年代の終わり頃まで続いていたようである。しかし、ザイールにも当然ロックを聴いて育ったガキどもがごまんといたから、彼らのうちで運良く芸能界入りを果たしたものから順番に、そうした風潮に檄を加えるものが出はじめた。
あの、我々が感動したオルケストル・ビバ・ラ・ムジカのドンとして、若い連中に絶大な支持を得ることになる「パパ・ウェンバ」もその一人だった。彼がビバ・ラ・ムジカを結成したのは一九七八年である。彼は、と「ザイコ・ランガ・ランガ」という老舗のグループから、反旗をひるがえす形で同志を引き抜いて独立したのだが、彼のやりたかったことはただひとつ、おじん臭いルンバに対する反撃だった。様々な苦労があったようだが、何年かの後にはビバの音楽は若い連中に絶大な支持を得るようになり、一九八〇年代中頃には押しも押されもしないザイールのトップ・バンドに成長したのである。歴史的には大体以上のような経過を経てきた音楽だったのだが、内容的にはおおむね次のようなものである。いかにロック的な手法が多く用いられるようになったとはいえ、音楽のニュアンスの根底を形作っているものは基本的にルンバである。
具体的には、多くのラテン・アメリカの音楽がそうであるように、リズムの基礎をなすものはクラーベである。これは、ごくシンプルなマンボの歌曲を聴けば、クラベスという一種の拍子木が刻んでいるリズムがすぐに聞き取れるが、あのリズム・パターンのことである。クラーベがリズムの基本をなしているという事はことのほか大切で、ロックの持つエイト・ビートが、いわば時間をぶった切っていく感覚に似ているのに対して、クラーベは延々と周りながら螺旋状に時を重ねていく感覚に似ている。それを大切にしているのは、やはり彼らの音楽も第一義にダンス・ミュージックだからである。そのラテン的な要素をベースに、彼らの出身部族特有の歌い回しが、音楽形式にアフリカ的な微妙な影響を及ぼし、しかも演奏している奴等の精神性がロックなのである。だからこそ面白いのである。聞いたことのない人には説明のしようがないが、クラーベを基本としたラテン的要素という点では、今ではすっかり日本でもポピュラーになったサルサに似ている。しかし、あれほど複雑な形式美を追求するシャープな音楽ではなく、よりまったりとした、歌が中心の、どちらかというと太くて重い感覚の音楽で、そこがアフリカ的である。アフリカ的という点ではさらに、ドラムやコンガの使い方、ギターやベースの音色や間の取り方が民俗音楽に近い。しかし、そのギターの弾き方やボーカルのがなり方やダンスのスタイルは明らかにロック精神を感じさせられる。ああ、かえってわかりにくくなった。つまり、そのような多様な要素が渾然一体となって光り輝いているところが魅力的なのである。
ひねくれ者の我々からすれば、もはやありきたりなロックなんて、ガキじゃあるまいしやりたくもない。かといって、そこにいた連中はそろいもそろって自分はミュージシャンだと豪語してやまないくせに、楽譜ひとつ読むことも書くこともできないくらい、鍛錬というものから縁遠い存在だった。だから今更サルサみたいなテクニックを厳しく要求されるような音楽など、やってみたいのは山々だが出来るはずがないし、それを修得するまでの我慢に耐えられるはずも、その気もない。それでも我々の知的好奇心は、より深みのある、何か別の音楽形式を模索してさまよっていたから、この、ラテンとアフリカとロックという三つの要素が、渾然一体となってマグマのようにどろどろに燃えたぎっている音楽を聴いたとき、「これしかないわ」と思ったのである。ちょっと難しそうだが、気持ち一発で何とかなるだろうと思った。しかしそれは大きな間違いだった。それに気づいた頃には時すでに遅く、どうにも抜けられない泥沼の中にいた。まさに怒涛のように分厚い流れとなって、メロディもハーモニーもリズムも、うねりながら絡み合って奈落の底にまっ逆さまに落ちていくような、破壊的でスピード感あふれるその音楽の滝壷の中で、我々はお互いの顔を見合わせるばかりだった。
「カーリー・ショッケール」の結成と地獄の始まり
ザイールのその手の音楽は、リンガラ語で歌われているところから、日本では「リンガラ・ポップス」と呼ばれている。しかし国際的に認知された呼び名は、「スークース」、あるいは「スーク・ズーク」という。最近では「ルンバ・リンガラ」などという言い方も見られ、また古くフランコの時代には、「アフリカン・ジャズ」とも呼ばれていた。私はこのなかで、日本名の「リンガラ・ポップス」という呼び方が好きだ。というのは、歪んでいながらキラキラする、この音楽を特長づけるそのギターの音色を連想させるのに、全くふさわしい呼び方だからである。
その後、そのレコード店には、数々のリンガラのレコードが入荷するようになった。最新のものもあれば、何年も前に出されていながら、長らくどこかの国の倉で眠っていたとおぼしきものもあった。それらは、初めはどれを聞いても大体同じに聞こえたものだが、そのうち微妙な違いに気づきはじめた。考えてみれば、このこと、すなわち、「違いがわかりはじめる」というのが、もののコレクターなら誰でも陥る地獄の始まりだった。テンポの速いバンド、失速寸前の微妙なのりを維持し続けるバンド、歌の華麗なもの、しぶいもの、様々な特徴があった。しかしどれも、ギターやスネアやシンバルの音がきらきらしている点では共通していた。その音はアフリカの音楽に対する我々の先入観を一掃させた。その音は非常に洗練されていて、涙が出るほど、また腰が落ち着いていられないほどにかっこよかった。聴けば聴くほどのめり込んでいった。当時、まだトミヨリ氏と大西先生と三人で、名前のないバンドをやっていた我々は、どうすればあんな音が出るのか話し合ったものである。あのギターのキラキラや、従来の私が見聞きしたどの奏法にもない、全く常識を覆すようなドラムのたたき方は、我々にとって全くの謎だった。その時点では手探りだったのである。ギターが何本鳴っているのかさえわからなかった。皮を打つようなあの中低音は、ドラムのタムタムなのかコンガなのかさえ聞き分けられなかった。従来我々が親しんできたロックのように、リズムとメロディとハーモニーが、明確に分離されているわけではないからである。
レコードだけを頼りに、耳を皿のようにして音を探っていたその頃、一九八六年のことだったが、そのビバ・ラ・ムジカが来日した。折りもおり、世の中はワールド・ミュージック大旋風のまっただ中だったのである。多くのにわかファンに混じって、我々三人と、のちに我々と共にカーリーを結成することになる何人かの連れが、一緒に、かなり前の方でステージを凝視した。我々のほとんどが、それぞれのミュージシャンの手や足をじっと睨み付けたまま、埴輪のように硬直していたのはいうまでもない。そこで我々の誰もが、彼らがいとも簡単に謎のフレーズを紡ぎ出すのをこの目で見た。私もドラマーがなんの苦もなくあのリズムをたたき出し、パーカッショニストがやはりこともなげに、まるでお遊びの様に、あのどうしても出来なかったうねりを出しているのをこの目で見た。きっと非常に緻密に細かく決められたルールに基づいて、バック陣は真剣に演奏しているものとばかり思いこんでいた私は、彼等がどちらかというと気ままに、はっきり言っていい加減な態度で、だらだらと演奏を続けているのを見て呆気にとられた。まるで目から鱗の落ちた思いだった。ほかの人たちはそうでもなかったようだが、私は絶え間なく流れてくる様々なリズム・バリエーションの洪水に、ゆっくり歌やダンスを楽しむどころではなかった。
まだこの頃は、ダンスというものについて、私はなんの興味もなく、彼らの音楽も、手や足でリズムを取りながら聞いていたのである。しかし、そんな聞き方が実は間違いで、本当にそのリズムの中に入り込もうと思ったら、全身で踊り狂わざるを得ないと思い知るのは、実はザイールへ行ってからのことである。とにかくプレーヤーとして、奏法上のあるきっかけをつかんで、我々はそこを出た。しかし、スタジオに入っていざやってみると、あれほど簡単に見えたものがなかなか出来なかった。見るとやるとでは、本当に大違いだった。しかし、全くの謎だったものが、おぼろげながらも見えてきたことだけは確かである。我々は、彼らが手をどう動かしていたかをなるべく思い出しながら、セッションを繰り返した。しかしどう考えても、たった三人では面子があまりにも足りなさすぎた。三人ともボーカルには全く不向きだったし、ベースやドラムは、マシーンに頼っていて、私はパーカッションを入れていたから、音の骨格部分に融通がなく、変化をつけようにも何かにつけて限界があったのである。
 当時、件のレコード店に集まっていた連中は、プロフェッサー・ピリピリを中心にして「ノン・ストップ・カイマン」というバンドをやっていたが、ちょうど我々がいつまでもこんなことをやっていても仕方がないと感じはじめていたその頃、そのバンドがミュージシャンの音楽性の違いから解散することになった。さらに昨年に続いて、ビバが新メンバーで二度目の来日を果たし、相前後して老舗の「ザイコ・ランガ・ランガ」も来日した。このように、レコードだけでなく、実際の演奏をこの目で見るようになり、さらにかたことながら、リンガラ語で彼らとのコミュニケーションが取れるようになると、きちんとしたバンドでこの音楽を演奏したいという、我々の想いは一層強くなった。そうして紆余曲折を経て、「ノン・ストップ・カイマン」のメンバーの一部と我々三人とで、「カーリー・ショッケール」が結成されることになった。一九八六年のことである。バンド名の意味は、少し言うのははばかられるが、「カーリー」とは日本語の「仮」のことで、これは仮性包茎の仮と、男のアレの先っちょの、女を最も感じさせることの出来る部分の名前とのかけことばからなっている。「ショッケール」はザイール人がよく使うフランス語のスラングで、ごろつきとか危ない奴とか、何でもやってしまう無鉄砲な男をさしている。つまり、「カーリー・ショッケール」とは、仮性包茎のくせにやってしまう奴等、転じて、自分の無能を棚に上げてなんでもやってしまう奴等、という意味である。断わっておくがこの名前は私が付けたのではないし、メンバーにはそんな下品な奴はひとりもいない。
当時、件のレコード店に集まっていた連中は、プロフェッサー・ピリピリを中心にして「ノン・ストップ・カイマン」というバンドをやっていたが、ちょうど我々がいつまでもこんなことをやっていても仕方がないと感じはじめていたその頃、そのバンドがミュージシャンの音楽性の違いから解散することになった。さらに昨年に続いて、ビバが新メンバーで二度目の来日を果たし、相前後して老舗の「ザイコ・ランガ・ランガ」も来日した。このように、レコードだけでなく、実際の演奏をこの目で見るようになり、さらにかたことながら、リンガラ語で彼らとのコミュニケーションが取れるようになると、きちんとしたバンドでこの音楽を演奏したいという、我々の想いは一層強くなった。そうして紆余曲折を経て、「ノン・ストップ・カイマン」のメンバーの一部と我々三人とで、「カーリー・ショッケール」が結成されることになった。一九八六年のことである。バンド名の意味は、少し言うのははばかられるが、「カーリー」とは日本語の「仮」のことで、これは仮性包茎の仮と、男のアレの先っちょの、女を最も感じさせることの出来る部分の名前とのかけことばからなっている。「ショッケール」はザイール人がよく使うフランス語のスラングで、ごろつきとか危ない奴とか、何でもやってしまう無鉄砲な男をさしている。つまり、「カーリー・ショッケール」とは、仮性包茎のくせにやってしまう奴等、転じて、自分の無能を棚に上げてなんでもやってしまう奴等、という意味である。断わっておくがこの名前は私が付けたのではないし、メンバーにはそんな下品な奴はひとりもいない。
さて、面子がそろったとはいっても、出来ないものはやはり出来なかった。全く鍛錬のなかった我々でさえ、色濃くブルー・ノートを引きずっていたから、それとはまるで違う情感を表現するにあたって、ギタリストやベーシストはどう運指すればよいのかさえさっぱりわからず、ドラマーやパーカッショニストは両手両足を動かす順番を考えるのに気が狂いそうになった。そんな中で、リード・ギタリスト、我々の世界では「ソロ」というが、その大西先生はいち早くきっかけをつかんで、一定のニュアンスを出せるようになった。しかし、問題はリズム・ギター、我々の世界では「アコンパニュマン」、略して「アコンパ」をどう弾くべきかだった。ソロのように派手に表に出て騒がない分、演奏は全体のアンサンブルの中に溶け込んで聴き取りにくかった。味噌汁でいえば、ダシのようなものである。フレーズとして音を取ることはなんとか出来るが、コードが取れなかったので、自分たちの音楽の中に応用するのが難しかった。アコンパがコードをストロークで演奏することは滅多になかったからである。
当時ドラムを担当していた奴も、コンガをたたいていた私も、リズムの山がつかめずに苦労していた。ドラマーが拍子の頭を中心にリズムを構成することは滅多にないし、コンガに至ってはもっと気まぐれだったからである。全体のリズムが、どこから始まってどこで終わっているのかさえわからないことも多かった。その点、ベーシストのトミヨリ氏はマイペースだった。それは今でも変わらないが、実に着実に音の特徴をつかみ、自分の音楽の中に生かしていった。これは大したもんだった。
残るは歌を担当するボーカリスト、我々の世界では「シャンテール」というが、最も中心となるべき彼らに至っては悲惨だった。合唱というものに縁のなかった彼らは、簡単な長調でハモることさえままならなかったし、なんといっても、日本語の歌詞ではリンガラの情感がさっぱり出せなかった。どうしても行進曲になった。まるで、四拍子の一拍目で拳を降りおろしながら軍歌を歌っているかのようだった。
さらにバンド全体の演奏に至っては、悲惨きわまりなかった。演奏が始まっても、まるで六角形の車輪で作った代八車みたいに、どたばたと不快な音がしばらくしたかと思うと、全体がバラバラになってへたり込んでしまったからである。カーリー・ショッケール結成当初なんて、こんな有り様だった。それでも諦める人間は一人もいなかった。まずは、間違えても演奏をやめないこと。我々が最初に取り組んだのはそんなことだった。そのうちなんとかなるだろうと思ったからである。
さらなる地獄、そして泥沼
しかし、なんとかなる日は遠かった。ひとつの問題を克服したと思ったら、また別のより深刻な問題が行く手を阻んだからである。初めの課題は、いかにオリジナルとはいえ、最も基本的なルンバののりをどうやって出すかだった。次は、日本語で歌うことによるダサさをどう克服するかだった。なんとか止まらずに演奏できるようになるまでに半年、お義理とはいえ、まばらな拍手をもらえるようになるまでに、さらに半年かかった。次第に問題点が明らかになっていった。その頃には、確かに各自が各様に、なんとかそれらしいフレーズを演奏できるようにはなっていた。それぞれどこをとっても、特におかしいところはないようだった。しかし、全体で演奏したときに、それらはまるで水と油のように反目し合った。音楽になっていないのである。何故出来ないのか誰にもわからなかった。責任の擦り会いから、犬も食わんような喧嘩に発展したこともある。「お前が足を引っ張るから、俺が引きずられるんや。」「アホゥ、人のせいにすな。お前がちゃんとキープしとかな、わしフレーズ考えられへんやんけ。」「なにゆうてんねん。やるたんびにちゃうことひきやがって。遊んどぉだけのくせにえらそうなことゆうな。」「ほななにかい?、いっつも決まったことだけやっとれちゅうんかいや、そんなおもんないバンドやったら今すぐやめたるわい。」果たして、どの言い分が正しいのかわからなかったが、わからないままに、見えない壁に向かって足を滑らせる時期がさらに一年ほど続いた。メンバーのあせりも次第に募ってきた。
そんなある日、ソロとアコンパのギタリストは、あるレコードをヘッド・ホンで聞いていて、それぞれが別のリズムの取り方で演奏することを思いついた。つまり、ソロが拍子の頭を中心にフレーズを構成していくとすれば、アコンパは、それを縫うように、拍子の裏を中心にフレーズを構成するといった具合である。この発見は我々にひとつのヒントを与えた。ソウルといいブルースといい、およそ黒人のやる全ての音楽に、そんなやり方があることを思い出したからである。そうしてベースとドラムが絡み、私も低音を中心にのりを下から支えるように演奏しはじめた。しかし依然として、実体はとてもまろやかなルンバなどとは言えず、クソやかましいドンシャリに過ぎなかった。私は元来気の短い性格である。結成して半年後には、その見えない壁にぶちあたり、さらに半年後には、ここでじたばたしても時間の無駄だと感じ、ザイール行きを決心していた。広瀬大先生の『やさしいリンガラ語』という本を買ってきて勉強を始めた。要らぬレコードや、金目のものを売り払い、モヤシと鳥の皮を食って食費を切り詰め、会社を辞めて短期間で金になる仕事に就いた。演奏面では、自分に対するあせりと怒りと不満で暗澹たる気持ちだったが、その後輸入された様々なリンガラのレコードにも耳を通していたから、その分彼の地へのあこがれは募る一方だった。自分たちの演奏の不出来に暗い思いがよぎると、はじめてビバを聞いたときの、あの感動を思い出して気を取り直した。あの何とも言えぬ、粗野で武骨ながら、繊細でエレガントな音の洪水を思い出すたびに、その音楽が実際に鳴り響いているまだ見知らぬ国のことを思い浮かべては胸を弾ませていた。
実際に行くことを決心した後は、空想がもっともらしい現実性を帯びてきた。プロフェッサー・ピリピリや、その他の彼の地へ行ってきた人々から話を聞いた。また、ベロティ発売以降、リンガラ・ポップスのレコードが日本盤で発売されることも多くなってきたから、そのライナー・ノーツに書かれている彼の地の事情を読んでは、想像をたくましくしていた。なんといっても国名や首都の名前が空想をかきたてた。「ザイール」・・・その名は余りにもゆったりとしたときの流れや、行けども行けども果てしない広大な大地を、そして鬱蒼としただだっ広いジャングルを、そこに闊歩する魑魅魍魎を、また一筋縄では行かない一種独特な混沌と複雑さを連想させた。その首都「キンシャサ」・・・この名もまた、光り輝く灼熱の太陽と、リンガラ・ポップスのキラキラ光る感触と、アフリカ大陸の大都会という我々には計り知れない危険な予感と、それが故にあらゆるジャングルから混沌が吸い寄せられて鈍く光っているスリリングな空気を連想させた。行ってみるに足る土地、かけてみるに値する旅と思われた。過酷な労働と悲惨な節約のおかげで、程なく実現できそうになった。出発は、一九八九年の二月と見通しを立てた。エア・チケットが最も安くなるシーズンだからである。
キンシャサ行きの具体的な準備にはいる
その前年の秋から、具体的な準備にとりかかった。初めての海外旅行だったから、一体どんな準備が必要なのかまるでわかっていなかったので、エア・チケットを予約した旅行代理店に一から教えてもらうことになった。まず彼らに注意されたことは、ザイール行きは、それ自体大変な苦労を伴うものなので、十分に気を引き締めてかかれということだった。その点では迷いはなかった。さらにビザを申請する前に、すべての手続きを終わらせておく必要があった。秋からやっておけば十分だろうと考えていたが、逆算していくとそうでもなかった。私はパスポートすら持っていなかったからである。その発給に二週間かかった。次に、二種類の予防接種が必要だった。まずコレラについては、一週間以上あけて二回、黄熱については、コレラの二回目の予防接種から三週間以上あけて一回と定められていた。これだけでさらに一ヶ月以上かかることになる。それらが全部揃った上で、最終のビザの申請だった。これもザイールのことなので日本人に比べて実に悠長なもんだから、一ヶ月前後はかかるだろうと言われた。私が準備を始めたのが前年の一〇月のことだったが、年末年始の休みを挟んで結果的にすべての手続きが終了したのは、出発予定日まぎわのことだった。計画は具体的に動きはじめた。チケットはケニアのナイロビまではツアーに便乗し、そこからザイールのキンシャサまではナイロビで何とかするということになった。日本から手配するのは、様々な困難があるからである。彼らは、「そんなの簡単ですよ。」と言っていたが、全く勝手の分からない私は、気が気ではなかった。
ピリピリは当時、大阪からザイールへ行ったうちの一人で、年長ということもあってか、事細かに私に対して心構えを諭した。何も知らない私は、まだ彼の性格もよくわかっていなかったから、彼の話をすべて鵜呑みにした。「ザイール人たちは大変プライドが高いので汚い格好を嫌うから、どこへ行くにも、またいかに暑くとも、スーツをビシッと決めて、決してなめられないようにしなければならない。だから、スーツを出来るだけ持って行った方がよい。」私は言う通りにした。しかし実際はそうではなかった。ザイール人達が大変誇り高い連中だったことは事実である。しかし、あんなクソ熱い灼熱の地獄でスーツなど着込んで歩いている奴など、よっぽどのチンピラかスターくらいのものだった。まだある。彼は、「ザイール人達は大変な日本人贔屓で、向こうで誰に世話になるかも知れないので、不公平があってはいけないから、持てる限りたくさんのおみやげ、それもTシャツやベルトといったものを持って行った方がよい。」ということだった。私は言う通りにした。しかし実際はそうではなかった。ザイール人達が大変日本人贔屓でお洒落なことは事実である。しかし、そんなものを誰かひとりに与えると、噂が噂を呼んでそれを欲しがる奴がごまんと押し寄せてきた。その災難を克服するのに非常な困難を経験した。まだある。「ザイールと日本は、いやほかの諸外国もそうだが、特に日本は往来が少ないので、向こうの連中は日本人でザイールへ来た者の近況を大変知りたがっているはずだから、彼の地へ行った人に出来るだけ多く声をかけて手紙を書いてもらい、それを持って行った方がよい。」とのことだった。「それはかならずや彼の地でお前を救うことになるだろう。」という、予言めいた言葉まで口にした。私はその通りにした。しかし実際はそうではなかった。ザイール人達が大変義理深くて、かつて彼の地を訪れた人たちの名前を覚えていたことは事実である。しかし、ある日本人があるザイール人に宛てた手紙を届けるのに別のザイール人に案内してもらわざるを得なかったのだが、そのザイール人が自分には手紙がないことに不満を持ったため、そのことがもとでザイール人どうしの人間関係までこじれるというとんでもない厄介を、事情もわからぬ私が調停せざるを得なくなった。
彼の助言を素直にきいたおかげで、私は彼の地でやるために用意した、現地録音用のテープやフィルムなど、本来の自分の荷物を大幅に削られ、役にも立たないスーツやおみやげやかさばる手紙などに荷物を占領されたばかりか、彼の地での滞在中とんでもない困難と不自由を被ることになる。しかし考えてみれば、こうしたことの全てが、ザイールという国や人々や、この旅行そのものを思い出深いものにしたこともまた事実である。善意に解釈すれば、こうしたことの全体がザイールを思い知るのに格好の手段であると、彼が霊験あらたかな助言をもって教えてくれたのだと考えられなくもない。今でも、出発の前日に、「元気で行って来い。」と言った彼の顔を思い出すたびに、「このアホが」、という気になるのだが、今となっては済んでしまったことである。かくして私は、ダーク・スーツに身を包み、巨大なスーツケース二個のうちの一個を機内預けとし、もう一個と、さらに巨大なボストン・バッグを狭い座席に押し込んで、足を納める場所もない窮屈な姿勢のままで旅を始めたのである。それは誰が見ても滑稽な出で立ちだったに違いない。
homepage> congo> 旅行記> | 次ページへ
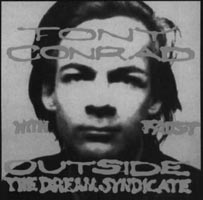 たしかあれは高校三年の頃だった。その悪友の一人から、あるテープを手に入れた。「トニー・コンラッド・ウィズ・ファウスト」。忘れもしないその音は、暗いと言うよりもごつごつに黒い音だった。しかもそれは、肉体的な黒さではなく、絶望的なまでに精神的な黒さだった。その黒さは暗さが極限にまで凝縮されて、どんな物質よりも固く、すべての光を吸い尽くし、自身の重さによって永遠に収縮し続けるかと思われるほどに深い黒、なにものの感情移入をもひたすら拒み続け、一切の人間的現実性をはるかに超越した純粋な意識を、厳しくこちらに突きつけてくるような冷徹で無機的な黒だった。気が遠くなるくらい単調で、背骨の芯から凍り付くような恐ろしさを持ったその音に、私は全身でのめり込んでいった。人と口をきかなくなり、物事の現実的な有り様や関連性が遠ざかっていった。音や光を現実のものとしてではなく、抽象的な概念としてとらえるようになり、時間と空間を意識できるようになった。ただ一人部屋にこもって、食事もとらず寝る間も惜しんでいつまでも繰り返しそのテープだけを聴き続ける日々が何日も続いた。両親が心配して様子を見に来ても一切応えず、ヘッド・ホンを両手で押さえ、アンプの前にかじり付いていた。そんなある明け方のことである。テープの両側にわずかにたるみがあらわれはじめたのを見て、それを何故かこの世界の終末と勘違いし、恐怖の余りまだ真っ暗な外へ飛び出して、大声を上げながら家の前の急な坂道を駆け下り、車でさえ三〇分はかかる、幼いころ自分の通っていた幼稚園の庭を一回りして、一歩も休まずに家まで走って帰って来た。驚いて起き出した両親の不安を後目に、猛烈な空腹感から台所にあった食料をあらかた平らげ、まだそんな時間でもないのに電車に乗って学校へ行った。相変わらず人とは口を利かない日々が続いたが、音楽を聴くのはそれきりぱったりとやめてしまった。何故か頭の中で何かが切れてしまって、すべてが相対的で、自分の存在にとってはどうでもよいことのように思われだした。あらゆるものが私自身との関連性を失い、バラバラに遠ざかっていくように思われた。そんな、空虚でなにものをも信じることの出来ない精神状態の中で受験に失敗した。
たしかあれは高校三年の頃だった。その悪友の一人から、あるテープを手に入れた。「トニー・コンラッド・ウィズ・ファウスト」。忘れもしないその音は、暗いと言うよりもごつごつに黒い音だった。しかもそれは、肉体的な黒さではなく、絶望的なまでに精神的な黒さだった。その黒さは暗さが極限にまで凝縮されて、どんな物質よりも固く、すべての光を吸い尽くし、自身の重さによって永遠に収縮し続けるかと思われるほどに深い黒、なにものの感情移入をもひたすら拒み続け、一切の人間的現実性をはるかに超越した純粋な意識を、厳しくこちらに突きつけてくるような冷徹で無機的な黒だった。気が遠くなるくらい単調で、背骨の芯から凍り付くような恐ろしさを持ったその音に、私は全身でのめり込んでいった。人と口をきかなくなり、物事の現実的な有り様や関連性が遠ざかっていった。音や光を現実のものとしてではなく、抽象的な概念としてとらえるようになり、時間と空間を意識できるようになった。ただ一人部屋にこもって、食事もとらず寝る間も惜しんでいつまでも繰り返しそのテープだけを聴き続ける日々が何日も続いた。両親が心配して様子を見に来ても一切応えず、ヘッド・ホンを両手で押さえ、アンプの前にかじり付いていた。そんなある明け方のことである。テープの両側にわずかにたるみがあらわれはじめたのを見て、それを何故かこの世界の終末と勘違いし、恐怖の余りまだ真っ暗な外へ飛び出して、大声を上げながら家の前の急な坂道を駆け下り、車でさえ三〇分はかかる、幼いころ自分の通っていた幼稚園の庭を一回りして、一歩も休まずに家まで走って帰って来た。驚いて起き出した両親の不安を後目に、猛烈な空腹感から台所にあった食料をあらかた平らげ、まだそんな時間でもないのに電車に乗って学校へ行った。相変わらず人とは口を利かない日々が続いたが、音楽を聴くのはそれきりぱったりとやめてしまった。何故か頭の中で何かが切れてしまって、すべてが相対的で、自分の存在にとってはどうでもよいことのように思われだした。あらゆるものが私自身との関連性を失い、バラバラに遠ざかっていくように思われた。そんな、空虚でなにものをも信じることの出来ない精神状態の中で受験に失敗した。 何故ザイールの音楽に興味を持ったのかを書くはずだったが、とんだ寄り道をしてしまった。その後、一年間の浪人生活の末、日本一授業料の安かった大学に進み、そこで今私の横でベースを弾いているトミヨリ氏に出会った。その出会いは私にとっては劇的だった。ある日、大学へ行きしなの天王寺の駅の売店で、当時まだ百円だった大阪のローカルな情報誌を買ったのである。無作為に開けたページの欄外に一行の広告を見た。「民俗音楽の好きなパーカッショニスト求む」それはトミヨリ氏がメンバーを募集するために出した記事だった。私はそれをまさに神の啓示だと感じ、乗りかけた電車を降りて即座に電話した。こうしてわれわれのつきあいが始まったのである。彼はレゲエやラテンをはじめ、様々なブラック・ミュージックの素晴らしいコレクションの持ち主だった。当時彼はレゲエに心酔していて、私は勧められるままにそれを聞いた。初めは何とも居心地が悪かったが、そのうち心地よくなってきた。そのころはまだ、レゲエといっても余り知られておらず、ただ汚い身なりの人をさして言う言葉としてしか使われていなかったぐらいだったが、我々はそんな人々を後目に、忘れた頃にやってくるレゲエ・ミュージシャンのコンサートには欠かさず足を運んだ。レゲエは意識して聞いたはじめての肉体的な指向の音楽だった。その後、私は彼のコレクションの中からサルサを聞くようになり、ハイチのコンパやキューバのソンなどを聞いていくにつれ、それらのリズムの面白さに惹かれていくようになった。
何故ザイールの音楽に興味を持ったのかを書くはずだったが、とんだ寄り道をしてしまった。その後、一年間の浪人生活の末、日本一授業料の安かった大学に進み、そこで今私の横でベースを弾いているトミヨリ氏に出会った。その出会いは私にとっては劇的だった。ある日、大学へ行きしなの天王寺の駅の売店で、当時まだ百円だった大阪のローカルな情報誌を買ったのである。無作為に開けたページの欄外に一行の広告を見た。「民俗音楽の好きなパーカッショニスト求む」それはトミヨリ氏がメンバーを募集するために出した記事だった。私はそれをまさに神の啓示だと感じ、乗りかけた電車を降りて即座に電話した。こうしてわれわれのつきあいが始まったのである。彼はレゲエやラテンをはじめ、様々なブラック・ミュージックの素晴らしいコレクションの持ち主だった。当時彼はレゲエに心酔していて、私は勧められるままにそれを聞いた。初めは何とも居心地が悪かったが、そのうち心地よくなってきた。そのころはまだ、レゲエといっても余り知られておらず、ただ汚い身なりの人をさして言う言葉としてしか使われていなかったぐらいだったが、我々はそんな人々を後目に、忘れた頃にやってくるレゲエ・ミュージシャンのコンサートには欠かさず足を運んだ。レゲエは意識して聞いたはじめての肉体的な指向の音楽だった。その後、私は彼のコレクションの中からサルサを聞くようになり、ハイチのコンパやキューバのソンなどを聞いていくにつれ、それらのリズムの面白さに惹かれていくようになった。 「カーリー・ショッケール」結成のいきさつもまた劇的だった。当時、我々は大阪のあるレコード店でそれらの音を手に入れていたのだが、そこには、その後カーリーの主要なメンバーになる何人かが集まってきていた。音楽バカなら誰でもやっている、いわゆる日曜日のレコード屋めぐりの途中で、顔見知りになった面々である。さて、そこに集まっていた奴等というのは、これがそろいもそろってひねくれ者で、「自分はサルサやレゲエが好きだ。」などと言っておきながら、ワールド・ミュージックのムーブメントに対しては、「どうせそんなものは、珍しいものを鵜の目鷹の目で世界中から引きずり出してきては使い捨てにする、一過性の消費文化に過ぎない。」などといって最初から批判的だった。だからブームに便乗して日本に輸入された、見せかけのアフリカ音楽は初めから相手にしていなかった。アフリカにも当然、ガキどものロック・バンドがあってしかるべきだと考えていた。「アフリカ人がロックをやったらすごかろうな。」それは自然に口をついて出た、我々の思いだった。その中に、のちに大阪名物のアフリカンDJとして名を馳せることになる「プロフェッサー・ピリピリ」というおやじがいた。彼は初めてのアフリカ音楽を遍歴する決死の旅行の過程で、タンガニーカ湖を不法越境しようとしてザイールの音楽に捕まった。それは、今にも割れそうになったザイール製のドーナツ盤だった。ピリピリが持ち帰ったそれを見て、我々はなんとも呆気にとられてしまった。曲名その他がフランス語で表記されていたからである。曲名「メリナ・パリジェンヌ」、演奏「オルケストル・ビバ・ラ・ムジカ」。オルケストル?、何とも仰々しいその名前に我々は滑稽ささえ感じた。バンド名なんて、「カン」とか「ファウスト」とか、短いのをもってよしとする私の美的感覚からすれば、とてもかけ離れたものだった。しかし、それに針が落とされた瞬間、そこにいたみんなはぶっとんでしまった。「こんな音楽があったのか。」それは、サニー・アデに接したときの驚きなどとは比べものにならなかった。まさにドラムとベースとギターと声の怒涛の洪水、明らかにロックだった。我々と同じようにロックの影響を受け、バンドやろうぜ、という感覚で始められた、我々が接する最初のアフリカのロックだった。無茶苦茶で過激でスピードがあって、破壊的で美しかった。要するに最高にご機嫌だった。先進国の奴等に媚びるとか、こうすれば売れるだろうなどという打算的なものが全く感じられず、ただ出したいだけのものを出したいだけ出したというのがありありと感じられるものだった。
「カーリー・ショッケール」結成のいきさつもまた劇的だった。当時、我々は大阪のあるレコード店でそれらの音を手に入れていたのだが、そこには、その後カーリーの主要なメンバーになる何人かが集まってきていた。音楽バカなら誰でもやっている、いわゆる日曜日のレコード屋めぐりの途中で、顔見知りになった面々である。さて、そこに集まっていた奴等というのは、これがそろいもそろってひねくれ者で、「自分はサルサやレゲエが好きだ。」などと言っておきながら、ワールド・ミュージックのムーブメントに対しては、「どうせそんなものは、珍しいものを鵜の目鷹の目で世界中から引きずり出してきては使い捨てにする、一過性の消費文化に過ぎない。」などといって最初から批判的だった。だからブームに便乗して日本に輸入された、見せかけのアフリカ音楽は初めから相手にしていなかった。アフリカにも当然、ガキどものロック・バンドがあってしかるべきだと考えていた。「アフリカ人がロックをやったらすごかろうな。」それは自然に口をついて出た、我々の思いだった。その中に、のちに大阪名物のアフリカンDJとして名を馳せることになる「プロフェッサー・ピリピリ」というおやじがいた。彼は初めてのアフリカ音楽を遍歴する決死の旅行の過程で、タンガニーカ湖を不法越境しようとしてザイールの音楽に捕まった。それは、今にも割れそうになったザイール製のドーナツ盤だった。ピリピリが持ち帰ったそれを見て、我々はなんとも呆気にとられてしまった。曲名その他がフランス語で表記されていたからである。曲名「メリナ・パリジェンヌ」、演奏「オルケストル・ビバ・ラ・ムジカ」。オルケストル?、何とも仰々しいその名前に我々は滑稽ささえ感じた。バンド名なんて、「カン」とか「ファウスト」とか、短いのをもってよしとする私の美的感覚からすれば、とてもかけ離れたものだった。しかし、それに針が落とされた瞬間、そこにいたみんなはぶっとんでしまった。「こんな音楽があったのか。」それは、サニー・アデに接したときの驚きなどとは比べものにならなかった。まさにドラムとベースとギターと声の怒涛の洪水、明らかにロックだった。我々と同じようにロックの影響を受け、バンドやろうぜ、という感覚で始められた、我々が接する最初のアフリカのロックだった。無茶苦茶で過激でスピードがあって、破壊的で美しかった。要するに最高にご機嫌だった。先進国の奴等に媚びるとか、こうすれば売れるだろうなどという打算的なものが全く感じられず、ただ出したいだけのものを出したいだけ出したというのがありありと感じられるものだった。
 「フランコ」と呼ばれた、今は亡きかつてのザイールの超大スター、ルアンボ・マキアディはイギリスのあるテレビのインタビューに答えて次のように言っている。「ヨーロッパやアメリカのロックよりも我々の音楽の方が何倍も優れている、ロックなんて二、三分も経ったら終わっちまうじゃないか、その点われわれのは違う、何十分も、場合によっては何時間も楽しむことが出来る。」インタビュアーは明らかに話をどうつないでいいのか困っていたが、要するに彼らの価値観では、音楽による陶酔をいかに盛り上げていって適度に長い時間もたせるかということが重要なのであって、歌詞によるメッセージ性や実験的な音楽性はそれに比べれば二の次とされていたのである。つまり、踊れない曲はいかに優れた歌詞を持っていても認められない。そうした、一種上流階級のサロン的な社交ダンスのBGMとしての風潮は、一九七〇年代の終わり頃まで続いていたようである。しかし、ザイールにも当然ロックを聴いて育ったガキどもがごまんといたから、彼らのうちで運良く芸能界入りを果たしたものから順番に、そうした風潮に檄を加えるものが出はじめた。
「フランコ」と呼ばれた、今は亡きかつてのザイールの超大スター、ルアンボ・マキアディはイギリスのあるテレビのインタビューに答えて次のように言っている。「ヨーロッパやアメリカのロックよりも我々の音楽の方が何倍も優れている、ロックなんて二、三分も経ったら終わっちまうじゃないか、その点われわれのは違う、何十分も、場合によっては何時間も楽しむことが出来る。」インタビュアーは明らかに話をどうつないでいいのか困っていたが、要するに彼らの価値観では、音楽による陶酔をいかに盛り上げていって適度に長い時間もたせるかということが重要なのであって、歌詞によるメッセージ性や実験的な音楽性はそれに比べれば二の次とされていたのである。つまり、踊れない曲はいかに優れた歌詞を持っていても認められない。そうした、一種上流階級のサロン的な社交ダンスのBGMとしての風潮は、一九七〇年代の終わり頃まで続いていたようである。しかし、ザイールにも当然ロックを聴いて育ったガキどもがごまんといたから、彼らのうちで運良く芸能界入りを果たしたものから順番に、そうした風潮に檄を加えるものが出はじめた。 当時、件のレコード店に集まっていた連中は、プロフェッサー・ピリピリを中心にして「ノン・ストップ・カイマン」というバンドをやっていたが、ちょうど我々がいつまでもこんなことをやっていても仕方がないと感じはじめていたその頃、そのバンドがミュージシャンの音楽性の違いから解散することになった。さらに昨年に続いて、ビバが新メンバーで二度目の来日を果たし、相前後して老舗の「ザイコ・ランガ・ランガ」も来日した。このように、レコードだけでなく、実際の演奏をこの目で見るようになり、さらにかたことながら、リンガラ語で彼らとのコミュニケーションが取れるようになると、きちんとしたバンドでこの音楽を演奏したいという、我々の想いは一層強くなった。そうして紆余曲折を経て、「ノン・ストップ・カイマン」のメンバーの一部と我々三人とで、「カーリー・ショッケール」が結成されることになった。一九八六年のことである。バンド名の意味は、少し言うのははばかられるが、「カーリー」とは日本語の「仮」のことで、これは仮性包茎の仮と、男のアレの先っちょの、女を最も感じさせることの出来る部分の名前とのかけことばからなっている。「ショッケール」はザイール人がよく使うフランス語のスラングで、ごろつきとか危ない奴とか、何でもやってしまう無鉄砲な男をさしている。つまり、「カーリー・ショッケール」とは、仮性包茎のくせにやってしまう奴等、転じて、自分の無能を棚に上げてなんでもやってしまう奴等、という意味である。断わっておくがこの名前は私が付けたのではないし、メンバーにはそんな下品な奴はひとりもいない。
当時、件のレコード店に集まっていた連中は、プロフェッサー・ピリピリを中心にして「ノン・ストップ・カイマン」というバンドをやっていたが、ちょうど我々がいつまでもこんなことをやっていても仕方がないと感じはじめていたその頃、そのバンドがミュージシャンの音楽性の違いから解散することになった。さらに昨年に続いて、ビバが新メンバーで二度目の来日を果たし、相前後して老舗の「ザイコ・ランガ・ランガ」も来日した。このように、レコードだけでなく、実際の演奏をこの目で見るようになり、さらにかたことながら、リンガラ語で彼らとのコミュニケーションが取れるようになると、きちんとしたバンドでこの音楽を演奏したいという、我々の想いは一層強くなった。そうして紆余曲折を経て、「ノン・ストップ・カイマン」のメンバーの一部と我々三人とで、「カーリー・ショッケール」が結成されることになった。一九八六年のことである。バンド名の意味は、少し言うのははばかられるが、「カーリー」とは日本語の「仮」のことで、これは仮性包茎の仮と、男のアレの先っちょの、女を最も感じさせることの出来る部分の名前とのかけことばからなっている。「ショッケール」はザイール人がよく使うフランス語のスラングで、ごろつきとか危ない奴とか、何でもやってしまう無鉄砲な男をさしている。つまり、「カーリー・ショッケール」とは、仮性包茎のくせにやってしまう奴等、転じて、自分の無能を棚に上げてなんでもやってしまう奴等、という意味である。断わっておくがこの名前は私が付けたのではないし、メンバーにはそんな下品な奴はひとりもいない。